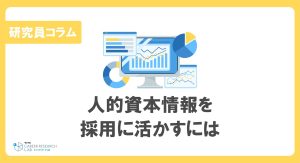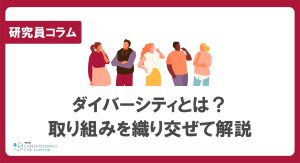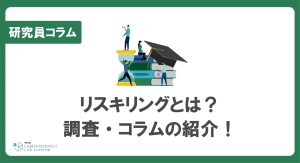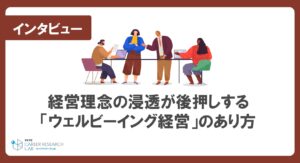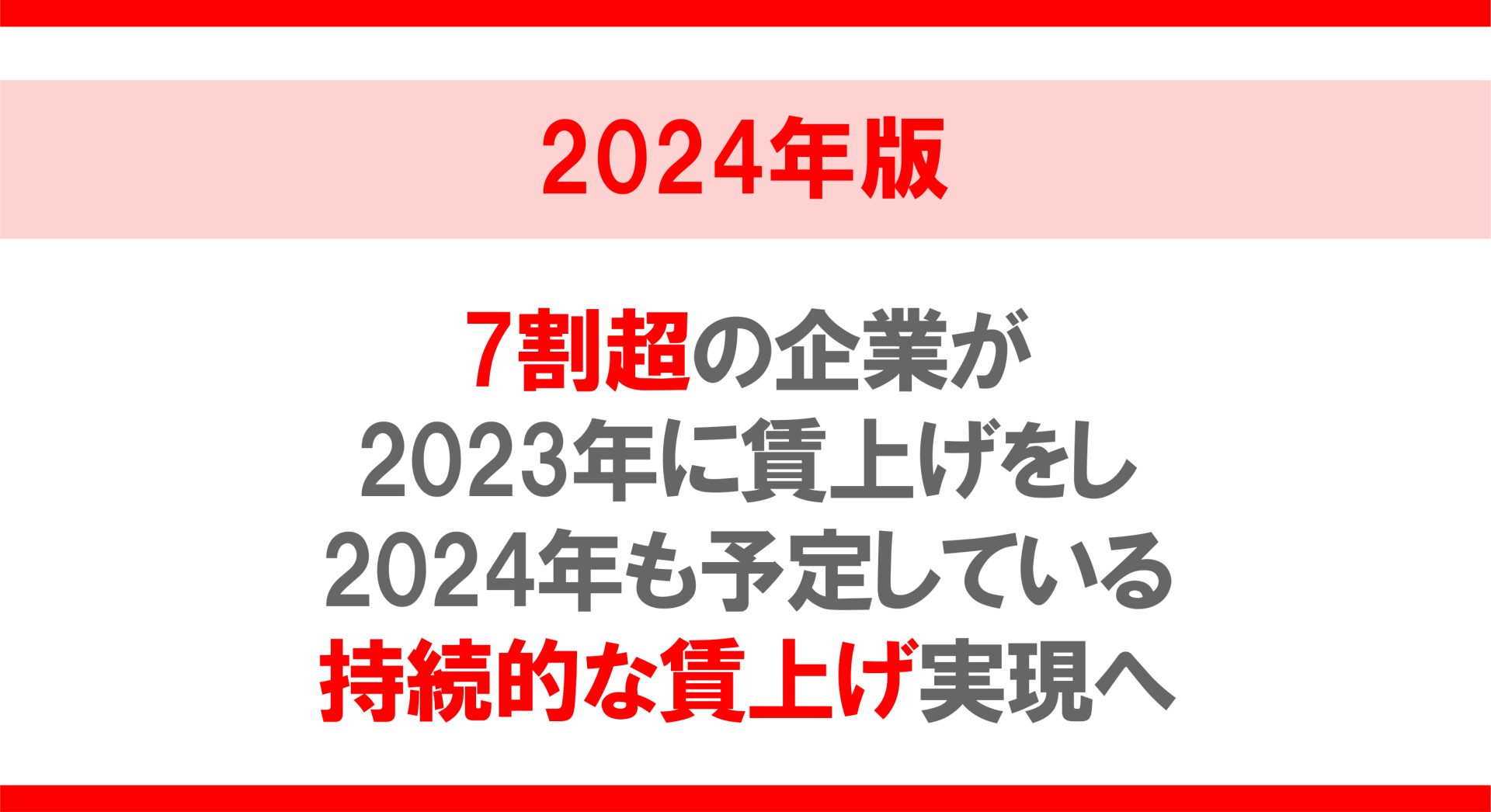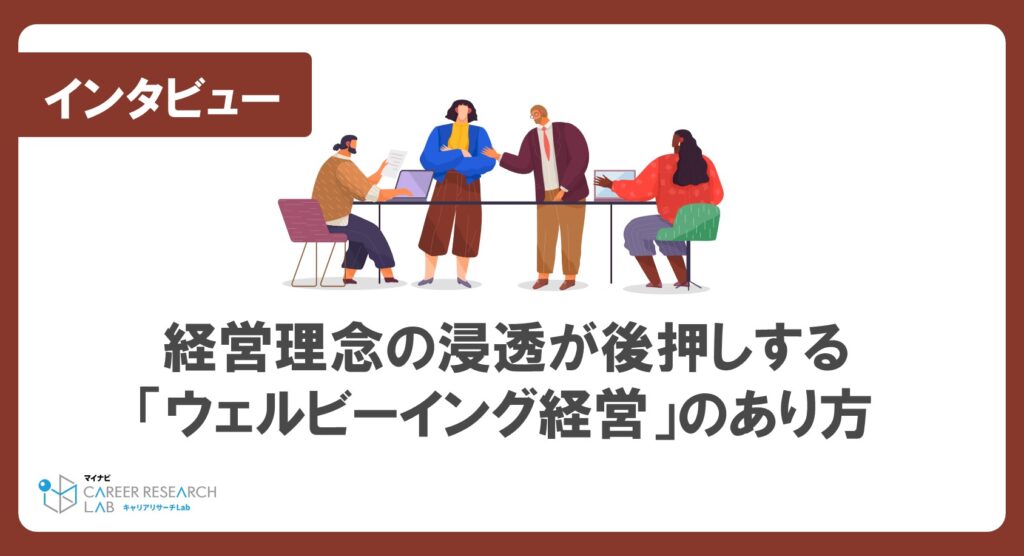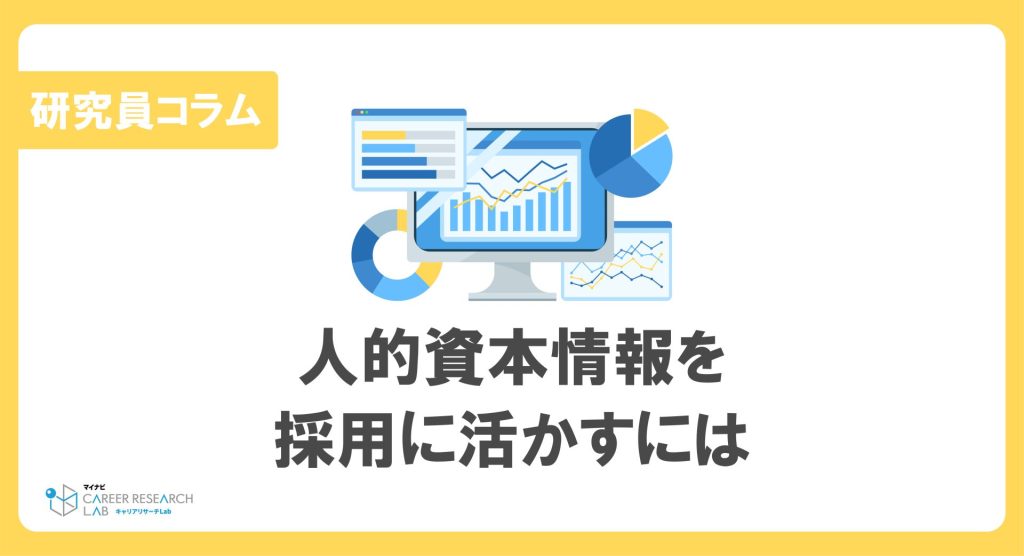
人的資本経営とは?ポイントとなる3つの視点と5つの要素も解説
企業にとって現代のビジネス環境では、IT技術の発展や労働市場の変化などに対応してイノベーションを起こせる優秀な人材を確保・育成することがまますます重要となっている。こうした背景の中、企業価値を中長期的に高めるための経営方法の一つとして「人的資本経営」への関心が高まっている。
本コラムでは、そんな人的資本経営について、経済産業省が公表した「人材版伊藤レポート」をベースに、注目されている背景や実践のための枠組みとして紹介されている「3P・5F」などを紹介していく。
目次 [もっと見る]
人的資本経営とは
人的資本経営は、経済産業省のホームページ*では、下記のように説明されている。
人材を『資本』として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方
経済産業省. (2025). 人的資本経営~人材の価値を最大限に引き出す~
人材の採用や育成、定着、配属など、人材戦略を最適化することで人材のパフォーマンスを向上させ企業価値を高めることを目指すのが人的資本の考え方だ。
従来まで、人材は「人的資源」と捉えられ、文字通り人材は資源として消費されるものとしていかに活用・管理するかという視点で考えられることが多く、育成などの人材にかける費用は「コスト」とされ、できるだけ抑えるものという発想になっていた。
しかし、人材は業務や職場環境によって成長して企業の価値創造を担い手となる存在であり、「人的資本」と捉える必要があるとしたのが「人的資本経営」の考え方だ。このような考え方になることで、マネジメントが目指すものは「人材の成長を通じた価値創造」に、人材に使用される金額や時間は価値創造のための「投資」になる。
注目されるきっかけとなった「人材版伊藤レポート」
上記の内容は「人材版伊藤レポート」と呼ばれる報告書でまとめられたことにより、注目されるようになった。2020年、経済産業省は「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」を開催し、企業価値を持続的に高めるための人材戦略が議論された。この際に検討された「人的資本」の重要性や人的資本経営をどのように実践するかについてまとめたのがこのレポートである。
2022年には内容をさらに深堀りする「人材版伊藤レポート2.0」が公表され、これらのレポートをきっかけに、人的資本経営の機運が高まることとなった。
人的資本経営が求められる理由
この人材版伊藤レポートでは、人材戦略を見直す必要がある理由として、企業や個人を取り巻く下記のような変化を挙げている。
- 第4次産業革命による産業構造の変化
- 少子高齢化や人生 100 年時代の到来
- 個人のキャリア観の変化
この変化の中で企業が直面するさまざまな経営課題を解決するためには、それらの課題と表裏一体である人材面の課題を解決する必要があり、企業はそれぞれの企業理念やパーパスを見直すことや、中長期にわたり企業価値を高めるための人材戦略に変えていくことが求められると指摘されている。
ここからは、人的資本経営が求められている理由となっている企業や個人を取り巻く変化について、上記のポイント以外のできごとも含めて見ていこう。
第4次産業革命の中でのイノベーションの必要性
近年、IoTやビッグデータ、AIの発展により、「第4次産業革命」と呼ばれる産業構造の大きな変化が起きている。生産性が向上したことで、どの企業でも高品質な商品が作れるようになった一方で、どの企業の商品やサービスも同程度の品質となるため、技術力だけでは差別化が難しくなった。
企業はこれまで以上に、顧客の潜在ニーズを把握し、高付加価値の商品やイノベーションを生み出さなければ競争優位性を確保できない。そして、このような創造的な取り組みには人間の力が不可欠であり、企業は人材の採用・育成・配置やパフォーマンスを発揮できる環境づくりに注力することが必要となっているのだ。
少子高齢化と人生100年時代の到来
日本国内では、少子高齢化による労働人口の減少が進んでいる。また、産業構造の変化が加速しており、それに伴って求められるスキルの変化も早く、適応人材が不足しやすい状況にある。このような外部環境の変化により、企業は変化に対応できる優秀な人材を求める場合、社内で求められる人材のスキルを定義し、採用だけではなく、育成にもより力を入れる必要性があることが指摘されている。
また、人生100年時代の到来により、社会で活躍する期間が長期化していることから、自律的なキャリア構築のサポートや、リスキリングなどの成長機会を提供することも求められている。
ESG投資への意識の高まり
近年、財務諸表だけではなく、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス(企業統治)に配慮した経営「ESG経営」を行っているかどうかによって投資先を選定する「ESG投資」への関心が高まっていることも要因の一つだ。人的資本経営はESGの「Social(社会)」に含まれるため、人的資本経営に取り組む企業が多くなったとされる。
人的資本の情報開示
ESG投資への関心が高まり、企業の「人材」という資本への意識も高まる中で、企業の人的資本についての情報を株主や投資家に公表する動きも進んでいる。
欧米では、2018年にISOが「人的資本に関する情報開示のガイドライン(ISO30414)」を策定し、2020年には米国の上場企業に対して、人的資本の情報開示が義務化された。一方日本では、2020年に「人材版伊藤レポート」が公表されて人的資本経営が注目されはじめた後、2021年にコーポレートガバナンス・コードが改訂され、2023年に金融庁が大手企業に対し人的資本の情報開示を義務化した。
マイナビの調査によると、実施している人的資本項目としてもっとも多かったのは「産休・育休の取得率に関する情報開示」となっていた。

この、「人的資本情報」については、採用の文脈で扱う際のポイントなどを下記コラムで解説しているため、こちらも併せて確認してほしい。
人的資本経営に求められる3つの視点(3P)
人材版伊藤レポート2.0は、人的資本経営を実現させていくために「経営戦略と連動した人材戦略をどのように実践するか」と、「情報をどのように投資家に伝えていくか」の両輪での取り組みの重要性を指摘し、経営戦略と連動した人材戦略を進めるために必要な枠組みとして、3つの視点と5つの共通要素によって構成される「3P・5F モデル」を提唱している。
まずは、人的資本経営を進めるにあたって求められる3つの視点(Perspectives)『3P』について解説する。
1)経営戦略に紐づいた人材戦略
人材版伊藤レポート2.0では、人的資本経営において第一歩となるのは経営戦略との連動性に取り組むことだとしている。具体的には下記のように指摘している。
最も重要な視点は、『経営戦略と人材戦略の連動』であり、まずは、『1.』に掲げる取組(経営戦略と人材戦略を連動させるための取組)に着手することが第一歩となる。
人的資本経営の実現に向けた検討会報告書 ~ 人材版伊藤レポート2.0~
取り組みの内容としては、人材戦略の責任者である「CHRO」の設置や、人材面における課題の洗い出し、経営陣とのすり合わせなどが挙げられ、KPIを設定する必要性も指摘された。また、人事部門の役割については、企業全体に関わる人事施策に携わるべきであり、事業部それぞれの採用や再配置については、事業部が責任を負うべきだと述べられている。
2)As is-To beギャップの把握
二つ目の視点は経営目標と現在の状況にどれだけの開きがあるかを確認する視点だ。人材版伊藤レポートでは、将来的な目標、言い換えれば目指すべき姿(To be)と現在の姿(As is)を照らし合わせ、どのくらいギャップがあるのか把握することが、人材戦略と経営戦略の連動性を確認する上で重要だとしている。
また、この際、CHROと経営陣が設定した「KPI(重要業績評価指標)」を用いることで、ギャップを定量的に把握できることが言及されている。
3)企業文化への定着
三つ目の視点は目指す企業文化を明らかにすることとその定着だ。人材版伊藤レポート2.0では、「持続的な企業価値の向上につながる企業文化は、所与のものではなく、人材戦略の実行を通じて醸成されるものである」と指摘されている。これは、企業文化と人材戦略が相互に影響を与えることを意味する。
また、人材戦略を策定する際には、自社が「どのような企業でありたいか」という企業理念や存在理念について見直すことや、その理念に沿った行動や姿勢が浸透するような評価制度などを検討することも効果的であるとも述べられている。
人的資本経営で重要な5つの共通要素(5F)
次に、人材戦略に取り入れるべき共通要素(Common Factors)『5F』について解説する。
1)動的な人材ポートフォリオ
一つ目の要素である人材ポートフォリオとは、どのようなスキルを持った人が、どの部署に、どれくらいいるのかを整理した人事情報のデータ基盤である。これらのデータは、経営戦略や外部環境の変化とともに、情報更新されるものであり、これを動的な人材ポートフォリオと呼ぶ
人材版伊藤レポート2.0では、「高度な専門性はもちろん、多様な視点を持ち、新たな発想を生み出せる人材がますます求められる。こうした必要性に対応し、動的な人材ポートフォリオを構築できるかが課題となる」と述べられている。
具体的な運用方法としては、まず必要な人材の質と量を整理し、動的な人材ポートフォリオを用いて現状と目標のギャップを把握する。そのギャップを踏まえた上で、中途採用や再配置、能力開発などの人事施策が行われる必要があるのだ。
2)知・経験のダイバーシティ&インクルージョン
二つ目の要素は、動的な人材ポートフォリオと同じくらい重視されている、知・経験のダイバーシティ&インクルージョンである。人材版伊藤レポートではその理由について、自足的な企業価値向上のためにはイノベーションが重要であり、それを生み出すのは多様な個人の掛け合わせであるとしている。
具体的には、女性活躍を促すことや外国人材、多様な知識や経験を持った人材を取り込むこと、それぞれの人材がより能力を発揮するような役職などへの登用の仕方を検討することなどが述べられている。
ダイバーシティに関しては下記の記事で関連コラムなどをまとめているため、参照してほしい。
3)リスキル・学び直し
三つ目はリスキル・学び直しだ。外部環境の変化に対応するためには、社員が自発的にリスキリングする必要があるとも指摘されている。企業は社員に新しいスキルのインプット(リスキル)と、自律的キャリア形成ができるように知識のアップデート(学び直し)を積極的にサポートする必要があると述べている。
そのための方法として、まずは組織として不足しているスキルを整理することや、スキル保有者の登用、社外での学習機会の提供など、スキルアップに取り組む社員をサポートする制度や風土を整えることなどが挙げられている。
リスキリングに関しては定義や関連コラムをまとめた下記の記事も参照してほしい
4)社員エンゲージメント向上のための取り組み
四つ目はエンゲージメントについての要素だ。人材版伊藤レポート2.0では「経営戦略の実現に向けて、社員が能力を十分に発揮するためには、社員がやりがいや働きがいを感じ、主体的に業務に取り組むことができる環境の整備が重要である」と指摘している。
このような、社員が感じる働きがいや会社への愛着心である「社員エンゲージメント」が高く、社員一人ひとりが自身の仕事にやりがいを感じ、高いモチベーションで働けている状態をつくることが重要とされている。
具体的には社員エンゲージメントには企業理念や存在意義、企業文化の浸透具合、ダイバーシティ&インクルージョンの達成状況など、さまざまな要因が影響すると指摘している。また、従業員エンゲージメントの高さをモニタリングし、エンゲージメントを向上させるための人事施策(社内公募や多様な働き方の推進、健康経営など)を実行し、改善を繰り返すことも重要だと述べている。
5)時間や場所にとらわれない働き方への取り組み
人材版伊藤レポート2.0では、事業継続の点においても、従業員がいつでも、どこでも、働くことができる環境を整える必要性が高まっていると指摘している。
具体的には、リモートワークが実施できるように業務のデジタル化を進めるだけではなく、オフィスに出勤して働くメリットと必要性を見直し、リモートワークとリアルワークの最適な組み合わせを見つけることも重要であると述べている。
留意すべき点
人的資本経営において重要な事柄を見てきたが、実際に取り組む際の注意点も指摘されているため、併せて確認しておきたい。
経営陣・取締役会・投資家の役割の整理
人材版伊藤レポート2.0では、人材戦略を効果的に変革させるためには、経営陣や取締役会、投資家それぞれに明確な役割があるとしている。具体的にはそれぞれ下記の役割が示されている。
人材戦略の変革に当たっては、経営陣によるイニシアティブ、取締役会によるガバナンス、企業と投資家との対話の強化が重要。
人的資本経営の実現に向けた検討会報告書 ~ 人材版伊藤レポート2.0~
まず、経営陣は自社の経営理念やパーパスに基づいて経営戦略を練り、それを実現するための人材戦略を考える必要がある。次に、取締役会はそれらの戦略を評価し、必要に応じて提言や軌道修正を行う。そして、投資家は開示された人的資本情報をもとに最適な投資先を選定することが求められる、としている。
人的資本経営についての関連記事
マイナビキャリアリサーチLabには、この他にも人的資本経営に関連する記事が掲載されている。
人生100年時代におけるキャリア施策・人的資本経営
人的資本経営の実践例については、法政大学キャリアデザイン学部教授 廣川進氏による下記の連載も参照してほしい。「人生100年時代におけるキャリア施策・人的資本経営」と題して、ミドルシニア世代を中心に、この先100年時代のキャリアと人的資源をどう活かしていくか、また未来に渡る有効な施策は何か、を各企業の生の声や取得したデータの考察を通して紐解いている。

人的資本開示のプロジェクト実践例
人的資本に関する方針を社内で検討・整理していった実践例としては、下記も参考にしてほしい。
まとめ
このコラムでは、人材を「資本」と捉えることで、人事施策に力を入れる経営手法であり、これによって、社員エンゲージメントや業務パフォーマンスが向上し、持続的な企業価値の向上を目指す「人的資本経営」について見てきた。
人的資本経営を成功させるためには、経営戦略との連動が欠かせない。人事部門だけではなく、経営陣や取締役会、そして投資家ともコミュニケーションを取りながら、人材戦略を見直し、修正していく必要がある。加えて、自社がどのような企業を目指しているのか、経営理念やビジョン、目標などを社員にしっかりと浸透させることも重要だ。
従業員一人ひとりがより良いパフォーマンスを発揮することで企業を成長させていける環境づくりにむけて、企業全体で考えていけるとよいだろう。