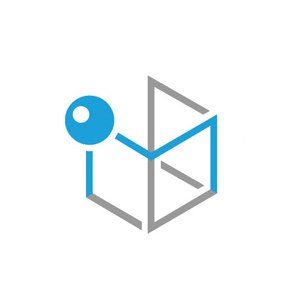視覚的要素がもたらす多様な成長~絵本の力について考える~
—駒澤大学・内藤寿子氏

現代日本における絵本の位置
大学などの高等教育機関で、「絵本の授業」を担当しはじめて20年以上の時が過ぎた。「大学で絵本について教えています」といった自己紹介も繰り返してきたのだが、わたくしの言葉に対して、相手からなされる定番の質問がある。「司書を養成するための講義ですか?」、あるいは「保育を学ぶ学生さんですか?」といったものだ。この種の質問には、「すべての学生向けの一般教養科目です」とまず答える。すると、「絵本は子供のためのものなのに、そんな単純な題材で大学の授業が成り立つのか?」といった主旨の質問が続いていく。しばしば経験してきたやりとりである。
しかし、絵本を軽んじる響きを持つこうした認識は、ただの偏見にすぎない。それは、たとえば2022年夏の日本の状況からも明らかだ。近年、美術館や文学館で、絵本に関わる展覧会が開催される機会が増えているが、特に、2022年夏は充実した企画が続いた。
わたくしが実際に足を運んだものについて述べれば、世田谷美術館で開催された「こぐまちゃんとしろくまちゃん 絵本作家・わかやまけんの世界」(7月2日~9月4日)では、ひとつひとつの線から原画の繊細さを知ることができた。屋外展示も工夫されており、世田谷美術館と広々とした砧公園が1つの作品を構成しているかのような企画展だった。
また、渋谷のBunkamuraザ・ミュージアムで行われた「かこさとし展 子供たちに伝えたかったこと」(7月16日~9月4日)では、資料を見入っている人びとの多彩さが印象的だった。幼児と保護者だけでなく、大学生のグループも目にした。『からすのパンやさん』(1973年 偕成社) の原画を指さすお年寄りの隣には、明らかに成人に達している孫と思しき同伴者が寄り添っていた。

『anan』をはじめとする雑誌でアートデザインを担った堀内誠一は、絵本作家としてもよく知られている。神奈川近代文学館の「堀内誠一 絵の世界」(7月30日~9月25日)では、長くフランスに住んでいた堀内が記したエアメールが展示されており、そこには、絵本の可能性を終生追求しつづけたひとりの総合芸術家の軌跡が刻まれていた。

絵本は、子供を第一の読者として考え、生み出されたものである。さまざまな物語は日々の生活を彩り、子供にとっての初めての文化体験になっている。さらに、ここに述べた2022年夏の活況からも分かるように、現在、あらゆる世代の人びとを魅了する芸術の1つとしての地位も獲得している。
1960年代、アンディ・ウォーホルは「キャンベルスープの缶」など日常的な存在をシルクスクリーンで表現し、「引用と複製」という思想―便器を美術館に展示し、作品にしてしまったマルセル・デュシャンの流れをくむ―を世に問うた。世界にただ1つの芸術作品だけではなく、ファッションや家具、スマートフォンなど生活に結びついたデザインも大きな文化的価値を有している。このような現代の芸術観に立てば、版画の技法を駆使した絵本の原画が、ウォーホルの作品と同じく美術館に展示され、観覧者を引き付けるのは極めて当然なのである。
絵本にとって子どもは重要な読者だが、このメディアは決して単純なものではない。実際は複雑な構成体であり、作品のあらゆる要素には深い意味がある。子どもにとってはもちろん、かつて子どもであったすべての大人にとって、「絵本を読む」という経験は大きな価値を持つ。本コラムでは、ロングセラーやベストセラ―などをもとに、それぞれの作品の特徴や意義を紹介すると共に、絵本が大人にとっても社会性を磨くためのツールになりうるということ、「学びの場」になりうるということを明らかにしていく。まず今回は、『しろくまちゃんのほっとけーき』(こぐま社 1972年)を題材に、日本の絵本文化の豊かさを照らし出したい。
「絵本を読む」とは?
絵本は現代芸術として独自の位置を占めはじめているが、やはり何よりも子供が生活する場において不可欠な存在である。なぜなら、「絵本を読む」という経験は、子供の発達や成長を多方面から支えてくれるからだ。
たとえば、〈絵本を読む=物語の体験〉は、第一言語(母語)や知識の習得を促すだけでなく、想像力や探求心を育んでくれる。特に、喜怒哀楽や善悪のあり方、他者の感情や認識を、絵本を通して追体験することは生きていく上での礎となる。
また、〈絵本を読む=コミュニケーション〉という側面も忘れてはならない。読み聞かせ(音読)を例にあげれば、1冊の絵本を中心に、ともに考える場を日常生活の中に築き上げることが可能だ。時間と空間を共有しながら、読み手と聞き手が自らの読解を語り合う行為は、自身の価値観に気づくための第一歩であり、他者を受け入れるための準備になる。
あらためていうまでもなく、社会生活とは他者と一緒に完成させていく織物だ。けれども時には、関係の糸が上手く結べない相手に出会うこともある。わたくしたちがこのような困難さを乗り越えられるのは、自分の視点と他者の視点を柔軟に切り替えることができるからであろう。そして、人間関係を構築するために必要なこの力を培ってくれたものの1つは、成長の過程で積み重ねた〈絵本を読む=他者の眼になって考える経験〉なのだといえる。
『しろくまちゃんのほっとけーき』に描かれた〈失敗〉
では、〈他者の眼になって考える経験〉へと読者を導く作品とは、どのようなものなのか。まず思いつくのは、〈失敗〉をテーマとする物語だ。何かを成し遂げるためには、試行錯誤を重ねなくてはならず、つまずきは「学びの場」となる。それゆえ、主人公がおかした〈失敗〉の追体験は大きな意味を持つ。だが一方で、挫折や過ちばかりの物語を読むことには苦痛が伴う。〈失敗〉の描かれ方によっては、作品そのものが拒絶されてしまう場合もあるのだ。実は、絵本において〈失敗〉を表現することは、思いのほか難しい。
しかし、ロングセラーやベストセラーの中には、〈失敗〉を巧みに描いた作品がある。『しろくまちゃんのほっとけーき』は、その代表ともいえる1冊だ。この絵本は、つまずきながらも、ホットケーキを作り上げる主人公の姿を通して、「失敗から成功へ」という喜びに満ちた追体験を読者にさせてくれる。さらに、「絵=視覚的要素」が伝える〈失敗〉は、〈他者の眼になって考える経験〉をもたらすものともなる。

「最初の失敗」を例に述べれば、「しろくまちゃん」は冷蔵庫から卵を取るにあたり、落として1つ割ってしまう。右ページに付されている文章は、「ひとつ ふたつ みっつ たまご ぽとん あっ われちゃった」という短いものだ。けれども、左ページ全面を使って表現された「絵=視覚的要素」は多義的な読解が可能であり、読者に対して、自分自身で主人公の〈失敗〉を考えてみるよう促す。

「絵=視覚的要素」に注目して、「最初の失敗」を少し読み解いていこう。場面の背景は、青一色である。これはキッチンの壁紙の色かもしれないが、冷蔵庫の冷気だともみなしうる。もちろん、卵を落としてしまった「しろくまちゃん」の落胆を象徴していると捉えることも可能だ。また、冷蔵庫の前に1人でいる「しろくまちゃん」の手はとても小さい。この形象は、主人公の未熟さや幼さを表す一方で、子供が自分の手で挑戦することの大切さを伝えるメッセージだと読解できる。「しろくまちゃん」の体は、前方に傾いている。その姿は、〈失敗〉を受け止めきれずに驚いているようでもあり、〈失敗〉の後に何をすべきなのか思案している姿にも感じられる。それとも、割れた卵を片付けるための行動を始めたのか…。
「絵=視覚的要素」を見つめれば見つめるほど、「最初の失敗」が持つ意味は広がっていく。つまり、『しろくまちゃんのほっとけーき』は、読者それぞれが「しろくまちゃん」の眼になって、〈失敗〉の理由やそれを乗り越える方法などに思いをめぐらせるための場を生み出す絵本なのである。そして、このような〈考える〉という主体的な営みへと読者を導く鍵は、何よりも『しろくまちゃんのほっとけーき』における「絵=視覚的要素」だといえる。
『しろくまちゃんのほっとけーき』の歩み
以上、『しろくまちゃんのほっとけーき』の「絵=視覚的要素」に注目してきたが、絵本を実際に手に取ると、さまざまな要素―視覚的要素、触覚的要素、聴覚的要素、嗅覚的要素、味覚的要素など―にあふれている点にも気がつく。『しろくまちゃんのほっとけーき』は、小さな手でも、無理なく自分でページをめくることができる大きさだ。この触感からは、子供の主体性を尊重するというメッセージが感じ取れるだろう。表紙のオレンジ色は視覚的要素であると同時に、ホットケーキの温かさや芳しさを伝える役割を果たしている。ホットケーキを焼く場面の「ぴちぴちぴち」「ふくふく」「くんくん」といった擬音は、甘い香りと味の記憶を喚起する…。『しろくまちゃんのほっとけーき』においては、これら複数の要素が「失敗から成功へ」という物語と有機的に結びついている。だからこそ、読者は心をつかまれてしまうのである。
最後に、この絵本の魅力と出版背景との結びつきについて述べておこう。『しろくまちゃんのほっとけーき』を含む「こぐまちゃんシリーズ」は、3人の作家(森比左志、わだよしおみ、若山憲)と1人の編集者(佐藤英和)の共同作業により、1970年に誕生した。50年を超えて版を重ねる「こぐまちゃんとしろくまちゃんの物語」は、「子供たちの豊かな情感を育て、あたたかな心を育む」(こぐま社HP「会社案内」より)ためのものであり、現在では、3世代に共有される文化体験の源となっている。
そのことをわたくし自身は、先に紹介した展覧会においてだけでなく、大学の教室でも実感している。のべ数百人に及ぶ授業の履修者に、毎年、「忘れられない絵本」について尋ねているのだが、もっとも多くの大学生が名前をあげる作品は20年以上変わらない。それは、『しろくまちゃんのほっとけーき』である。コロナ禍の厳しいおりには、ある履修者から「こぐまちゃんシリーズ」を扱ったオンライン授業用教材を、「祖母や母と一緒に閲覧したい」との相談が寄せられたこともあった。閲覧後の話によれば、教材をもとに絵本の思い出を3世代で語り合ったひとときは、不安に苛まれる日々において、稀有で「あたたかな」時間だったという。
現在、『しろくまちゃんのほっとけーき』はロングセラーの代表となっているが、その誕生は出版状況への問題提起でもあった。日本の絵本は、翻訳文化として発展してきた歴史がある。「岩波の子供の本シリーズ」(1953年創刊)などを通して紹介された主に欧米の作品は、子供たちの読書環境を育んできた。しかし、絵本を通して伝えられた海外の姿は、異なる世界への好奇心を養ったといえる一方で、文化的な相違が足かせとなり、翻訳絵本に対して難しさや退屈さを感じる読者も少なからずいたのである。このような状況下に誕生した「こぐまちゃんシリーズ」は、絵本の新たな表現を追求する取り組み―日本で生きる子供たちが主体的に読みたくなる絵本―であった。作品を担う「こぐまちゃん」と「しろくまちゃん」は、日本語を母語とし、日本に生活基盤を持つ子供の分身として描かれている。自己投影できる主人公の物語は、翻訳絵本にはない親近感や面白さを読者に抱かせ、心の発達や成長を支えてきたのだった。
大学の授業で『しろくまちゃんのほっとけーき』を取り上げるたびに、「しろくまちゃんの真似をしてホットケーキを作った」との思い出が、必ず履修者から寄せられる。けれども不思議なことに、「しろくまちゃんと同じように失敗をした」との声に出会った記憶はない。これも、日本の子供たちが、「しろくまちゃん」の眼になって考える経験を通して、〈失敗〉を克服してきた歴史の証拠なのかもしれない。
今回のコラムでは、絵本の視覚的要素に焦点を当て、多様な解釈を可能にする「学びの場」としての絵本の姿を明らかにした。次回は、言語表現などに注目し、絵本というメディアの意義についてさらに考察を深めていく。
著者紹介
内藤寿子(ないとう・ひさこ)
早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。2010年より駒澤大学に着任。現在、総合教育研究部日本文化部門教授。専門は日本文化。映画や雑誌、絵本など、いわゆる大衆メディアと呼ばれるものを題材に、近現代日本文化および日本社会について考察を行っている。