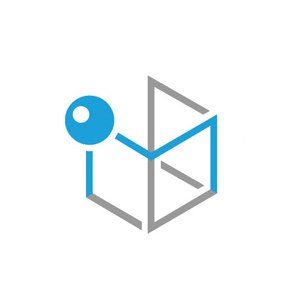脳神経科学における創造性やクリエイティビティとは何か──『つむぐ、キャリア』で必要となるキャリア開発の視点から創造性の重要性を考える(対談:東京大学大学院情報理工学系研究科 大黒達也氏)
シリーズ第3弾となる今回は、脳神経科学者で東京大学大学院情報理工学系研究科 大黒達也特任講師をお迎えし、『つむぐ、キャリア』監修者の法政大学 梅崎教授と、キャリア開発で必要とされる創造性やクリエイティビティについて議論していただいた。
脳の統計学習とは何か、個性や創造性を生み出す“不確実性のゆらぎ”とは何か、最新の研究成果をもとに創造性の本質を解き明かしていく。

(写真左)東京大学大学院情報理工学系研究科 大黒達也特任講師
(写真右)法政大学 キャリアデザイン学部 梅崎修教授
目次
「収束的思考」と「拡散的思考」が創造性に不可欠

梅崎:創造性やクリエイティビティは、キャリア開発に取り組む人にとってはたいへん重要なキーワードでありながら、その本質があまり理解されていないと感じます。そこで今回は、脳神経科学の専門家である大黒先生に、脳のことについて教えを乞うスタイルで進めさせていただきたいと思います。
まず最初に、「あの人は頭がいいよね」というような言い方をよくしますが、頭の良さと創造性、クリエイティビティはどのような関係にあるのか、そのあたりからご説明いただけますでしょうか。
大黒:創造性は、ポップサイエンス(※)といわれていた時期もあって、1960年以前は研究対象にならないとされていましたが、最近になって研究が進められるようになった若い研究分野です。
※ポップサイエンス:通俗科学(popular science)。難解な専門用語を用いず、一般大衆にもわかりやすく説明したもの
一般的に「頭がいい」というのは、学歴や経歴を見て判断する人が多いと思いますが、創造性については、自分が何を知っているか、あるいは知らないかを認識していることが重要であると思います。自分の知識の枠にはまらず、新しいものに対して順応できることが、創造性の起源、オリジンだと考えます。
この創造性には2種類のタイプがあると考えられています。数学的な課題のように、自分のアイデアで1つの解に導くような創造性。これを「収束的思考」といいます。もう1つが「拡散的思考」で、答えがないものに対して自分なりのアイデアを1つの解に限らずたくさん考えること、それも創造性には不可欠な思考方法です。
| 収束的思考 | 数学的な課題のように、自分のアイデアで1つの解に導くこと |
| 拡散的思考 | 答えがないものに対して自分なりのアイデアを1つの解に限らずたくさん考えること |
梅崎:創造性という言葉の意味はとても幅広く、「考えを収束させて論理的に説明できる枠組みを見つけられる人」と「何にもないところからアイデアを探してくる人」は、全然タイプが違うということですね。
大黒:人によって個性はあるものの、基本的には個人の脳の中で、収束的思考と拡散的思考は時間的な“ゆらぎ”を持って生じています。数学的な解答を導き出すのも、まだ世の中にないものの答えを見つけるのも段階が違うだけです。
梅崎:ゆらぎというキーワードを理解するために、先生ご自身の著書でご説明されている「統計学習」「不確実性」「チャンク」「記憶の種類」という4つのワードについてもご講義いただけますでしょうか。
大黒:統計学習は、人間が生まれつき持っている脳の学習システムで、私たちの身のまわりで起こるさまざまな現象・事柄の「確率」を自動的に計算し、整理する脳の働き・システムのことです。
脳の統計学習では、「次に何がくるか(遷移確率)」と「情報エントロピー(不確実性)」を計算します。遷移確率とは、移り変わる確率のことで、たとえば交差点で信号が変わるのを待っていて、青信号になったので横断歩道を渡ろうとしたとき、車が突っ込んでくる確率はほぼ0%で、赤信号になったら車が突っ込んでくる確率はほぼ100%と脳は情報の移り変わりを計算します。
また、情報エントロピー(不確実性)とは、情報の複雑性のことで、情報が複雑で予測がしづらい状態を「情報エントロピーが高い=不確実性が高い」と表現し、情報が複雑ではなく予測がしやすい状態を「情報エントロピーが低い=不確実性が低い」と表現します。
たとえば、「わたしは大黒達也」といったら、次に続くのは基本的に「です」と予測しますよね。「ではありません」とはいうはずがないと。だから「わたしは大黒達也」といったときに、高確率で「です」を予測して、それ以外のパターンはほとんどありえない状態。それが不確実性が低い状態です。ある情報の次に来るパターンの数やばらつき度合いを不確実性というわけです。
次にチャンクですが、脳の統計学習では特に言語において一番大きな役割を担っています。たとえば、「わたしは大黒達也です」という言葉は、どこまでが単語で、どこが単語と単語のつながりか、赤ちゃんにはわからないでしょう。しかし、先ほどの「わたしは大黒達也/です」のように、「わたし」という単語の後に「わたし/は」「わたし/に」などの接続詞が続く可能性があると予測できます。さらに言えば、「わたし」という単語は「わた」の後に「し」が続く確率が高いことから、「わたし」とひとまとまりで認識するわけです。
この高い確率の塊を人間は統計学習によって認識できるようになるんです。これをチャンクといいます。チャンクとは複数の情報を1つに圧縮することで、脳内に空きを作ることです。それによって脳は情報処理の効率を上げることができるわけです。
| 統計学習 | さまざまな現象・事柄の「確率」を自動的に計算し、整理する脳の働きのこと |
| 不確実性 | 情報の複雑性のこと |
| チャンク | 統計学習によって高い確率の塊を認識できるようになること |
意味記憶とエピソード記憶の共創によって個性や創造性が生まれる

梅崎:記憶の種類ついても教えてください。脳の記憶には、「短期記憶」と「長期記憶」、そして「潜在記憶」と「顕在記憶」などがあるということですが。
大黒:記憶を時間の観点で分類したのが短期記憶と長期記憶です。数十秒から数分の間だけ保持されるのを短期記憶、数時間から生涯保持されるのを長期記憶といいます。短期記憶の情報は時間の経過とともに忘れ去られますが、反復することによって長期記憶に転送されるといわれています。
また、潜在記憶と顕在記憶は、記憶を意識の観点から分類したもので、潜在記憶とは、記憶していることを本人も気づいていないような記憶を指します。この潜在記憶も記憶のタイプによって「手続き記憶」と「プライミング記憶」に分けられています。
手続き記憶というのは、自転車の乗り方のように、身体で覚えて言葉では明確に説明しづらい記憶のことです。そして、プライミング記憶は、事前の事柄が後の事柄に影響を与えるような記憶のことで、「ピザ」と10回いって、「これは何?」とヒジを指すと、「ヒザ」と答えてしまうような状態を生み出す記憶です。
一方、顕在記憶は、言葉によって説明できる記憶、記憶していることを本人が気づいている記憶のことで、「意味記憶」と「エピソード記憶」に分けられます。意味記憶とは、物の名前や単語など皆で共有できる記憶のことで、エピソード記憶は、個々の実体験の記憶を指し、自分自身の身に起きた体験(エピソード)に基づいて形成されます。
| 短期記憶 | 数十秒から数分の間だけ保持される記憶のこと |
| 長期記憶 | 数時間から生涯保持される記憶のこと |
| 潜在記憶 | 記憶していることを本人も気づいていないような記憶のこと |
| 顕在記憶 | 言葉によって説明できる記憶のこと |
| 手続き記憶 | 身体で覚えて言葉では明確に説明しづらい記憶のこと |
| プライミング記憶 | 事前の事柄が後の事柄に影響を与えるような記憶のこと |
| 意味記憶 | 物の名前や単語など皆で共有できる記憶のこと |
| エピソード記憶 | 個々の実体験の記憶のこと |
梅崎:意味記憶は人と共有できるというものの単位や概念で、エピソード記憶は自分というものを説明したり、もしくは「あのとき自分はこうだったな」と自分の頭で固有の体験をイメージするような記憶ですね。
大黒:他人と共有するのが意味記憶で、それによってコミュニケーションが効率化して、人間の進化にとって重要な役割を果たしてきました。エピソード記憶はこの意味記憶が組み合わさってできるもので、意味記憶とエピソード記憶の共創によって人の個性や創造性が生まれると考えています。
「一般化・抽象化」と「特殊化・具体化」がサイクルすることで不確実性にゆらぎ
梅崎:ご著書『AI時代に自分の才能を伸ばすということ』では、「意味記憶的情報を生成する統計学習(一般化・抽象化)」と「エピソード記憶的情報を生成する統計学習(特殊化・具体化)」がサイクルを繰り返し、共創することで徐々に表現に自分らしさや個性が見えてくると解説されています。創造性を統計学習のサイクルや意味記憶とエピソード記憶の連鎖で説明されているのが非常に新鮮です。
大黒:不確実性の観点からいえば、「一般化・抽象化」は高確率の情報の塊をチャンクして1つの情報としてまとめて情報量を減らすので不確実性が下がります。しかし、「特殊化・具体化」ではチャンク情報を組み合わせて新しい情報を作成するので不確実性が上がる傾向にあります。
不確実性に対して逆方向に動く「一般化・抽象化」と「特殊化・具体化」の2種類の統計学習がサイクルし、共創し合うことによって、不確実性にゆらぎが生じます。私は、このゆらぎそのものが個性や創造性の種となると考えています。
梅崎:絵画とか音楽でも模倣や反復が非常に大切です。このことによってチャンクされ、そしてクリエイティビティにつながっていく。茶道や武道の修行のプロセスで「守・破・離」というのがありますが、「守」で基本や型を身につけて、「破」で既存の型を破り、「離」で独創的かつ個性を発揮する…自由に絵を描いたり、自由に演奏することが創造性につながるわけではないということですね。
大黒:情報的な新しさと創造性は全く違うものだと思います。新しいことをやることが創造的であるわけではないということです。私は、創造性は感性の1つだと思っていて、情報そのものの新しさではなくて本人のモチベーションが重要だと考えています。
もっといえば、本人が創造的な体験をするというのが大事で、それを創造的に作れたと自分で認める。何回も反復してみると、自然に何か違うことをし始めます。そのときに初めて創造性が生まれるわけです。とにかく同じことを繰り返して、反復し続けると自然にゆらぎが生まれるわけです。
梅崎:絵画でも何度も反復して鑑賞することが重要で、繰り返して鑑賞することで本当のすごさ、魅力がわかってきます。創作することも体験ですが、鑑賞することも体験です。鑑賞するという経験が蓄積される。いろいろな角度、視点で何度も見るうちに新しい見方が創造できるわけですね。
創造性を高めるために仕事ができる人を徹底的に真似てみる

大黒:ブレーンストーミングをする際などは、「新しいアイデアを思いつくぞ!」と意図を持って実行することが多いと思いますが、それではなかなか答えは出ないのではないかと思います。何か意図を持っている時点でまだ収束する余地があるのではないでしょうか。
梅崎:最近は、イノベーションにつながるオフィス環境作りが流行りですが、そこで働く人は楽しい会話はできても、みんながチャンクされていない状態では、創造性が生まれることを期待するのは難しいですね。
仕事のなかで創造性を発揮するにはいったいどうすればいいでしょうか。仮に商品開発を担当している人がいて、何を反復すればいいのか、どうチャンクして、どう意味記憶を増やしていけばいいのか、仕事では個人に任されている範囲が広くて、創造性を発揮するのは簡単ではなさそうです。
大黒:個性を重視することが大切だと思います。収束が得意な人と拡散が得意な人が組めば、ゆらぎが生まれる可能性が大きくなり、それをしっかりとまとめる人がいると、それぞれの個性が生かされて圧倒的なパフォーマンスを発揮することが期待できます。それがある種ブレーンストーミングとかチームクリエイティビティの面白いところかなと思います。
梅崎:チームクリエイティビティでは、対話によって集合的な創造性が高まりますが、もちろん個人の中にも2つのモードがあり、ゆらぎもある。ゆらぎを持つ他者との対話で協奏的な関係が生まれますね。仕事のなかで反復するものを作るのはどうでしょう。仕事ができる人を徹底的に真似てみるというのも1つの手法ではないでしょうか。
大黒:私も模倣が非常に大事だと思います。音楽でもスポーツでもまずは真似る。それが正解だと思います。ベイズ統計(※)の観点から考えると、同じ90%の確率でも、信頼できる90%と信頼できない90%があると考えることができます。
※ベイズ統計:トーマス・ベイズが提唱した「ベイズの定理」を基本的な考え方とする統計学。新しいデータを取り込みながら推定や予測の精度を高めていく特徴がある。
脳は、ベイズ的な推論をしていると言われていますが、例えば10回中9回の確率でAを経験するよりも、100回中90回の確率でAを経験した方が、Aを90%で予測する信頼性は向上するのが、直感的にわかると思います。そして確率の信頼性が上がると、ちょっとしたズレがあった場合に、新しさを認識できるようになります。
創造的な人と模倣が得意な人、お互いの役割を認め合う社会を
梅崎:反復することで潜在学習が機能して、余計なことに脳を使う必要がなくなって、クリエイティビティのほうに使えるというわけですね。しかし、世の中には他人の真似はうまくても、創造においてブレークスルーできない人がいます。これはどう説明すればいいでしょうか?
大黒:創造性を語るうえで気をつけなくてはいけないところですが、創造的な人が一番偉いというわけではないんです。全員が創造的になってしまったらそれはそれで問題です。それぞれがお互いの役割を認めたうえでチームを組むのが大事だと思います。
模倣が得意な人が無理やり創造的になる必要はありません。ある種のダイバーシティ的な発想でお互いがお互いの役割を全うできるような社会的慣習というか、認め合う社会であることが大事ではないでしょうか。
梅崎:世の中には「不確実性を圧縮するのが得意な人」と「ふわふわした不安な状態を楽しめる人」がいるように思います。このコンビをどう作るかというのも重要ではないでしょうか。収束が強い人と拡散が強い人のコンビが効果的なように。
大黒:脳の報酬として、快感や多幸感をもたらすドーパミンという物質がありますが、脳の報酬は、ふわふわして不確実性が高いものを圧縮したときに生じるものだといわれます。ふわふわした情報を努力次第で圧縮できるかもしれないと思った瞬間に興味を持つ。これが知的好奇心ですね。
人間はふわふわしすぎているものを嫌うのは普通のことなんですが、ふわふわしすぎたまま情報を許容できる人、別の言い方をすればネガティブ・ケイパビリティ(※)が高い人というのがいて、なぜそれが可能なのか、またそういう人をどう捉えていくかも重要になりつつあります。
※ネガティブ・ケイパビリティ:事実や理由を性急に求めず、不確実さや不思議さ、懐疑の中にいられる能力
梅崎:会社では業務の効率性が重要視されるので、そういうタイプの人は疎まれる可能性が大きいですね。しかし、長期的な視点に立てばイノベーションは不可欠なので、企業経営の視点で考えれば、そういった人たちをどう扱うのかが重要になってきます。ただ、前衛芸術家がなかなか理解されないように、不確実性を嗜好するする人とまわりの人とのズレが出てきます。
大黒:現代音楽を例にとると、どんどん暴走してしまって一般的な音楽モデルを超えてしまうような状態ですね。本当は一般モデルよりちょっとずれたものを作るのが一番知的好奇心を高め、学習効率も上がるはずなんですが。
梅崎:松任谷由実さんの作品で『悲しいほどお天気』というタイトルの曲があります。われわれは、「恋人や友達と別れて悲しい⋯」という感情に共感はできてもエピソード記憶としては弱い。でも、「悲しいほどお天気」というちょっと不思議なタイトルだと、気になって何度も聞いてしまいます。
大黒:想像の範囲を少し超えるくらいがちょうどいいのかもしれません。不確実すぎず、確実すぎないレベルで。
梅崎:ビジネスパーソンも、ちょっとしたクリエイティビティを発揮する仕事があります。プレゼン資料の最後の言葉を考えたり、グラフをどう見せるか工夫したり。企業は社員のクリエイティビティをうまく引き出すために、オフィスを設置したりワーケーションを導入したりしていますが、なかなかクリエイティビティと直結していない状態だと思います。
ワーケーションなどは、あまりに非日常的な場所だと情報量が多すぎて、全然仕事に集中できない状態になるかもしれません。
大黒:新しい場所に行くと、身体は自然とわくわくします。そういう、ある種のガットフィーリング(直感)は感性を高めるために大事だと思います。わくわくしない人というのは、自分の身体の反応を認識できず、常識ばっかり考えてしまってわくわくする感情を抑えてしまったりしますから、そういう意味では新しい場所に行くというのも1つの手段だと思います。
強制的“接続”と強制的“切断”を意識的に実行し、不確実性の領域を拡大

梅崎:強制的接続と強制的切断を意識的にゆらぎの中でやるといいと思っています。接続は、新しい何かに出会ってわくわくすること。一方、カントや西田幾多郎のような哲学者は、毎日同じルートを散歩しています。こういう「習慣化された散歩」は、歩行から受ける情報エントロピーの最小化しているのかもしれません。座禅のようなものも、切断モードです。接続と切断を繰り返すこと、つまり、不確実性の領域を大きくしたり小さくしたりして、クリエイティビティ維持する努力をしているのではないでしょうか。
昔は日常生活にハレとケ(※)があって、農村には1年のサイクルがありました。働くときと休むときの切り替えが明確だったわけです。しかし近代社会は「とにかく働け、疲れたら休め」という単純な肉体疲労モデルをベースにした労働時間管理でした。それが最近では、副業が解禁され、在宅ワークなども導入されて、休暇についても自律的に選択することが求められています。休暇を研究対象にする休暇学が必要な時代になっているかもしれません。
※ハレ=晴れは、冠婚葬祭や行事などの特別な日をこと。ケ=褻は、ハレ以外の日常的な生活のこと。
大黒:興味深いですね。現代では休暇も大事な仕事ですから。
梅崎:80年代は余暇がテーマでした。ただ、この言葉からわかるように「余った時間」という意味でしかなかった。キリスト教圏では日曜日に教会に行くことで「内省する時間」を大切にしているのですが…。ところで、何も考えずに「ぽかーん」としているのは実は訓練が必要でよね。何もしないよりも単純な反復のほうがよほど無になれます。ランニングをする人が増えているのは、頭を空っぽにできるからですよね。
ご著書では、新しい発想や発見が生まれる仕組みとして、グラハム・ワラスの4段階(※)について解説されています。(1)準備期→(2)あたため期→(3)ひらめき期→(4)検証期の4段階で、このうちあたため期の重要性を指摘されておられます。頭を一度リフレッシュして、あえてボーッとする時間を作り出すことによって、次のひらめき期で創造的なアイデアが生まれるわけですね。しかし、人間にとってボーッとするのは意外に難しいですよね。
※ワラスの4段階:イギリスの社会科学心理学者グラハム・ワラスが創造的なアイデアが生まれるプロセスを4段階に分けて解説した理論のこと
大黒:スマートフォンから距離をおいて、散歩程度の軽い運動をするのがいいかもしれませんね。
梅崎:私は今、埼玉県の秩父に足繁く通っていて、ワーケーションしながら地元の人と交流しています。初めて行ったときは目新しい情報ばかりでわくわくしてボーッとはできなかったのですが、訪問回数が増えてくるとだんだん慣れてきて、仕事に集中できるようにもなりました。
ただ、訪問回数が増えすぎると今度は不確実性が減ってしまう。隣町に行ってみたりしはじめます。ちょうどいいバランスを維持するのが難しいです。ワーケーションの場所として3つくらい確保できるといいのかもしれません。
大黒:私の場合は、仕事のなかで自然にバランスをとっている気がします。クリエイティビティが求められる実験をやりつつ、疲れてくると執筆作業をします。収束的な仕事や不確実性の高い作業をうまく取り入れて、意図的に仕事にゆらぎを持たせているイメージです。
梅崎:先生のご著書を読んで、ボーッとすることやあたため期の重要性はよくわかったのですが、何も頭を使っていなくてただボーッとしているのではなくて、あたため期のボーッという状態を維持するのは難しい。ついついキーボードでデータの打ち込み作業を始めたりしてしまいます。
大黒:何か作業をしたほうが安心するという発想になってしまうのかもしれませんね。
梅崎:会社で、仮に上司から仕事をさぼっているんじゃないかと疑われたときに、「今、アイデアを探しているんです」と理解してもらうのは難しいような気がします。イノベーションを起こすためにクリエイティブな人を増やすという意味では、ボーッとしている人が増えたほうがいいのですが、自分が管理者だとしたら、この目の前の“ボーッと”はクリエイティビティにつながる“ボーッ”なのか、単なる“ボーッ”なのか(笑)、判断がつかないです。
また、“ボーッ”の識別の問題とは別に、「新しいアイデアを出すために頑張れ!」という上司の言葉には、そもそも“ボーッとする”という概念が入っていません。先生のご著書にはマインドワンダリング(※)というキーワードが紹介されていますが、アイデアを出すためには、積極的にぼんやりするあたため期を持つことが重要だと思います。
※マインドワンダリング:いわゆる「心ここにあらず」といわれる現象のこと。心がボーッとしている状態
しかし現代では、「心ここにあらず」というような状態が許されない状況になっています。個人レベルではクリエイティビティの重要性は理解できたとしても、経営側の価値観では、ボーッとしている人は、怠けているとみなされてしまうし、天才的なクリエイティビティを発揮する社員でさえ、チームワークを乱す人という烙印を押される危険性があります。
大黒:確かにそういった側面があるのは否定できません。やはり、管理するほうも休暇というものに対する認識を変えないといけない世の中になってきているのかもしれません。休暇している人が今、アイデアを創出する前の重要な状態にあることを客観的にわかるような指標があると、お互いがハッピーなんですが。
ゆらぎが生まれる時間軸が人によって違うことを許容する
梅崎:1990年代以降、日本企業は成果主義を導入しました。短期の成果を重視して人事評価を行うようになったと思います。その結果、長期的には成果を生むとわかっていても、ボーッとしていることが許されなくなりました。
不確実性の割合が大きいほうが画期的なアイデアを生み出せる可能性が高いのだと思うのですが、それは比較的高いという可能性なので、アイデアが生まれないことの方が多い。だから、個人はリスク回避的な行動をとることになります。つまり、確実だけど小さな成果を目指してしまいます。
また、仕事を進める際に、1つのチームにあたため期でボーッとしている人と検証期にいる人が混在すると、意識の差異がが生じて、よいグループダイナミクスが生まれない。ブレーンストーミングも「今はあたため期」という合意はできていても、なかなかいいアイデアが出てきません。結局は、個人個人でやったほうがいいような気がします。
大黒:実は、私もクリエイティビティは個人主義のほうがいいと考えています。対談の冒頭でお話したように本当のクリエイティビティというのは、モチベーションが重要で、その意欲はどんどん収束していった先にしか生まれないから、やっぱり個の中で解決するものなんじゃないのかなと思います。ただ、ゆらぎが生まれる時間軸は人によって違うので、それを許容できる世の中であるべきだと思います。
梅崎:チームで仕事をする際にメンバーが今、どんなモードにいるのかがわかるといいですね。「今、あたため期です」とか「ボーッとモードに入っています」とか、何かサインのようなもので判別できないものでしょうか。
大黒:ゆらぎを判断することは脳波上で不可能とは言い切れませんが、何か体を動かしているときの脳波はそもそも体の動きのノイズがかなり含まれていて信頼性が低くなりますし、実用化はまだまだ難しいのではないかと私は感じています。
ただし、そういうモードに強制的にスキップさせることはできるかもしれません。散歩することである種の準備モードに入ることができるし、色とか音、温度とか気温をコントロールすると、モードを強制的に切り替えることが可能だと思います。まだ信頼できるデータはありませんが、オフィス環境を考えるときに参考になるかもしれないですね。
もしかしたら、これから生まれてくる子供たちはそういう社会に順応して、必然的にクリエイティブの能力が勝手に高まる可能性があります。ルーチンワークをする必要がなくなって、アイデアを考えることに集中できる環境になっていくと思いますので。
AI時代に人間が残すべき能力とは何か?

梅崎:先生のご研究では、AIにもどんどんクリエイティビティを実装させる段階に進んでいる状況になっているようですね。でも、クリエイティビティは人間に残された大切な能力だったはずなのに、それさえ不要となってくると、将来的に人間にとって残すべき能力は何でしょうか?
大黒:そうですね、世の中の動きがすごい早いので難しい回答ですが、私個人的には、人間には「身体」があるということが重要と考えています。身体は人間にはありますが、少なくともロボットではない、アルゴリズムやモデルとしてのAIにありません。
わくわく感とか内受容的な身体性は人間にしかないことから、そういった身体的な感情、例えば「感動」するとかいうのは人間の仕事だと僕は思っています。わくわくから始まる感動、身体的な感動とその感動の共有、たとえば1人で音楽を聞くよりもコンサートホールでみんなで聴いたほうが一体感を生じるような。そういう体験は多分、今のところ人間にしかできないんだと思っています。感動しないと生まれない創造性というのは絶対あると思うんです。
私が作っているAIやモデルも、創造性を生み出す可能性もありますが、最終的に解決するための過程としての創造性でしかなくて、創造性は創造性のままでいいんだというふうには判断できません。でも、人間はぼやっとしたままでいいんだという判断ができる。わくわくして、それだけでいいんだと思える。
梅崎:テレビ番組などで「神回来た!」みたいな表現をすることがありますが、人間にとって制作することは体験であり、それを見ることも体験だから、創造性が生まれた瞬間を追体験すること自体が楽しいわけです。体験は基本的に身体がからんでくるので、それ自体はなくならないわけですね。
おそらく人間自体がシステム全体にとってバグみたいなものだと思いますが、バグみたいなものが神回を作ったり、同時に失敗を生み出したり。それ自体が楽しいと思ってしまうから。
「いいバグを起こしてるね」とか、「いい混乱してるよね」というワーディングを作ることで、人間の意識を変える必要があるかもしれません。効率性を求めるばかりでなく、不安であるとか、不完全性が高い状態を楽しめるという状態が求められている気がします。ジェットコースターに乗ると不安だけど楽しいと感じますが、それを安直に「不安」と言わないようにしないと。
大黒:AIと人間の違いでいえば、AIは人間が作ったものを学習しているわけですが、人間は自然にあるものを学習しています。その中で特に重要なのが感情で、人間は言語が生まれる以前に感情を持っていたわけです。たとえば、楽しいとか悲しいという概念は言語的な境界線はなくて、とにかく何か感じる。でも言語が生まれて感情が細分化されてきたわけです。
たとえば、「楽し悲しい」という感情は、言語によって細分化されたけれども、それによって生まれた隙間、感情の隙間を人間は理解できます。しかし、AIは人間が作った言語を学習しているので、悲しいと楽しいの足し算でしかないわけです。つまり、効率性はAIだけれども、AIでは埋められない隙間が絶対にあって、そこは人間がやることなんだろうと思います。これからの人間はその隙間を埋めるのが仕事だというふうに育つのかもしれないですね。

梅崎 修(うめざき おさむ)
法政大学 キャリアデザイン学部 教授
マイナビキャリアリサーチLab 特任研究顧問
1970年生まれ。大阪大学大学院経済学研究科博士課程修了(経済学博士)。2002年から法政大学キャリアデザイン学部に在職。専攻分野は労働経済学、人的資源管理論、オーラルヒストリー(口述史)。人材マネジメントやキャリア形成等に関しての豊富で幅広い調査研究活動を背景に、新卒採用、就職活動、キャリア教育などの分野で日々新たな知見を発信し続けている。主著「「仕事映画」に学ぶキャリアデザイン(共著)」「大学生の学びとキャリア―入学前から卒業後までの継続調査の分析(共著)」「大学生の内定獲得(共著)」「学生と企業のマッチング(共著)」等。
大黒 達也(だいこく たつや)
東京大学大学院情報理工学系研究科 次世代知能科学研究センター 特任講師
広島大学 客員准教授
ケンブリッジ大学CNEセンター 招聘研究員
脳神経科学者。1986年生まれ。博士(医学)。オックスフォード大学、マックス・プランク研究所勤務などを経て現職。専門は音楽の脳神経科学と計算論。著書に『芸術的創造は脳のどこから産まれるか?』(光文社新書)、『音楽する脳』(朝日新書)など。