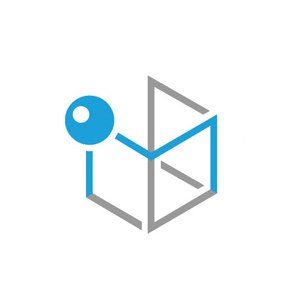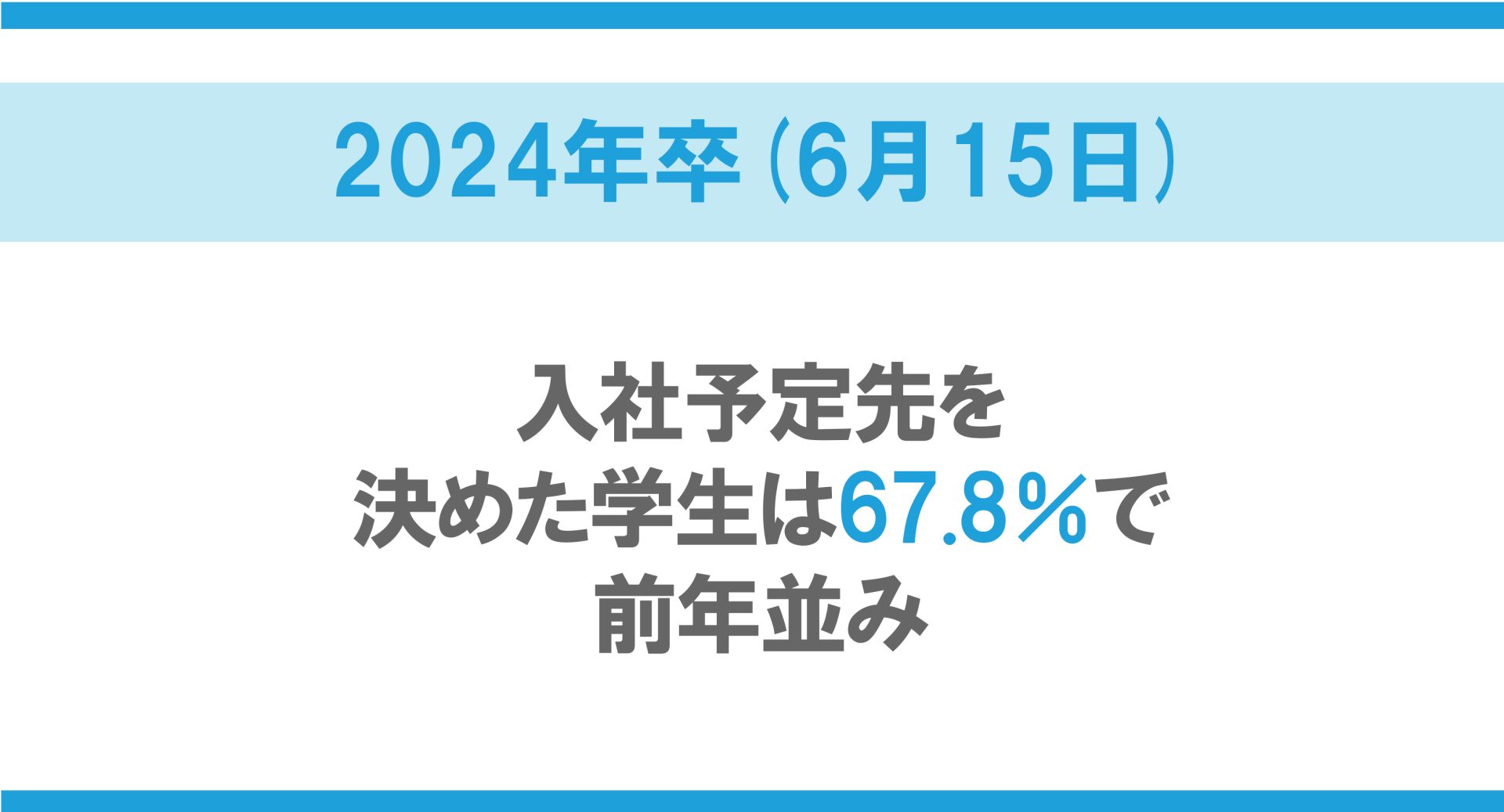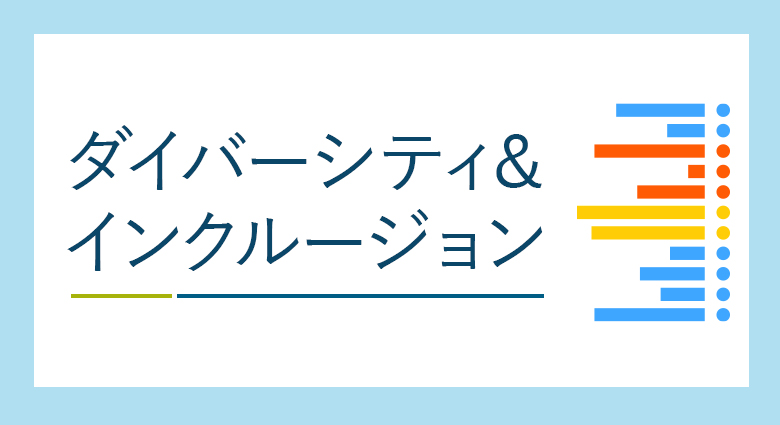ブックリスト・絵本文化と科学~絵本の力について考える(4)~
—駒澤大学・内藤寿子氏

絵本文化と科学
前回(第3回)のコラムでは、キャリア教育につながる絵本をブックリストの形で紹介した。これらの作品は、子供だけでなく大人にも、自分自身を見つめ直すきっかけを与えてくれものであり、また、メディア・リテラシーを磨く場となり得るものだ。
本コラムシリーズを終えるにあたり、今回も引き続きブックリストの形式を取り、絵本と現代日本社会との接点についてお伝えしていきたい。ブックリストのテーマは「絵本文化と科学」。この2つの結びつきについて、違和感を覚える方もいるだろう。しかし、最近の教育の潮流を知れば、それは払拭されるはずだ。
「マイナビキャリアサポート」の「STEAM教育とは?事例と背景、今後の展望やSTEM教育との違い」(2023年2月28日公開)にあるように、現在、5つの領域の学習―科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術(Art)、数学(Mathematics)―を、実社会における問題発見・解決に活かしていくための横断的な教育が注目されている。教育といえば文部科学省の管轄とのイメージが強いが、STEAM教育に関していえば、経済産業省が開設した「STEAMライブラリー」(※1)もある。「STEAM」というキャッチフレーズは、社会連携による新たな教育のあり方を推進する役割を果たしている。
※1:学びのSTEAM化の実現のために、企業・研究機関が参画し始まった事業。教材コンテンツや指導案などが、1カ所に集約されている。 (「STEAMライブラリー」における説明より)
本コラムでこれまで紹介してきた絵本は、まさにジャンル横断的な存在である。加えて、自分自身と社会との関係を、読者みずからが考えるための手助けとなる多彩な要素で構成されている。言葉をかえれば、「STEAM」という教育政策が、21世紀になり輸入される遥か以前から、日本社会では絵本というメディアによって、ジャンルを融合した学びの場が育まれていた。その象徴が、「科学」に関わる絵本なのである。
「絵本=擬人化された動物たちが活躍するファンタジー」といったイメージも強いが、実際は、ユニークな特徴で彩られたさまざまな絵本が出版されている。以下、紹介する作品を通して、このメディアが持つ力を感じていただければ幸いである。
科学絵本とは?
人類が初めて月面に着陸した1969年。科学に対する夢や希望に満ちふれていたこの年に、日本において新たな絵本の取り組みが生まれた。福音館書店による月刊絵本「かがくのとも」の創刊である。
創刊を牽引した松居直氏は、「何かの断片的な知識や情報を提供するのではなく、科学の世界で子どもたちが遊べて楽しめるように内容と表現を工夫した絵本」(『月刊科学絵本「かがくのとも」の50年 かがくのとものもと』福音館書店 2019年の帯に付された言葉より)を目指したと述べている。このような出版方針のもと、『はははのはなし』(加古里子 1970年6月 15号)をはじめとする人気作が数多く誕生し、現在に至るまで、「かがくのとも」は日本における絵本文化の豊かさの源泉となっている。
「科学」という言葉からは、動植物の観察や人体の組織図、実験や化学式などがイメージされやすい。しかし、「かがくのとも」における「科学」の定義は、非常に幅広い。「かがくのとも」の名のもと、自然科学だけでなく社会科学、生活科学、人文科学について取り上げた作品が出版されているのである。
ブックリスト
それでは、日本の絵本は「科学」をどのように描いてきたのか。まずは、生活科学をテーマとする1冊から紹介していこう。
『サンドイッチつくろう』
(かがくのとも傑作集 わくわく・にんげん さとうわきこ 福音館書店 1993年)
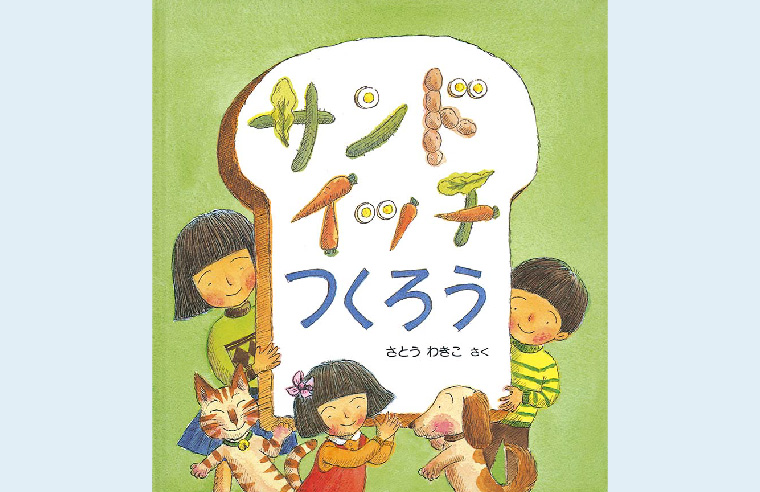
自分でアイスキャンディーを作ってみれば、水の三態を実感することができる。できたてのヨモギ団子を食べたければ、春の野草ヨモギがどこに生息しているのかを知っておく必要がある。このような結びつきから分かるように、科学は日常生活の中に存在するものであり、料理はその代表だといえる。
「かがくのとも」の50年をこえる歩みの中で、料理をテーマにした絵本は何冊も出版されている。『サンドイッチつくろう』は、タイトルの通り、子供たちが協力してサンドイッチを作る物語。卵をゆでる過程などの科学的な正確さと、犬も猫も一緒に食卓を囲むファンタジーの面白さのバランスが、絶妙な科学絵本である。
この絵本には3人の子供たちが登場するのだが、メディア・リテラシーを磨くためのレッスンとして、ぜひ、子供たちの形象を読み解いてみていただきたい。一例をあげておこう。『サンドイッチつくろう』は、登場人物の性別を限定する説明を巧妙に排している。「料理をするのは女の子」「髪が短いのは男の子」といった読者の先入観を揺さぶるこの絵本は、いつの間にか内面化してしまっているジェンダーバイアスに、気付かせてくれる。
『サンドイッチつくろう』の作者・さとうわきこは、「ばばばあちゃん」を主人公した科学絵本のシリーズを書いている。『よもぎだんご』 (かがくのとも傑作集 わくわく・にんげん 1989年)や『ばばばあちゃんのアイス・パーティ』 (かがくのとも傑作集 わくわく・にんげん 1998年)も、日常生活から科学を考えることをテーマにした作品である。一読をお薦めしたい。
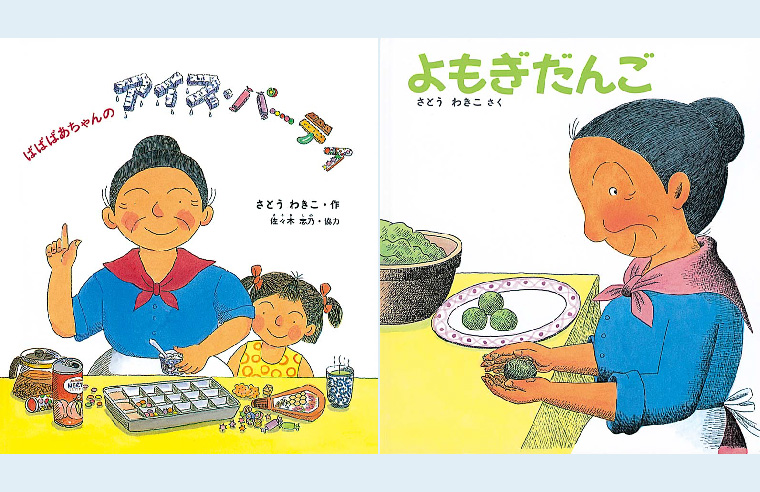
(右)さとうわきこ・作『よもぎだんご』(福音館書店、1989年)
『いっぽんの鉛筆のむこうに』
(たくさんのふしぎ傑作集 文・谷川俊太郎 写真・坂井信彦ほか 絵・堀内誠一 福音館書店 1989年)

月刊絵本「たくさんのふしぎ」は、「かがくのとも」よりも年長の読者をターゲットに創刊された。その記念すべき第1号(1985年4月)が、『いっぽんの鉛筆のむこうに』である。
絵本は、スリランカのボガラ鉱山で黒鉛を採掘している「ポディマハッタヤさん」の写真が、真ん中にレイアウトされたページに始まる。写真の背景には、地下300mにある鉱山の様子が、正確でありながらデザイン性にあふれた堀内誠一の筆致で描かれている。隣のページの文章は、詩人として名高い谷川俊太郎によるもの。「鉛筆のシンのなくてはならぬ材料」が、固有名を持った1人の人間による真摯な労働の産物であることを読者に伝えている。
1本の鉛筆が1人の日本の小学生の手元に届くまでを描いた『いっぽんの鉛筆のむこうに』は、流通やグローバル経済といった社会システムを絵本という形式で描き出した作品である。本書を読めば、鉛筆という〈見えるもの〉を通して、その背後にある〈見えないもの〉を想像することの大切さや、自分と世界とのつながりをはっきりと感じ取ることができる。
『いっぽんの鉛筆のむこうに』は、社会科学的思考への第1歩となる絵本だが、人文科学との出会い―言語、文化、歴史を知る―という特徴も有している。たとえば、アメリカ西海岸から鉛筆の材料を運ぶコンテナ船はメキシコ国営船社のもの。コック長の「ミグエル・アンヘル・シップさん」の先祖はマヤ族だ。また、絵本で紹介されている船内の食事メニューはスペイン語(日本語訳付き)で、その中には、メキシコやマヤ族と深く結びついた飲み物「ATOLE アトーレ[トウモロコシ粉をミルクやチョコレートでといたあたたかいのみもの]」などが含まれている。このメニューのページは、食文化の多様性を伝えると同時に、現代社会と植民地支配の歴史が通底していることを読者に教えてくれる。
1985年に「たくさんのふしぎ」版が発行されてから、およそ40年が経った現在、日本社会において鉛筆は、変わることなく使い続けられている。だが、絵本に登場する国や地域、人びとの状況は大きく変わった。(※2)このような視点に立って作品と向き合えば、『いっぽんの鉛筆のむこうに』という〈見えるもの〉から、1985年~2023年にかけての国際社会の変化という〈見えないもの〉を浮かび上がらせることも、可能なのではないだろうか。
※2:たとえば、2019年以降、内政問題を抱えるスリランカでは、経済危機の深刻さが増している。詳しくは、外務省「スリランカ民主社会主義共和国 基礎データ」をご覧いただきたい。
なお「かがくのとも」からも、『いっぽんの鉛筆のむこうに』とテーマが重なる社会科学の絵本が発行されている。一例をあげれば、『うおいちば』(かがくのとも絵本 文・安江リエ 絵・田中清代 福音館書店 2016年)は、自然科学的な要素も有する1冊である。本書を通読すれば、食卓にのぼる魚料理がこれまでとは違ったものに見えてくるはずだ。
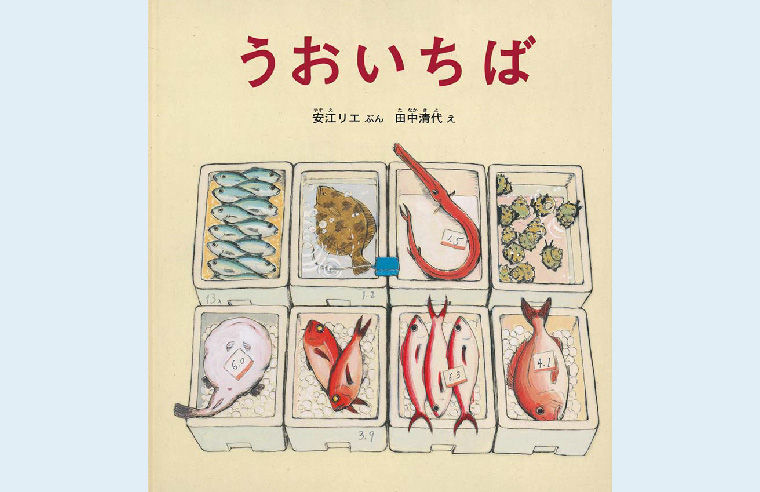
「美しい数学」全6巻
(『10人のゆかいなひっこし』『新装版 すうがく博物誌』『壺の中』『赤いぼうし』『3びきのこぶた』『ふしぎなたね』 童話屋 初版1981年~1995年)

ブックリストの最後として、数学を題材にした科学絵本「美しい数学」(全6巻)を紹介したい。このシリーズは、芸術家(安野光雅)、数学者(野崎昭弘、森毅)、編集者(安野雅一郎)の協働により生み出されたものである。6冊それぞれには、「数と量」「順列と組み合わせ」といった数学的なテーマがあり、これらのテーマは、安野光雅のユーモアに満ちた細密画により物語化されている。
第1作『10人のゆかいなひっこし』は、10人の子供たちを主人公にした文字のない絵本。「10-1=9」といった数式(加法・減法の概念)を、視覚的要素で実感させてくれる魅力的な1冊である。絵本の中では、左ページの家から右ページの家へと1人ずつ引っ越していくのだが、子供たちの移動の様子は省略されている。そのため、読者みずからが、複数のページの絵を見比べて、想像力を働かせ、子供たちの変化や人数の違いについて考えていかなくてはならない。
『10人のゆかいなひっこし』は、このような特徴を持った科学絵本だが、実は、仕掛け絵本でもある。作品に登場する2つの家、その外観には複数の窓が描かれており、いくつかの窓はガラス部分が切り抜かれている。それゆえ、ページを重ねてみると、誰もいなかったはずの窓から、子供が顔をのぞかせたりする。ぜひ、この仕掛けを自分の眼と手で体験し、『10人のゆかいなひっこし』に込められた数学の「美しさ」を実感していただきたい。

「美しい数学」シリーズの中で、特に大人にお薦めしたい作品がある。第6作『ふしぎな たね』だ。物語は、怠け者の主人公が仙人から不思議な種を2粒もらうところから始まる。「ふしぎな タネを あげよう。その タネを 1こ やいて たべれば 1年かんは もう なにも たべなくても おなかが すくことはない。また この タネ 1こ 今 じめんに うめておくと、らいねんの 秋には かならず みのって 2こに なる」という仙人の言葉に導かれ、主人公は日々の生活を積み重ねていく。そして、種が増えるにつれ、主人公を取り巻く環境も変わる……。
『ふしぎなたね』の数学的なテーマは倍数であるが、そのテーマを読者に伝えるための物語の中では、自然科学、社会科学、生活科学、人文科学が有機的に結びついている。たとえば、『ふしぎなたね』は、人間の歩みと社会の形成―たった2粒の種から、「計算」という文明が発達し、農業や商業などが生まれ、人びとのコミュニティが作られていく―を描き出す。さらに、ページをめくるにつれ、「人間にとって働くとは?」という問いかけも浮かび上がってくる。
幅広い「科学」により構成された『ふしぎなたね』は、科学絵本の1つの到達点だといえる。読者のリテラシー能力にあわせて、多種多様なメッセージを発してくれるこの絵本を、大人の視点から、さらに読み解いてみてはいかがだろうか。
絵本=メディア・リテラシーを磨く場
「絵本の力について考える」と題した本コラムも、今回で最後となる。第1回では、絵本の視覚的要素に焦点を当て、絵本がもたらす学びについて紹介した。第2回では、翻訳絵本が多様性と出会う場になりうることを取り上げ、第3回では、絵本というメディアが日本におけるキャリア教育に寄与してきた歴史を示した。
連載を終えるにあたり、あらためてお伝えしたいことは、絵本とは、どのような世代の読者にとっても意味を持つメディアであるということだ。これまでのコラムで述べてきたように、絵本の構成要素の中でも、特に視覚的要素はメッセージの宝庫であり、読者の立場にあわせた多岐にわたる解釈が可能である。
言葉をかえれば、絵本を読むことを通して、リテラシー能力の異なる個々の読者―子供も大人も、園児も保護者も―は、それぞれに必要な気付きや学びを手に入れることができる。また、大人になって初めて気付いた発見に考察を加えていけば、子供の頃に抱いた読後感とは異なる作品の魅力に出会える。
『フレデリック ちょっと かわった のねずみの はなし』(レオ=レオニ 訳・谷川俊太郎 1969年 好学社)を例に述べれば、この作品を通して、子供たちは個性を活かすことの大切さを知るだろう。

冬を越すために、「五ひきの ちいさな のねずみたち」は食べ物を集めているのだが、その中でフレデリックだけは違う行動をとる。その姿は、まったく働いていないかのようにも見える。しかしのちに、フレデリックが集めたものは、困難な状況に陥った仲間たちを救ってくれるのだった。柔らかな色彩で、「労働とは多様なものである」というテーマを描き出す『フレデリック』は、まさに子供にとってキャリア教育の第一歩となる作品だ。
そして、大人になって、あらためて読み直せば、この絵本に「ダイバーシティ&インクルージョン」を見出せるはずだ。フレデリックのあり方に戸惑いながらも、4匹はこの仲間と言葉を交わし続ける。小さなのねずみの集団は、フレデリックを決して排除しない。「個性の異なる他者の集まりであるからこそ、新たな道を切り開いていくことができる」。『フレデリック ちょっと かわった のねずみの はなし』が発するこのようなメッセージは、出版から50年以上が経った現在においても、決して古びていない。
絵本とは、子供を第一の読者として想定し出版されたメディアだが、そこからは現代社会を考えるためのさまざまなヒントを紡ぎ出すことができる。まずは、本コラムシリーズで紹介した作品から、手に取ってみていただきたい。
著者紹介
内藤寿子(ないとう・ひさこ)
早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。2010年より駒澤大学に着任。現在、総合教育研究部日本文化部門教授。専門は日本文化。映画や雑誌、絵本など、いわゆる大衆メディアと呼ばれるものを題材に、近現代日本文化および日本社会について考察を行っている。