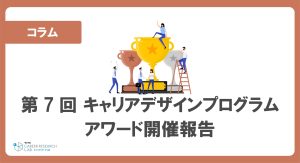
7回目の開催となった「学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」。学生の職業観涵養を促進する効果的な取り組みを周知することで、プログラムの質的向上および実施企業数の増加を実現し、学生と企業のより精…
1970年生まれ。大阪大学大学院経済学研究科博士課程修了(経済学博士)。2002年から法政大学キャリアデザイン学部に在職。専攻分野は労働経済学、人的資源管理論、オーラルヒストリー(口述史)。人材マネジメントやキャリア形成等に関しての豊富で幅広い調査研究活動を背景に、新卒採用、就職活動、キャリア教育などの分野で日々新たな知見を発信し続けている。主著「「仕事映画」に学ぶキャリアデザイン(共著)」「大学生の学びとキャリア―入学前から卒業後までの継続調査の分析(共著)」「大学生の内定獲得(共著)」「学生と企業のマッチング(共著)」等。
16件中
1件 - 10件
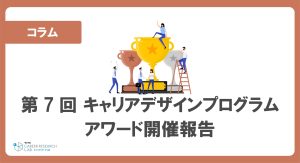
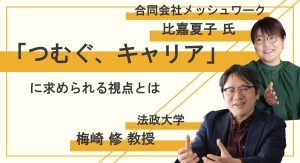
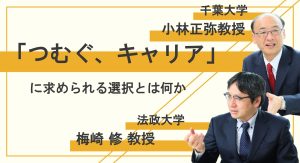
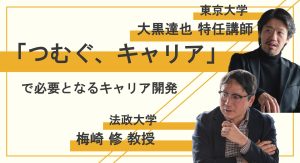
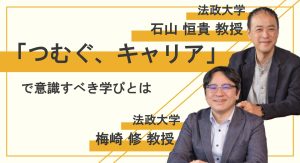
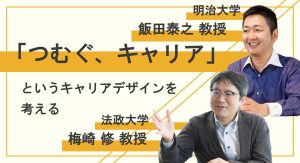




1