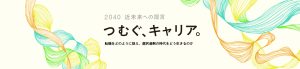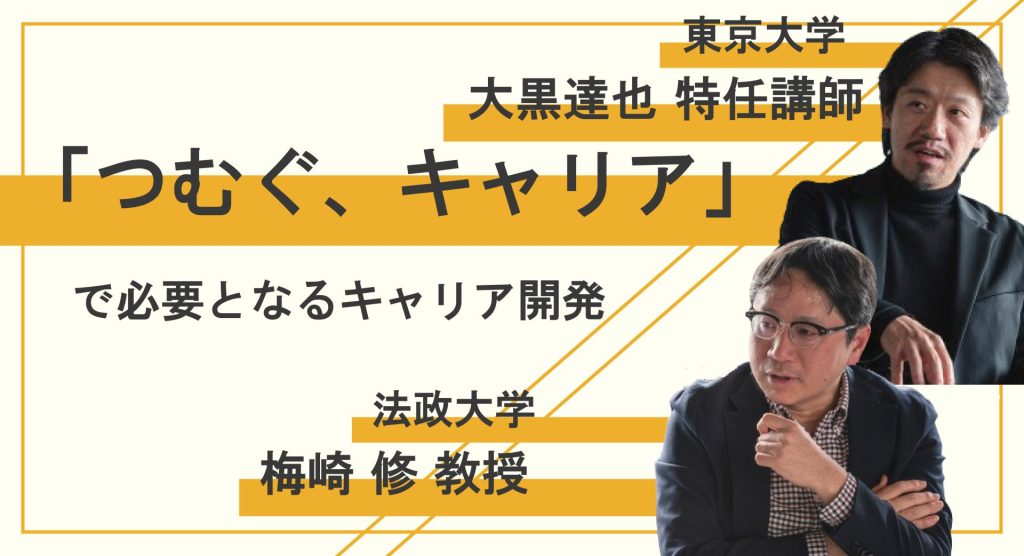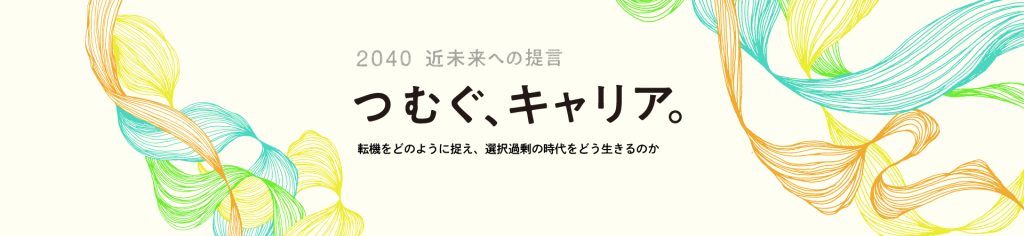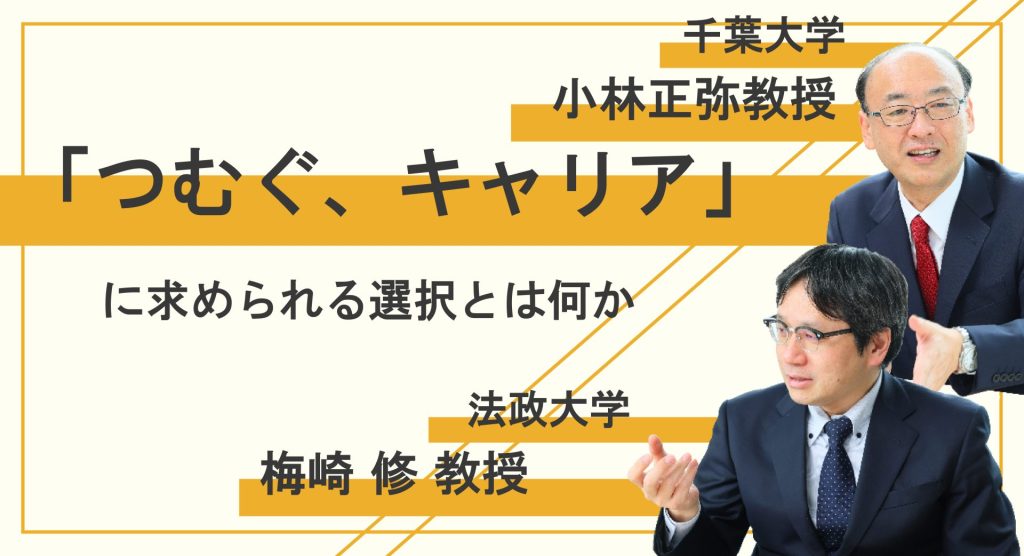
ネットワークではなくメッシュワーク、輸送ではなく徒歩旅行でキャリアを考えることの意味とは何か。これからのキャリア論に求められる人類学の視点とは?(対談:人類学者 比嘉夏子氏)
『つむぐ、キャリア。』対談シリーズ、最終回となる今回は、社会が大きな転換期を迎える中で、未来予測の難しいこれからの時代を生き抜くヒントが見つかるかもしれないと期待を集める人類学の比嘉夏子氏をお迎えした。人類学とはどんな学問か、企業研究における有効性、これからのキャリア論を考える人類学ならではの視点について、『つむぐ、キャリア。』監修者の梅崎教授と議論していただいた。

(写真左)法政大学キャリアデザイン学部 梅崎修教授
(写真右)合同会社メッシュワーク 比嘉夏子氏
目次
現場に入り生活をともにしながら理解を深めるのが人類学の手法
梅崎:この対談シリーズでは、これまで経済学、経営学、脳神経科学、政治学と、さまざまな専門領域の先生方にお声がけをして、これからのビジネスキャリア、ライフキャリアをどうつむいでいくべきかについて議論をさせていただきました。
比嘉先生は人類学がご専門で、人類学のフィールドワークで培った視点をビジネスの現場でも生かすべく、合同会社メッシュワークを立ち上げて社会人向けゼミなども開催されています。そこでまずは、人類学についてご説明いただき、その後でメッシュワークでの活動についても詳しくお聞きできればと思います。
ところで、人類学者と聞くと、一般の人には未開の地に行って探検している人みたいなイメージがあると思うのですが、人類学とはどんな学問なのでしょうか。
比嘉:学問名が示すように、「人間にまつわるあらゆることの学問ですよ」と宣言しています。アメリカとイギリスでは人類学の系譜も違うんですが、アメリカでは人類学のなかに4つの分野があり、文化人類学・考古学・自然人類学・言語人類学に分けられるのが一般的です。
霊長類の研究や考古学の発掘調査のようなイメージを持たれている方もいらっしゃいますが、現代社会の人間を研究する方、歴史をさかのぼって古い時代の生活・文化を研究する方、あるいは生物学寄りのアプローチを取られる方もいます。その中で、私自身の専門としては文化人類学、同時代の人たちを自分自身でフィールドワークして理解するというアプローチを取っています。
私の場合、オセアニアのトンガをフィールドにさまざまな島に見られる社会の経済実践や日常的相互行為について研究してきました。その経験を生かして、メッシュワークという会社を設立して企業のアドバイザリー業務やコンセルティング業務なども行っていますが、400人が住む村を見ることと、400人が所属する会社を見ることって、私はあまり変わらないと思っています。人類学者は、自分自身が現場に入って人間集団、人間社会を見ていきます。
調査者自身が調査対象である社会や集団に加わり、長期にわたって生活をともにしながら観察し、資料を収集する方法を「参与観察」と言いますが、ただ遠巻きに観察するのではなくて、自分たちも現場に入り、人と関わり、一緒に手を動かしたりしながら同時代的な人々や、社会コミュニティを理解していくわけです。
梅崎:研究対象が幅広くて一言では説明できないと思うのですが、文化人類学に限定してみると、起源としては西洋社会が自分たちの文化とは異なる文化に初めて出会った時に、「これを説明したい」「理解したい」ということがスタートですよね。
比嘉:そもそも植民地期に発達した学問なので、列強が領土を拡大し統治する目的とともに研究が進みました。かつては、非西洋の人々に対して「未開」だとか「野蛮」だと形容していた時代がありました。
その中で、ポーランド出身のイギリスの人類学者ブロニスワフ・カスペル・マリノフスキやフランスの人類学者であるクロード・レヴィ=ストロースが、彼らの中にも独自の論理や合理性があって、社会的なシステムがあるということを見いだしていきます。西洋近代が相対化されていくプロセスと、人類学が発展していくプロセスは、重なり合っていたと思います。
梅崎:西洋・近代社会が拡大していく中で、物珍しさで他の文化を見ていたものの、これはこれで一つの独立した文化であって別の解釈が可能だよねとなっていったわけですね。
しかし、自分はもうすでに何かの文化に包摂されて生活している状況で、他の文化や生き方を理解していくのは、とても難しいことです。文化人類学の場合は、それを参与観察によって理解していくと考えていいのでしょうか。
比嘉:こういう土地にこういう習慣があるとか、文化的な営みがあることを文献から比較したり、社会構造を見ていくこともできなくはないんですが、人類学では自身でフィールドワークを行わないことを批判的に言われることが少なくありません。やはり、自分たちが現場に行くということが基本です。
私自身もトンガで経験したことですが、人々が約束の時間に遅れるとか、物を盗まれるとか、嘘をつかれるといったできごとが度々あったんですね。最初はすごくイラッとするし嫌なんですが、そうした物事には何か理由があるはずで、そのことが頻発すればするほど、そこに何か社会的な理由があるんじゃないかと思うんですね。
個人的な性質に帰するのではなくて、私にとって違和感あるできごとも、フィールドの社会では許される論理があるのかもしれない、それよりも別の何かを優先しているのかもしれない。そんな私とフィールドの人々の摩擦があるからこそ、理解が深まっていくという経験をしました。
梅崎:参与観察は異文化を理解する際に、自分に埋め込まれている文化との摩擦によって自分にも変化が起きる。そういう意味では、観察することによって自分も変わってしまうから、動態的な研究方法ですね。
比嘉:「参与する」というのは身体性がとても重要で、私の身体がそこにあり、その人たちと同じ場や時間を共有することで初めて何かに気づけるんですよね。私の恩師は、人類学のことを「フィールド哲学」と表現しましたが、身体を伴いフィールドに出て、その場で思考が進んでいく、まさにその場に自分が紐づけられているというところが特徴だと思います。
人類学が企業文化を研究対象とするようになった背景

梅崎:研究対象としてトンガを選ばれたのはどういう理由なんですか?
比嘉:学部生の頃は、沖縄でフィールドワークをして、豚肉の食文化を調査することで人と家畜の関係について研究していました。沖縄では家畜としての豚と人間の距離感が非常に近くて、それがとても新鮮で、日本の他のエリアでは見つけられない光景でした。
ただし沖縄でのそれは戦前〜戦後の時代の語りのなかにしか存在しなかったので、海外ならまだそういう光景や生活が見える場所があるのではないかと思い、知り合いの先生にトンガのことを聞いて、修士論文の予備調査のためにトンガに行くことにしました。現地語もわからずに行ったので、最初の1カ月ぐらいはいくつかの島を回ったりして過ごしていました。
そのときに知り合った現地の方の村に連れて行ってもらい、結局、その村がフィールドとなって本調査をし、博士課程に進学してからもずっと通い続けるようになりました。足かけ20年以上、通算すると2年以上は滞在したと思います。
季節によって農業や牧畜の暦が違ってくるので、一通り見るという意味で、2年ぐらいはフィールドワークをするというのが、人類学者のコンセンサスとしてありますね。
梅崎:人間の歴史から考えると、近代化とか産業化はとても大きな変化なので、研究テーマとしても非常に奥深いと思います。
それに比べて、現代の企業を分析するという場合には、どちらかというと微細な文化的差異になりますよね。人類学が、企業文化とか組織文化なども研究対象とするようになった背景には何があるのでしょうか。
比嘉:歴史的に考えると、人類学が対象としてきたものはいわゆるマイノリティの人たちで、中心よりも周縁から世界を見るというアプローチを取ってきました。それに対して、ビジネスや資本主義の現場はまさに現代社会の構造的中心にあるともいえるので、そこに人類学者が入って関わりを持つのは忌避される傾向があったと思います。まさに植民地主義の反省というか、権力的な構造の中で人類学が使われてしまったことへの内省と自己批判が強いような気がします。
梅崎:自分の文化を相対化しようとして研究が進んできた側面と、アメリカの文化人類学者のルース・ベネディクトの『菊と刀』(※)のように統治するために他国の文化を理解することを目的として研究が進められてきた側面がある。使い方一つで薬にも毒にもなるという反省ですよね。
※『菊と刀』:ルース・ベネディクトの戦時中の調査研究をもとに1946年に出版された。日本人の行動や文化の分析からその背後にある独特な思考や気質を浮き彫りにした
比嘉:人類学者たちは現地の人々の営みををわかりたいという真摯な気持ちで研究していても、その知見がどのように応用・活用されるのかという部分に関してはいろいろな議論がありますね。
参与観察することで企業文化が明確に
梅崎:人類学者であるノースウエスタン大学の宮崎広和教授がアメリカで活躍されていて、『金融人類学への誘い トレーダーたちの日本と夢の終わり』という本を出版されていますが、金融トレーダーという資本主義のど真ん中の組織にもやっぱり企業文化があって、独自の思考方法みたいものがあるという研究ですよね。
そういう近代化・以降に出てきた組織であっても、参与観察でなければわからない部分があるのでしょうか。
比嘉:そうだと思います。例えば企業も業界や職種によって使う言語が異なりますよね。トンガでも、日本語にはない概念がトンガ語にある場合もありますし、日本語では複数の言葉で表現しているものがトンガ語では一つの言葉に該当することもあります。彼らの認識を、その場で実際に使われる言語を通して知ることも参与観察の一つのゴールなんですね。
日本企業でも、社内でよく使う単語や、特定の会議によく出てくる言葉があると思います。それは、多分その組織の中で作られる共通認識や常識を反映しているので、そのような言語を丁寧に調べていくことで組織の特徴がわかることも多いと思います。
梅崎:たとえば、20年サイクルで会社の文化が変わるとしても、入社5年目の人にとっては今の状態が当たり前なのであって、自分を取り巻く組織文化を自分で相対化して理解するのは非常に難しいですよね。
しかし、何かのきっかけで仕事をするのがしんどくなったり、萎縮しちゃったりすることもあります。そのときに初めて、組織文化と自分との間の距離に気づくことになります。そうだとすれば、本当の意味のダイバーシティみたいなものを考えれば、ただ組織文化に適応すればよいわけではなくて、適度な距離の適応状態でいることも重要だと思うんです。
比嘉:そういう意味では、私たち人類学者が組織に入ってフィールドワークをして、その企業らしさや組織文化を明らかにしていくこともできますが、組織の中の人自身もそれをできた方が面白いし、もっと解像度が高いと思います。
そのときに鍵になるのはよそ者の目を持っている新入社員とか中途入社の社員です。まだしっかりと組織に染まっていなくて、違和感をたくさん感じている人たちは、人類学者の目と似た目を持ってるんじゃないかと思うんです。その違和感に気づいて詳細にメモを取っていくと、先生がおっしゃったような組織との適度な距離感が保てるようになるし、それは組織にとっても良いことじゃないかと思います。
組織と個人との適度な距離感と関係性

梅崎:集団である限り、構成メンバーには一定の組織社会化は必要ですが、全員が適応し過ぎてしまうと、本人たちは満足しているはずなのに、長期的に持続できなくてバーンアウト現象が起きてしまう危険性があります。また、形だけイノベーションセンターみたいなスペースを作っても、組織文化が変わらない。結果的に、イノベーションが起こらないケースもあります。
そこでは「適応」のコントロールが必要で、距離も調整できるという状態が大切ではないでしょうか。そのためには、内でもあり外でもあるという参与観察者が持っているトレーニングされた目が求められますね。
比嘉:フィールドデータを分析する際は、少し引いたところにメタな視点の自分がいて、調査者の自分を含めたフィールドでのできごとを分析しています。一方でフィールドの渦中にいるときにはとにかく一所懸命に現地の人とやりとりをする自分がいますし、その両方の視点があって自分の人類学の営みは成立しているような気がします。
梅崎:そういう意味では、人類学のトレーニングを受けるべき人を組織の中で探せば、組織の文化なりイノベーションを起こすべき人材だと思います。初期人類学にある統治の思考とは違って、うまく舵を取るみたいな思考ですね。
キャリア論では、「境界を越える」という話がよく出てきます。ただ単に越えるだけではなくて、行って、帰ってくることが重要です。「往還する」ことによって、うまく組織を変えられる人材が求められていると思います。
どっちつかずの状態を許容する文化、余白が必要
比嘉:人類学者としての自分は、どっちつかずなところに常にいるなと思うんです。ある時は中にどっぷりと入るけど、またある時は外側にもいて、結局どこに立っているのといえばどこにも固定されないような。そういう存在だから見えることがあるのだと思います。
コミュニティや組織でも、「どっちつかずの状態」を許容する文化、いわゆる余白が必要だと思います。どっちつかずの人材であるからこそ持てる視点や気づきが、うまく活かされていくということが組織には必要ではないでしょうか。
梅崎:企業の人材マネジメントにおいても組織の境界を自由に往還できる機会を作れるといいのですが…、現在よりも日本的雇用システムが強かった時代のほうが、出入りの自由度は高かったように思います。
今の研修って、無駄を省いて短くしろ、何を得られるかはっきりさせろという感じです。そうすると、自由度がなくなるように思います。かつては「いろんな会社の人と仲良くなってね」くらいのアバウトさがありましたね。
比嘉:外の異質なものと出会って、気づけることってとても多いですよね。私たちが企業のサポートをする際は、普段、単一的な見方とか社内の論理に縛られてしまっている状態を、まさにイノベーションのように、たがを外し、普段とは別の視点をもってもらえるように、人類学的なアプローチによって促しています。私たちの研修やプロジェクトをとおして、クライアントの方々が自己を相対化し揺さぶられて、思考が進むような機会にできればいいなと考えています。
体験を通じて自分を相対化するのが人類学的なアプローチ
梅崎:相対化というのは頭の中だけでやっているわけではなく、体感するという身体性が重要ですね。リフレーミングとかアンラーニングという言葉だけを理解するのではなく、自分の身体で体験してみる。摩擦が生まれることで相対化されます。
一方、相対化するとか物事の捉え方を変えるというのは、人を不安にさせます。個人の認識とアイデンティティを手放すことにもなるのですから。
比嘉:メッシュワーク人類学ゼミ生である社会人の方々も、学びのプロセスのなかで時折非常に不安そうな顔をされますし、自分の信じているのとは異なるロジックがやってくると不快に思うこともあるかもしれません。私個人としては、すべてに対して共感することなどは不可能だと思っていますが、共感しなくても理解することはできると思っているので、どんなに異質なものであっても、どんなに自分と異なる論理であっても、まずはきちんと理解しようとすると態度が重要です。
そのプロセスは、新しい知識をインプットしていくこととは全然違います。知識は自分が持っている本棚の中に新たな本をうまく収めていくイメージだと思うんですが、今ここで言っていることは、その本棚の形を変えましょうという提案なんです。
梅崎:この対談シリーズでも脳神経科学者の大黒達也さんに、クリエイティビティには複雑なものを単純化するタイプと、複雑なものを複雑なものとして理解するタイプの2タイプあるというお話をうかがいました。今のご指摘は、その話と対応していて、人は単純化すると安心する。
しかし、ずっと安心しているとクリエイティビティは生まれないわけです。クリエイティビティを生み出すためには複雑性を求めるという逆のベクトルが必要なんですが、これは今までわかっていたものを崩しちゃう。一般的にはそれは好奇心とかで乗り越えるしかないんですよ。
それを企業がやるのは簡単ではないですし、社会学的なアプローチで考えると社会問題を考えなくちゃいけないというような気持ちになりますが、人類学的なアプローチであれば、ちょっと考古学みたいな雰囲気もあるから、楽しく取り組める可能性がありますね。
比嘉:他の学問領域と比べて相対的に、人類学者は「社会課題」を字義通りには捉えていない気がしますね。もちろんフィールドに入って多様な現実に向き合うと、貧困、差別、暴力などの問題に生で触れることはあるんですが、そこに課題感を持って入っていってない。むしろそもそも何が課題なのか、いやそれは別に課題ではないのかもしれない、といった引いた目を持っている。そこは他の学問と違うかもしれないですね。
人類学では結論よりもプロセスで感じる揺らぎや摩擦を大切にする

梅崎:先日、メッシュワーク人類学ゼミの展示を拝見しましたが。「自分がどう揺らいだか」とか「考え方が変わった」ことを文章で書くと、ちょっと重くなってしまいますが、展示だと楽しそうに見えますね。人類学×アートみたいな印象を持ちました。
比嘉:人類学の調査から得られたデータは膨大で、たとえば論文だとボリュームは限られますが、本の形であればいくらでも分厚く書ける。でも、分厚いものを読む人というのは限られてくると思います。メッシュワークゼミでのゴールは学会発表や論文出版ではないので、新規性よりも現場で聞いたエピソードや人々に出会い思考したプロセスが重要で、そういったリッチな経験を、展示を見に来てくださった方々とともに共有することを大切にしています。
社会人のゼミ生たちにも、いわゆる「結論」は出さなくてもいいと伝えています。大切なのは結論じゃなくて、やってみてここまでわかったとか、こんなことが見えた、あるいは見えなかったという事実をきちんと形にして提示し、それを見に来た人との対話がまた進めばいいわけです。わかるって本当はエンドレスじゃないですか。ですからゼミの展示も通過点だと位置づけています。
梅崎:まさに共感する部分です。企業内でワークショップする際も、1時間で結論を出そうとするとプレッシャーになるんですよね。グループディスカッションを始めても、そろそろかなってタイミングで、結論を出さなきゃなっていうアイコンタクトが始まり、ゴールに向かって一直線に進みます(笑)。
それは多分、結論を出すことが自己目的化しているからですね。3回に1回とか2回に1回は結論が出なくてもよいというゆるい感じにしたようがよい。結局10回のうちの1回がすごい結論になるというのが本当のクリエイティビティなんだと思います。
比嘉:社会人ゼミやスクールは、グループワークを取り入れるケースが多いようです。参加者を増やしてグループワーク形式にした方が、効率的ですが、それではつかみきれない感覚や至らない思考があると思いまして、メッシュワーク人類学ゼミは個人プロジェクトをやってもらうところが特徴です。自分が調査対象の中に飛び込んで向き合って、いろんな不安や、ざらついた感覚をも覚えながら、とにかくノートを取りつづけて、それをオンライン上で共有し議論していきます。
梅崎:結局、グループディスカッションって本人たちの満足度が高いから、場が持つんですね。ただ、人数が多くなると、コミュニケーションが自動的に発動して、楽しいことが自己目的化してしまう危険性があります。
比嘉さんの場合は、一人ひとりがフィールドとの対話を繰り返してきたことに対して横から合いの手を入れていきますよね。参加者は、フィールドとの対話、コーディネーターとの対話、仲間との対話の三つの対話をすることになります。
比嘉:人類学ゼミ全体が人類学の営みをいかに社会に開いていけるかというトライアルだと思っています。自分の研究では、フィールドノートを書いて、そこから抽出したものを、大学院のゼミとか研究会みたいな場所で共有しながらディスカッションして論文にしていくというプロセスを取ってきたわけで、基本的に一人仕事なんですよね。
しかし、社会人ゼミの目的を考えると、互いの書いたものを見合うことによる学びの効果も非常に大きいですし、そこでは1人だったけど1人ではない感じを持ったってみなさんおっしゃってくださっていて、究極的には1人でフィールドに向き合うしかないんだけれども、1人で向き合う仲間がいるからこそ頑張れるといったことが起きていたようです。
言語化することが自己内対話を促し内省につながる
梅崎:会話のコミュニケーションと、書いてコミュニケーションをするのはやはり違っています。書いたものの最初の読者は自分です。喋ることに比べると、書くことは自己内対話を内包しています。推敲的なコミュニケーションになっています。
比嘉:人類学ゼミでも、徹底的に言葉に落としてくださいと話していて、膨大な量のフィールドノートから何を抽出してどう編集して、どんなメディアで伝えようか考えていただきます。非常に手間のかかるプロセスを経ているんですが、企業での研修ももっと言語化することを徹底的にトレーニングできるんじゃないかと思っています。
梅崎:やはりトレーニングが必要ですね。実は今、認知科学者の諏訪正樹先生(慶応義塾大学)と2人で小説を読む研究会をやっています。諏訪先生と自分とでは視点というか読み解き方が違うんですよね。私の場合、概念が先行してしまうというか、認知科学における言葉の分析の仕方を学んでいます。言葉は、氷山の一角で、その下には違和感とかザラザラした感じあるわけです。
今、比嘉さんがおっしゃっているように、「徹底的に言語化しろ」っていうのは、安易な言語化をスルーして、感じているものを自己内対話なり、他者との対話の中からギュッと絞り出す、それが本当の言葉と体による内省なんだと思います。
比嘉:目の前のできごとや自分の経験を書き言葉にするというのは本来自分以外にはできないから、誰かに頼ることができないんです。でも、喋るときは借り物の言葉でいくらでも喋れる傾向があるじゃないですか。
それらしくプレゼンするとか議論するのはいくらでもできるんだけど、「あなた自身が見たことや経験したことを徹底的に言葉にしましょうね」って言ったら、絞り出すように書くしかない。でも、そうやって書いてみると、そこで起きていた出来事が強く意識化されるんです。
方法論ではなく、対象に向き合う態度が大切
梅崎:最近は、アート教育もすごく流行っています。ビジネスパーソンを対象に直感とかひらめきとかをテーマにしたアートスクールなどが開かれたりしていますね。何か変えなくちゃという問題意識があるから、アートとか人類学とかビジネスから遠かったものに注目が集まっています。
比嘉:ビジネスのコンテンツに近いものは道具化されやすいと思うのですが、人類学って道具化しづらいんです。メソッドとして説明するというのがしっくりこないというか、いわゆる方法論ではないと思っています。
むしろ対象に向き合う態度や物の見方、何かそういう曖昧な表現になってしまうんですが、それは一度持つととても強い。知識は明日忘れているかもしれないけど、態度やマインドセットは一度自分のなかに入れば折に触れて思い出すし、呼び覚まされるし、残ると思います。
さまざまなものを織り込んでいくメッシュワークのイメージでキャリアを考える
梅崎:既存の学問に比べると人類学は、統合性があるという印象です。人類学の入門書を読んでみると、キャリア論に読み替え可能なものがたくさんあります。
たとえば、イギリスの社会人類学者であるティム・インゴルドは、移動について「徒歩旅行」と「輸送」という区分をしています。キャリア論で考えてみると、輸送というのは企業に入ってキャリアを管理されて定年まで務めるイメージに近いのです。でも、今や会社が個人のキャリアを計画してくれないわけで、個人のキャリア自律が求められている。
こんな変化があるのですが、自分を自分で「輸送」しようとするようなイメージなんです。しかし、自律とはそういうことを言っているのではなくて、インゴルドの言葉を借りると「歩行」していくイメージの方がピッタリですね。
キャリア論の限界が指摘されるようになってきたときに、人類学は近代の限界を考えていたから、人類学が作ってきたキーワードには力があると感じます。人類学が持っている全体性や統合性の背景には何があるのでしょうか。
比嘉:人類学者にとっては、対象と向き合って自分の身体で格闘するのが、認識の仕方であり、世界との関わり方だと思います。インゴルドの言葉は、フィンランド北東部のサーミ人たちをフィールドに、トナカイの狩猟を研究してきた中で出てきた言葉で、その身体感覚に根ざしているからこそ説得力があるのではないでしょうか。
彼は、ネットワークとメッシュワーク(※)の対比についても解説していますが、現代社会に生きる私たちの行動は、先生がおっしゃったように、自分で自分を輸送するようなあり方になってしまっていると感じます。どこに行くにも最短、最速で行くことが当たり前になっていますが、いっぽうで自分の人生を最短、最速で進めることは絶対無理だともわかっているはずです。
それは当たり前なはずなのに、「合理的個人」なるものが想定されて、そういうモデルが無批判に語られている場所に出くわすと、私は戸惑ってしまいます。
※「私たちが「メッシュワーク」である理由」より
梅崎:社会学でもネットワーク分析というのがあるのですが、二つの立場にわかれています。人はネットワークの中に埋め込まれているから意思決定はそれに制限されるという立場と、ネットワークは合理的に構築可能だからうまく設計すればいいとする立場があります。これは、両面の真実なのですね。
ただ、「おぎゃー」と生まれて親のネットワークの中で生きていくときに、自分でどこまで合理的にネットワークを作っているのか。実際は、ネットワークではなくてメッシュワークのようにさまざまなものを織り込んでいくイメージのほうがしっくりくるのではないでしょうか。いい言葉ですね。
このシリーズで対談した政治学者の小林正弥さんは、人間が家族やコミュニティや国家など、さまざまな具体的状況を負っていることを「負荷ありし自己」と表現されていました。自分が置かれた環境の中で、何かを選んで生きていく感覚は、人類学で言うブリコラージュ(※) という言葉がしっくりきます。
※ブリコラージュ:フランス語で「ありあわせの道具、材料を用いて自分の手でモノをつくること」という意味で、文化人類学者のクロード・レヴィ=ストロースが1962年に発表した『野生の思考』で取り上げた概念。
仕事モードとプライベートを再接続し、ワークとライフを地続きで捉えてみる

比嘉:散歩するときに、いかに最短、最速に歩くかなんて考えませんよね。そろそろ桜のつぼみが大きくなってきたなとか、今日はちょっと川の流れが早いなとか、ゆっくり散歩するほうが気づけることが多いということは、みなさん身体的にわかっているはずです。
そうやって世界と向き合い、やりとりすることを、インゴルドは“応答”と表現しましたが、何かの気づきを得たい人にはそのやり方のほうがが向いているはずです。ただし、スピードは遅く、どこに行くかわからないという不安もあり、説明責任が求められる現代社会で周囲に理解してもらうのは難しいかもしれません。
それでも、「散歩」的な態度ではないと見えない景色やわからないことがあるという事実、そしてその価値はちゃんとアウトプットにもつながることやきちんと活かされうることを多くの人にわかっていただきたいですね。
梅崎:理想主義的かもしれませんが、社会はあと一歩のところまで来ているという期待感があります。ソロキャンプが流行ったり、散歩もののテレビ番組の人気があったり、みんなその価値に気づき始めているのではないでしょうか。
ただし、「個人にとっての価値」は理解されても、産業社会や企業活動にとってもプラスになることへの理解は追いついていないかもしれません。ワーケーションを取り入れる企業も出てきましたが、本当は自然や環境との応答をして、参与観察モードに入って、そこから戻ってくるとすごく発想も豊かになる。このダイナミックな動きが評価されるべきではないかと。しかし、実際に、気分転換とかストレス発散程度に捉えられている印象です。
比嘉:仕事のモードとプライベートの時間における自分のあり方みたいなものを、どこかで切り分けてしまっているのかもしれません。
そこを接続し直せば、解消することも多いんじゃないかと私は思っていて、ワーク・ライフ・バランスという言葉で切り分けて考えるのではなくて、ライフの中に仕事をしている時間があるし、すべてを地続きのものとして捉えなおすことで開ける視点があるんじゃないかと考えています。
VUCAの時代、柔軟に対応するために必要な「察知する身体性」
梅崎:江戸時代の農政家の二宮金次郎は、農作物(ナス)の味で飢饉の予測をしたそうです。見事な身体知です。察知する能力が長けていたということですね。企業活動に当てはめれば、儲けのシステムができあがったものをコツコツ運営していくのがオペレーションだとすると、最近はオペレーションに適応している人材ばかりが増えているようで、察知する身体性の欠如が心配になってきます。
というのも、AIによって知的労働の標準化が進めば、大半の仕事は機械に置き換わってしまうわけです。人間は身体的な知性が求められる仕事にシフトしていかないと、失業してしまうことになります。
比嘉:不確実性が高く将来の予測が難しいVUCAの時代に、未来を先読みしてリスクを下げる動きをするよりは、何かが起こったときに、柔軟に対応できるようにしておくことのほうが最終的には強いのではないかと思います。
それができるのは、インゴルドが指摘するように、私たちが周りをきちんと見ながら、“徒歩”で進もうとするからですよね。不確実なものに対応していくには、普段は見落としがちな周囲のものごとに注意を払って、何かが起きたときに即座にに応答できるような身体やそういった身構えを作っておくことが必要ではないかと思います。
梅崎:この対談企画では、これまでさまざまな専門家をお招きして、これからのキャリアのあり方、考え方についてご意見をお聞きしてきました。世界のキャリア論は、キャリアを多角的・包括的に捉えようとする「キャリアエコシステム」や「サステナブルキャリア」といった第4次キャリア論に移行しているのですが、その本質を誰も捕まえきれてないのではないかという課題を感じていました。キャリア論とは違った専門家との対話を通じて何かヒントが得られないかと考えていました。
多様なネットワークをもち越境していくこと、「負荷ありし自己」を認識すること、不確実性をダイレクトに受け止めてクリエイティビティを向上させること、世界と応答できる身体性を取り戻すこと、みなさんが指摘されたことは実は共通しているのではないかと思います。
ビジネス社会においては、個人による合理的計画性の重要性や自律が強調されて、キャリアに対する不安が強化され過ぎているように感じます。このループを解くヒントを先生方との対話の中で見つけていきたいと思います。

梅崎 修(うめざき おさむ)
法政大学キャリアデザイン学部教授
マイナビキャリアリサーチLab特任研究顧問
1970年生まれ。大阪大学大学院経済学研究科博士課程修了(経済学博士)。2002年から法政大学キャリアデザイン学部に在職。専攻分野は労働経済学、人的資源管理論、オーラルヒストリー(口述史)。人材マネジメントやキャリア形成等に関しての豊富で幅広い調査研究活動を背景に、新卒採用、就職活動、キャリア教育などの分野で日々新たな知見を発信し続けている。主著『「仕事映画」に学ぶキャリアデザイン(共著)』『大学生の学びとキャリア―入学前から卒業後までの継続調査の分析(共著)』『大学生の内定獲得(共著)』『学生と企業のマッチング(共著)』等。
比嘉 夏子(ひが なつこ)
合同会社メッシュワーク共同創業者
山梨県立大学特任准教授
1979年生まれ。京都大学人間・環境学研究科博士課程修了(人間・環境学博士)。専門は人類学。ポリネシア島嶼社会の経済実践や日常的相互行為について継続的なフィールドワークを行う一方で、より実践的な人類学のありかたを模索し、メッシュワークを設立。人類学的なアプローチと認識のプロセスを多様な現場に取り込むことで、きめ細かな他者理解の方法を模索し、多くの人々に拓かれた社会の実現を目指す。著書に『贈与とふるまいの人類学―トンガ王国の〈経済〉実践』(単著、京都大学学術出版会)『地道に取り組むイノベーション―人類学者と制度経済学者がみた現場』(共編著、ナカニシヤ出版)等。