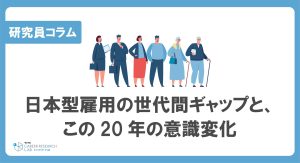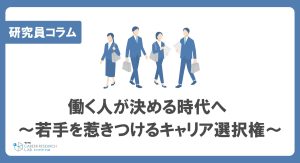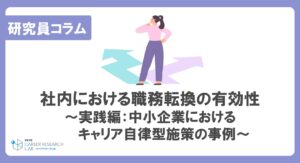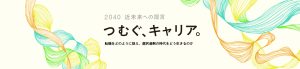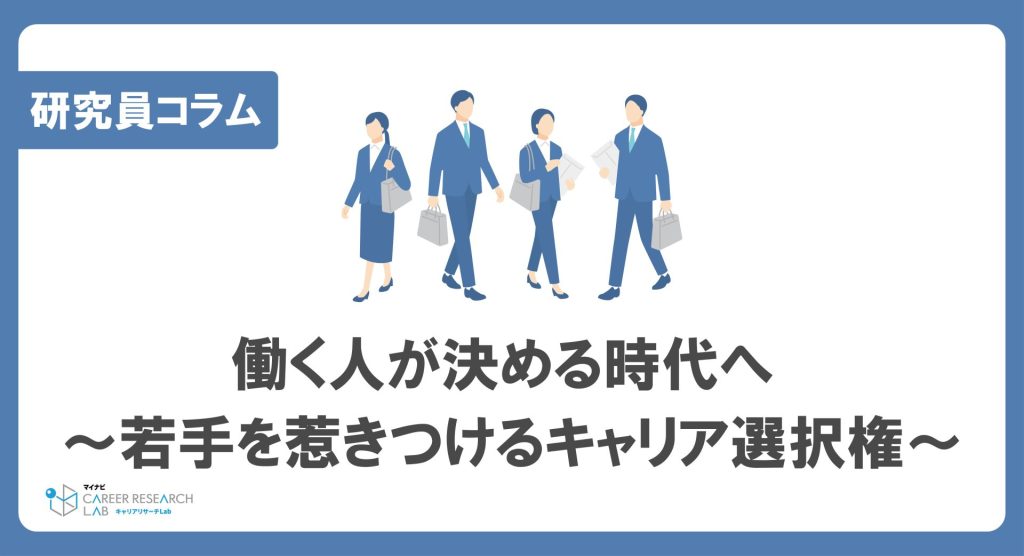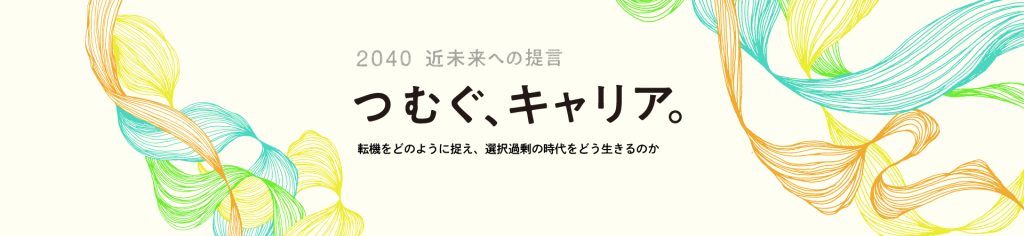人生100年時代に注目される「キャリアオーナーシップ」。企業が取り組むメリットは?
昨今、先行きが不透明なVUCA時代となっているが、日本では人生100年時代による職業人生の長期化も進み、個人が自律的にキャリア形成に取り組む「キャリアオーナーシップ」が注目されている。
働く個人が主体的にキャリアを考えていくことを指す言葉ではあるが、企業が従業員のキャリアオーナーシップを支援する取り組みを行うことも重要だ。本記事では、企業の視点から、従業員のキャリアオーナーシップを促すメリットやその方法について解説する。
目次 [もっと見る]
キャリアオーナーシップとは
キャリアオーナーシップとは、働く個人が自身のキャリア形成に主体的に取り組んでいくことを指す。2018年に経済産業省が公表している報告書ではさらに詳しく、以下のように説明されている。
個人一人ひとりが「自らのキャリアはどうありたいか、如何に自己実現したいか」を意識し、納得のいくキャリアを築くための行動をとっていくこと
経済産業省「我が国産業における人材力強化に向けた研究会報告書」
従来の企業主導のキャリア形成とは異なり、従業員が自身でキャリアの方向性を決定して必要なスキルや経験に向けて取り組むことが重視されているのだ。
個人のキャリアオーナーシップと企業の関わり
しかし、だからといって企業が個人のキャリア形成に関わらないということではない。前述の報告書では、キャリアオーナーシップへの企業の関わり方について、以下のように指摘している。
「キャリアオーナーシップ」を持つ個人は、主体性を向上させ、自らの「持ち札」を増やすことでキャリアを切りひらいていく。一方で、企業や組織は、効果的な人材確保を通じて多様な人材が活躍する場を提供するプラットフォームとなることではじめて成長し続けることが可能になる。
経済産業省「我が国産業における人材力強化に向けた研究会報告書」
働く個人の考えも多様化しているなか、企業が従業員にどのようにキャリアプランの設計を促し、それぞれが描いたプランを実現できる環境をどのように整え、後押ししていくかということも重要になっているのだ。
キャリアオーナーシップの重要度が増している背景
ではなぜ、昨今このようにキャリアオーナーシップの重要性が叫ばれているのか。この背景には、労働市場や価値観の変化がある。
職業人生の長期化と日本型雇用の変化
人生100年時代の到来によって職業人生は長くなりながらも、日本では終身雇用や年功序列といった従来の就業スタイルが限界を迎えている。そのため、従業員は企業にキャリア開発を任せるのではなく、自分自身で長期的なキャリアビジョンを持って自律的にキャリア形成に取り組んでいくことが求められている。
「終身雇用」や「年功序列」など、日本型雇用への働き手の意識の変化や自律的なキャリア観への印象については下記のコラムでも語られているため、参考にしてほしい。
働き方やキャリアパスの多様化
また、働き方やキャリアパスが多様化していることも大きな要素の一つだ。働く人のライフキャリアが画一的ではなくなってきた昨今において、働く個人は自分自身で理想のライフキャリアを考え、そのプランにあった働き方やキャリアパスなどを選択していくことが必要になっているのだ。
ESG投資の広まり
企業の視点では、ESG投資の拡大もキャリアオーナーシップに取り組む必要性が増している理由の一つだ。ESGは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)の頭文字をとった造語で、ESG投資は、これらを考慮して行う投資のことである。企業はSocial(社会)の観点で人的資本の最大化を目指すうえで、従業員の自律的なキャリア形成を促進することが求められているのだ。
企業が従業員のキャリアオーナーシップを促すメリット
これらの社会的な変化によってキャリアオーナーシップの重要性が高まっていることがわかったが、実際に企業が従業員にこれを促すことにはどのような効果があるのだろうか。次は企業が従業員のキャリアオーナーシップを支援することによるメリットを見ていく。
生産性や業績の向上
従業員が自らのキャリアを主体的に考えることによって、将来の目標に向かって計画的に行動するようになる。自身のキャリアビジョンに向けてスキルや知識を積極的に習得するようになることで職場でのパフォーマンスが向上すると、企業としての生産性の向上や業績向上が期待できる。
従業員のモチベーション向上
従業員が自らのキャリアを考え、自身の目指すキャリアビジョンが明確になることで、目の前の業務と、自身のキャリアのロードマップが結びつき、業務へのモチベーション向上も見込める。モチベーション向上によって業務により主体性を持って取り組むことができるようになることで、成果につながりやすく、その成功体験がさらなるモチベーション向上につながることも期待できるだろう。
従業員の定着率向上
従業員が自らのキャリアプランについて長期的な視点で考える機会を持ち、キャリアを重ねていくことで、離職につながりやすい「キャリアの不透明さ」がなくなり、離職も防止できる。また、従業員が自らのキャリアに対する責任感を持ち、企業に対する満足度や忠誠心が高まることも定着率向上につながるだろう。
従業員にキャリアオーナーシップを促す方法
このようなメリットを持つキャリアオーナーシップを従業員に促すためには、企業側のサポート体制が重要だ。ここからはいくつかの方法を紹介していく。
キャリアプランを考える機会の提供
従業員がキャリアオーナーシップを持つために、もっとも始めやすいサポートはキャリアプランについて考える機会の提供だ。たとえば、キャリア開発プログラムやメンター制度を導入することで、社員が自らのキャリアを積極的に管理できるよう支援することができる。その際は、画一的なキャリアプランを提示するだけではなく、一人ひとりが理想とするキャリアをデザインできるような形にすることも重要だ。
トレーニングと教育
従業員が自身のキャリアのロードマップを描けても、それに必要なスキル等を学んでいける環境がないと、実現しづらくなってしまう。そのため、企業は従業員にとって必要なスキルや知識を習得できるよう、定期的なトレーニングや教育プログラムを提供することも重要である。
これに参加してスキルアップしていくことにより、従業員は自己成長を実感し、さらにキャリアオーナーシップを持って自身の望むキャリアを実現していく意欲の向上にもつながる。
幅広いキャリアの選択肢の用意
従業員が自らの望むキャリアビジョンに向けてキャリア開発に取り組めるよう、ジョブチェンジやキャリアアップに主体的に挑戦できる制度や機会を用意しておくことも重要だ。たとえば、社内公募制度や社内FA制度、副業可能な環境整備など、企業主導ではなく自身の意思やタイミングでキャリア開発できる制度が考えられる。
また、社会人インターンシップやプロボノの受け入れなども、従業員への刺激や気づきにつながり、その後のキャリア形成によい影響を与えることがある。
「プロボノ」については、以下のシリーズにて有用性や実践例を紹介しているため、そちらも参考にしてほしい。
キャリアオーナーシップに関する参考記事
マイナビキャリアリサーチLabでは、キャリアオーナーシップやキャリア自律等に関する記事をほかにも公開している。ここからはそのような記事を紹介する。
キャリアオーナーシップ人材の育成に関する企業事例
キャリアオーナーシップを育成し、働き甲斐のある組織づくりを実現している企業のインタビューは下記を参照してほしい。
シリーズ企画:ミドルシニアのキャリア形成
以下のシリーズでは、キャリア自律の意識や仕事へのモチベーションがほかの世代と比較して低いと言われる50代も含まれる「ミドルシニア」のキャリア形成について各企業の取り組みや課題について特集している。

自律的なキャリア形成を可能にすることの有用性と施策
下記2つのコラムでは、従業員が自らの働き方やキャリアを選択できる環境や複線的なキャリアルートを描ける環境をつくることの有用性と、具体的な施策例について紹介している。
選択過剰の時代における、キャリアのつむぎ方
本コラムで述べてきたように、キャリアが多様化し、社会情勢も不確実な時代に自らの転機をどのように捉え、どう生きるべきかについて、キャリアリサーチLabでは「つむぐキャリア」という考え方を提示している。
「自律的なキャリア形成」という概念への限界や捉え方の提案がされている専門家対談や、つむぐキャリアを実践している個人に対するインタビューもあるため、参考にしてほしい。
まとめ
キャリアオーナーシップは、急速に変化する現代のビジネスパーソンにとって、自身の望む職業人生を歩んでいくうえで不可欠な概念であると同時に、企業にとっても、従業員のモチベーション向上や企業としての生産性向上を目指すうえで欠かせない。
企業が主導してきたキャリア形成と異なり、従業員が望むキャリアを叶える環境の整備を検討することは、従業員が多様化しているなかで容易ではない。しかし、従業員がそれぞれの希望するキャリアビジョンに向けて主体的に業務に取り組み、自らキャリアアップに取り組むことはモチベーションの向上にもパフォーマンスの最大化にもつながるはずだ。