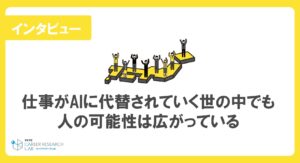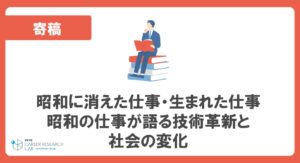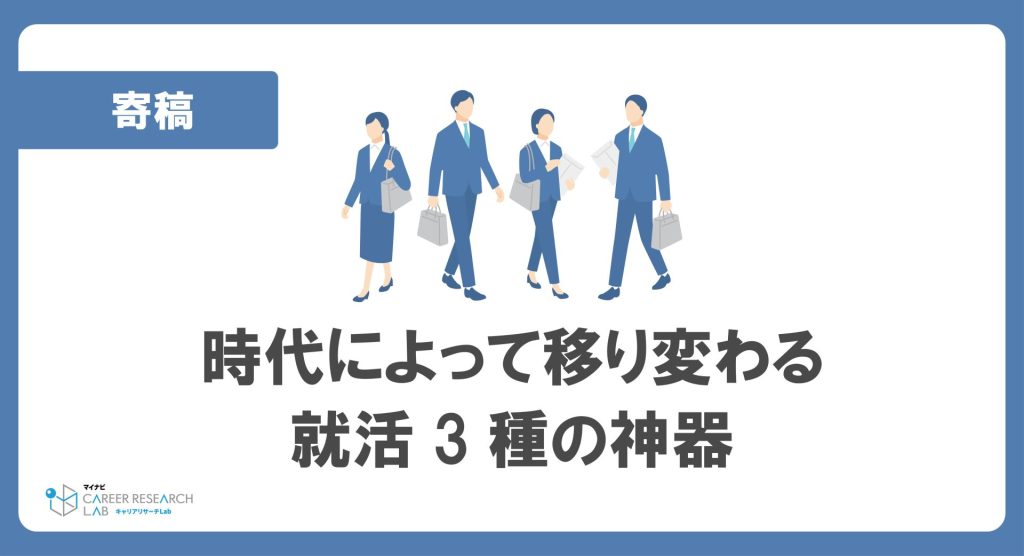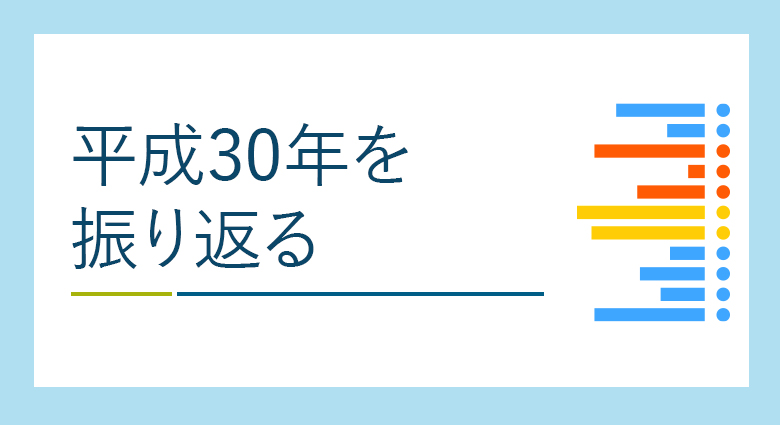
国勢調査からみる「平成になくなった・誕生した職業」!影響を与えた時代の変化とは?ー大正大学地域構想研究所 主任研究員 中島ゆき氏
約62年間続いた昭和に比べて、その半分しかない平成の30年間。実は、この期間において、さまざまな職業がなくなり、一方で新たな職業が誕生しています。それだけ社会がめまぐるしい速さで変化し、かつ複雑化していることが読み取れます。
その職業と時代の変遷を知るために、5年に1度実施されている国勢調査をもとに職業の移り変わりを追いかけているのが、大正大学地域構想研究所の中島ゆき主任研究員です。平成から令和の転換点であり、アフターコロナの転換点をみれる直前(2025年に国勢調査が実施される)というこのタイミングで、平成になくなった職業と誕生した職業、そしてその背景について伺いました。

中島 ゆき(大正大学地域構想研究所主任研究員/大正大学地域創生学部兼任講師)
法政大学修士課程修了(政策学修士)。広告業界に長く在籍し、そのうち約11年編集長職を勤める。多くの企業のプロモーション戦略やマーケティング分析に携わり、現在は、これまでの経験を生かし自治体のマーケティングやプロモーションコンサルタント業に従事。2010年より法政大学地域研究センター研究員、法政大学兼任講師、2015年より現職。専門は地域経済学、地域マーケティング。現在は、マーケティング手法の一つとして地域のポジショニング分析を基盤とし、地域資源評価、地域分析などを中心に、自治体のまちづくりコンサルタントとして各地の地域活性化プロジェクトに関わる。
目次 [もっと見る]
平成に2回にわたって職業分類の大改訂がおこなわれた
まず研究のベースにされている「国勢調査」についてお聞きします。「国勢調査」はどういったことを調べ、どういう目的に利用されているのでしょうか。
中島:国勢調査は5年に1回おこなわれ、日本に住んでいるすべての人と世帯を対象にした国のもっとも重要な統計調査です。1920年(大正9年)に初めて開始され、2020年で100周年を迎えました。国内の人口や世帯の実態を明らかにするだけではなく、日本の将来推計人口やGDPを中心に、さまざまなデータとして用いられています。
たとえば、地方交付税の算定や衆議院議員選挙区の改定などの各種法令、少子・高齢化対策や雇用対策などの行政上施策の活用。民間企業では、出店計画などのマーケティング、研究機関では将来人口・世帯数の推計のための基礎資料に役立てられています。
また国勢調査では、報酬を伴うあるいは報酬を目的とする個人の仕事として職業を分類して、その数を計算しています。この職業分類は、総務省が設定した職業を体系的に表示している「日本標準職業分類」がベースになっています。
「日本標準職業分類」では、今まで5回にわたって改定がおこなわれてきました。その中で、大幅改定になったのは1990年(平成2年)と、2015年(平成27年)の2回です。この2つの大改訂は、統計上の職業分類を大幅に変更しなければならず、相当な時代の変化があったことが読み取れます。
IT化により違う職種あるいは機械に代用され、職業がなくなっていった
「平成になくなった職業」とは、どういう基準で選ばれたのでしょうか。
中島:今回説明する「平成になくなった職業(以下、なくなった職業)」の定義は、1990年(平成2年)にあった職業が2015年(平成27年)の大改訂によって職業分類から名前が消えてしまったことを指しています。
その際、大きく2つの観点があります。ベースにしている「日本標準職業分類」は、大分類、中分類、小分類、そして例示に分かれていて、このうちの小分類自体がなくなってしまった職業を反映しています。これを「廃止」としています。
この場合、分類から職業がなくなっただけなので、どちらかというと他の分類に統合されてしまったケースが多いです。もう1つは、職業自体の名前がなくなった場合です。これを「削除」としています。これは職業分類に出す意味がないくらい人数が減ってしまった職業が該当します。
実は、この2度の大幅改定により、過去からのデータが時系列で追えなくなりました。以前の職業分類ではAというカテゴリーだったのが、改訂後にはBに移ってしまったり、あるいは職業名称が変わったりしたわけです。2010年(平成22年)からは時系列で追えるようになっていますが、それ以前については、分類や名称が変わった職業を私が手作業で調べて、反映しています。
平成になくなった職業とは
「なくなった職業」とは、具体的にどういう仕事があるでしょうか。
中島:「なくなった職業」は、次の表のとおりになります。
| 平成2年国勢調査(存在していた職業) | 平成27年国勢調査の分類 |
|---|---|
| (旧小分類の廃止) ・速記者 ・タイピスト ・ワードプロセッサ操作員 | ・速記者→他に分類されない専門的職業従事者の例示に移動 ・タイピスト→廃止 ・ワードプロセッサ操作員→廃止 |
| ・速記者学校講師 ・タイピスト学校講師 | 削除 |
| ・ワードプロセッサ操作員 ・タイピスト | 削除 |
| (旧小分類の廃止) ・キーパンチャー | ・データ・エントリー装置操作員の例示へ移動 |
| (旧小分類の廃止) ・芸者 ・ダンサー | 廃止 |
| ・声色師 ・奇術師 ・あやつり人形師 ・腹話術師 ・ボードビリアン ・曲芸師 | 削除 |
| ・キャバレーのレジスター係 | 削除 |
| ・預貯金集金人 ・保険料集金人 | 削除 |
| ・場立人 ・才取人 | 削除 |
| ・注文取り | 削除 |
| ・呼売人 ・ミシン販売員 | 削除 |
| ・絹織物買継人 ・牛馬仲介人 ・雑穀仲介人 ・電話売買仲介人 | 削除 |
| ・書生 ・留守番 | 削除 |
| (旧小分類の廃止) ・電気・ディーゼル機関士 | ・鉄道運転従事者の例示に移動 |
代表的な職業について、補足しておきます。
速記者、ワードプロセッサー、タイピスト
中島:「速記者、ワードプロセッサー、タイピスト」などは、ワープロやタイプライターが主流だった昭和に存在していた花形職業の1つ。パソコンが普及し技術革新が進み、それらの機器が衰退したのが要因として考えられます。
預貯金集金人、保険料集金人
中島:「預貯金集金人、保険料集金人」は、今では考えられないかもしれませんが、生命保険やガス、水道などの料金を個人宅などに訪問して徴収していた人のこと。銀行振込などが当たり前になり、集金だけに人を割り当てる必要がなくなったことが背景にあります。
場立人、才取人
中島:「場立人、才取人」という職業もなくなりました。「場立人」は、証券取引所で手サインを使って株の注文を伝えていた人のこと。「才取人」とは、株の売買注文の付き合わせなどの業務をおこなっていた人のこと。どちらも、1999年(平成11年)に株券売買の立会場が閉鎖されたのを機に、なくなった職業です。
書生、留守番
中島:個人的に、驚いたのが「書生、留守番」という職業です。1997年(平成9年)まで、この職業の名称が例示として記載されていました。夏目漱石の小説『吾輩は猫である』『こころ』などの代表作によく出てきたので、明治〜大正時代の職業だと思っていましたが、平成の初期まで、一定数の人がいたようです。
ただ、削除されるまでは「その他の家庭生活支援サービス職業従事者」の小分類にあったので、「家事手伝い」として区分されていました。「書生」について詳しく調べてみると、「他人の家に住み込みで雑用などを任される学生のこと」と記されています。いかにして報酬を得ていたのか、詳細な調査はおこなっていませんが、現在も職業の名前を変えて、存在するかもしれません。
平成になくなった職業に共通するものとは
「なくなった職業」に共通する時代背景はありますか。
中島:「キャバレーのレジスター係」「絹織物買継人」「牛馬仲介人」「雑穀仲介人」「電話売買仲介人」のように、時代の変化によりなくなってしまった職業というのは、一定数存在します。
その一方で、ITの発展により、その職種が担っていた役割が形を変え、他の職業やITに代用されていったケースもあります。それがこの「なくなった職業」で共通する背景だと考えています。「預貯金集金人、保険料集金人」は、銀行振込になり、「ワードプロセッサー・タイピスト」は、ツールがワープロ・タイプライターからパソコンに代わり「キーパンチャー」という職業に代替されていきました。
「キーパンチャー」もルーチンワーク化されていけば、AIやRPA(ロボットによる業務自動化)が導入され、いずれはなくなる職業になる可能性もあります。
平成に誕生した職業とは
平成に「誕生した職業」についてはいかがでしょうか。まずは、こちらも定義について教えてください。
中島:平成に「誕生した職業」は、1990年(平成2年)と比較して、2015年(平成27年)の大改訂から新たに追加された職業と定義しています。実は、国勢調査の職業分類は、「日本標準職業分類」をベースしていますが、小分類については若干異なります。
たとえば、「日本標準職業分類」だと「個人教師」となっている小分類が、国勢調査の場合では、「個人教師(音楽)」「個人教師(舞踊,俳優,演出,演芸)」「個人教師(スポーツ)」「個人教師(学習指導)」と細かく表示しています。国勢調査では、調査対象者一人ひとりに対して職業を細かく聞いているので、リアルな現状を表すことができるのが特徴です。
「ITによる技術革新」「法改正」「個人ユースの拡大」が新たな職業誕生に影響
時代背景などを考慮した場合、平成に「誕生した職業」にはどういう傾向があり、どのような職業が生まれているのでしょうか 。
| 新しく誕生した職業 | 同職業が該当する小分類(平成27年国勢調査) |
|---|---|
| ・情報ストラテジスト ・システムコンサルタント ・ビジネスストラテジスト ・ISアナリスト | ・システムコンサルタント |
| ・ITサービスマネージャ ・システム保守技術者 ・サーバー管理者 ・情報セキュリティ技術者 | ・システム運用管理者 |
| ・情報処理プロジェクトマネージャ | ・システム運用管理者 |
| ・心理カウンセラー(医療施設) | ・他に分類されない保険医療従事者 |
| ・心理カウンセラー(福祉) | ・その他の社会福祉専門職業従事者 |
| ・金融商品開発者 ・金融ストラテジスト ・保険商品開発者 | ・金融・保険専門職業従事者 |
| ・テクニカルライター | ・記者,編集者 |
| ・苦情受付事務員(電話以外によるもの) | ・その他の一般事務従事者 |
| ・調査員(統計調査員・世論調査員・市場調査員) | ・調査員 |
| ・リサイクルショップ店主 ・リサイクルショップ店員 | ・小売店主・店長 ・販売店員 |
| ・ハウスクリーニング | ・ハウスクリーニング職 |
| ・ネイリスト | ・美容サービス従事者(美容師を除く) |
| ・レンタカーカウンター係員 | ・物品賃貸人 |
| ・ボディガード ・刑事施設警備員 | ・警備員 |
| ・自動販売機商品補充員 | ・配達員 |
中島:「誕生した職業」については、おもに3つの時代背景が影響しています。
インターネットを中心としたITの技術革新
中島:1つ目は、「インターネットを中心としたITの技術革新」です。1990年代にWindows95の登場によりPCやインターネットが普及し、一般の人々がWebサイトに簡単にアクセスできるようになってきました。
ビジネスにおいても、生産性向上や業務改善、事業戦略などにITシステム(ネットワーク含む)が欠かせない技術となり、ITを扱うサービスが爆発的に市場に導入されていきました。市場の成長に伴い、ITに関連する職業も急速に増え、今や幅広い分野で専門職が必要とされる時代となっています。
こうした背景によって「情報ストラテジスト、システムコンサルタント」「ITサービスマネージャ、サーバ管理者」「情報処理プロジェクトマネージャ」など新たな職種が誕生したと考えられます。
法改正による業界の整備
中島:2つ目は、「法改正による業界整備」です。法改正は、多くの場合、業界の安全性や効率性の向上、社会的な問題の解決を目的としています。これにより、従来の職務や業務が細分化され、各分野でより高度な専門性を持った職業が必要とされるようになります。
「心理カウンセラー職(医療施設・福祉)」は認知度の高い仕事ですが、実はこの時まで日本では、心理職の国家資格が存在していませんでした。それが2011年(平成23年)に東日本大震災により全国的に不安が蔓延し、心のケアの重要性が再認識され、一定の基準・スキルの明確化が社会的に求められるようになりました。そこで2018年(平成30年)8月に日本で初めての心理職の国家資格「公認心理師」が誕生したのです。
医療現場では、1986年(昭和61年)から「臨床心理技術者(または臨床心理士)」が心理専門職として認知され活躍し、長きにわたってニーズがあったようです。その他の分野では、1992年(平成4年)には旧労働省が産業カウンセラー資格を技能審査資格として認定し、公的機関や民間企業などで導入されるようになりました。2019年(平成31年)には文部科学省がスクールカウンセラーを全国に配置。これらの広がりにより、心理カウンセラーはなりたい仕事の1つとなりました。平成生まれの仕事の代表格といえそうです。
また、「金融商品開発者」「金融ストラテジスト」「保険商品開発者」の誕生は、金融関連のシステム改革や法制度の改正が影響しています。1990年代に金融ビッグバン(金融システム改革プラン)が内閣から提唱され、金融市場(保険含む)の規制が大きく緩和されました。さらに、2001年(平成13年)にはiDECO(個人型確定拠出年金)がスタートし、個人による資産運用も普及していったのです。これにより、金融や保険の商品づくりや、投資の方針提案をおこなうような人が必要になってきました。
「リサイクルショップ店主・店員」は、2015年(平成27年)特定家庭用機器再 商品化法(家電リサイクル法)施行など、リサイクル関連法の影響を大きく受けています。この法律により家電を廃棄処分する際の費用として数千円かかるようになり、個人消費者は処分費用がかからないようにするためにリサイクルショップのニーズが増えていきました。
さらにライフスタイルや消費行動の変化により、リサイクルへの関心が高まり、大型家電だけでなく、衣類やゲーム、パソコンなど対象製品が広がっていきました。今やリサイクル・リユース市場は毎年右肩上がりで伸びています。
個人ユースの拡大
中島:3つ目は、「個人ユースの拡大」です。「ハウスクリーニング」は、清掃のプロが専用の機材・洗剤を使って、個人の掃除では行き届かない汚れを落とすサービスのことで、自宅全体だけでなく、お風呂場、トイレ、エアコン、キッチンのレンジフードなど一部分の清掃も含まれます。高齢化や単身層・共働きの増加により、家事の外注化が増えてきたことが予想されます。平成に誕生し、今後も増える職業の1つです。
「ネイリスト」も、個人ユースの拡大により誕生した職業です。1990年代から2000年代にコギャルブームが到来したことで、ネイルアートが若者を中心に身近になりました。次第に鮮やかな色づかいやパールやストーンを使ったデコパーツが人気になり、ネイルサロンも増え、ネイリストが誕生したのです。
今回は、中島ゆき主任研究員に平成に「なくなった職業」「新たに誕生した職業」について解説していただきました。後編は、直近の就業者が増えている職業、令和における新たな職業の広がり、AIが普及する中での人間がおこなう可能性について、伺います。