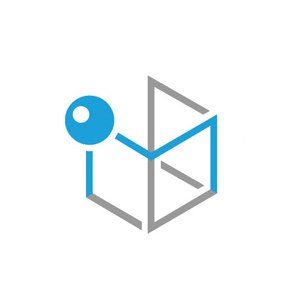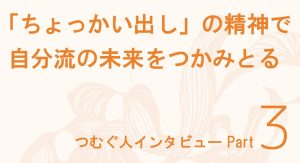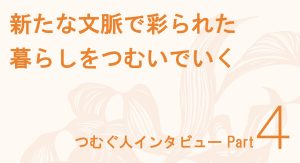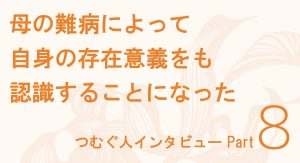【つむぐ人】自ら築いた新しい故郷で、理想を叶えるために、調剤薬局を開設するという道を選んだ。
『つむぐ、キャリア』では、多様化する過剰な選択肢から選び続けていると、選択結果のあいだに矛盾が生じたり、相容れないものを選んでいたり、これらを新しい文脈で意味づけて、撚り合わせ、調和させることを「つむぐ」と表現しました。
そこで、「つむぐ、キャリア」を実践している方々を「つむぐ人」と称し、その方々にインタビューを行い、自らのライフキャリアとビジネスキャリアをどのようにつむいできたのかをお聞きします。また、今後各インタビューに共通して現れた要素などを専門家の先生方との対談とあわせ、「つむぐ、キャリア」という概念に必要な要素などを具体化できればと考えています。
目次

つむぐ人 プロフィール
楠原 健司(くすはらけんじ)
1974年生まれ。福岡県の薬科大学を卒業後、薬剤師として上天草市、名古屋市、人吉市にて勤務した後、2009年に独立。自ら開設した薬局経営に取り組みながら、管理薬剤師として調剤業務、在宅訪問業務、かかりつけ薬局業務、学校薬剤師業務に携わる。株式会社Camphor 代表取締役。水俣芦北薬剤師会副会長、熊本県薬剤師会薬局委員・職能委員・介護認定審査委員。熊本県薬物乱用防止指導員。
薬剤師への道、それはリスタートだった
楠原さんは、大阪府阪南市の出身。高校を卒業し、そのまま大阪で2年目の浪人生活を過ごすことになったが、それまで自身の将来について深く考えることはなかったと言う。20歳を迎える頃になって初めて、将来について真剣に考えはじめたのだと、当時を振り返ってくれた。
楠原:「ちょうどバブルが弾けて、その余波が広がりはじめた頃だったんですね。景気も後退していくなかで、このまま漠然と大学に進学しても、それだけで思うような未来が描けるわけじゃないな、と。自分が将来、どう生きていくのか、確かな目標を定めた上で、進学先を選ぼうと考えました。
これから少子高齢化が進むだろうから、医療・看護の時代かなと思って、近くの本屋さんで、医学部への進学について調べてみると、学力も遠く及ばないし学費も桁違い。これは無理やわと思っていると、その棚の近くに薬学部の本が置いてありました。実はその時まで、薬剤師という仕事について、何も知らなかったんです。
当時は今ほど薬剤師は多くなく、医薬分業も進んでいなかった。薬学部の本を手に取って僕がイメージしたのは、近所の薬屋さん。薬局で風邪薬などを売るのかなという仕事でした。店を訪ねてくれた年配の人たちとのんびり話をしながら、薬の相談に乗って…と。これなら、僕の性格にも合ってるし、やりがいがあるかなと思って、薬学というものに初めて興味を持ちました。
もちろん、薬剤師になるとどのくらいの給料がもらえるのかも、ちゃんと調べましたよ。意外に高かったんです。学費も高いけど、返せんこともないやろうと思って…」
この時、楠原さんは、もう一つの点にも着目していた。
楠原:「それは、薬剤師になるには、国家試験に合格する必要があるということです。大学で勉強するだけでは薬剤師にはなれない。でも、そのハードルを乗り越えたなら、高学歴の人たちと同じスタートラインに立てる。
これまでは目的もなしに、遊んでばかりの人生だったけど、薬剤師を目指すことで、リスタートすることができると考えて、決断しました」
薬剤師としての、“出稼ぎ“人生?の幕開け
福岡県の薬科大学への入学を決めて、薬剤師への新たなスタートラインに立った楠原さん。初めての福岡での生活にも、次第に慣れていく。学業に勤しみ、学友との交流機会も増え、充実した学生生活を送ることになった。そして、いよいよ薬剤師の国家資格を得て、薬剤師として歩みはじめることに。入学当初、楠原さんは薬剤師の資格を得た後、地元の大阪に帰ろうと考えていたが、それがままならない現実に直面することになる。
楠原:「薬学部に進むにあたって、両親には、学費を出してもらえるよう頼み込みました。薬剤師になって稼げるようになったら、きちんと返すという約束でした。薬剤師の資格によって、さまざまなしごとに就けるようになります。たとえば製薬会社や保健所の薬剤師だったり、県庁や市役所などの薬剤師、病院の薬剤師、そして調剤薬局の薬剤師など、さまざまな就業先があります。
当然、もらえる給料も担当する仕事や就業先によって異なり、働く地域によっても差があることがわかってきます。当時は、薬剤師が多い都会では給料は低く抑えられ、高齢者が多く、薬剤師不足を抱える地方のほうが厚遇されていました。
そこで、親に借りていたお金を早期に返すために、“出稼ぎ”の道を選ぶことになります。つまり大阪に帰って薬剤師になるよりも、九州に残って調剤薬局に就職しよう、大阪に帰るのは親への返済にある程度の目処が立ってからでも遅くはない、と考えたわけです」
天草の大自然と、あったかい人々に囲まれて

こうして九州に残ることを決めた楠原さんが、最初の就職先として選んだのは、熊本県上天草市にある調剤薬局だった。4年余りを過ごした上天草の魅力について、楠原さんは、こう語った。
楠原:「喫茶店もないような田舎町なのですが、とにかく海がきれいなんです。薬局の患者さんが漁師さんだったので船に乗せていただき、夜の海に連れて行ってもらったのですが、珊瑚がサーチライトに照らされて、艶やかなピンクや紫色に輝いている。魚たちも夜は眠っているのか、銛のひと突きで捕れちゃうし、岩の下に潜った蛸も手づかみできる。
いちばん感動したのは、“ウミホタル”ですね。天草では夜光虫というプランクトンをそう呼ぶのですが、海面を波立たせると、波紋が広がるように美しく光って、神々しいほどに。それに、休みの日などに昼から海に出かけると、マリンビーチが貸し切り状態。そのまま夕焼けを眺めたり、友だちと海鮮バーベキューをしたりして…いやほんま楽しかったなあ」
上天草の雄大な自然とその繊細な美しさについて、楠原さんの話は尽きそうにない。だが、上天草が楠原さんをとりこにしたのは、自然の美しさだけではなかった。
楠原:「上天草は、気候も温暖で暮らしやすい町でした。けれど、それ以上にあったかいのが、この町に暮らす人たちです。薬局で出会って知り合いになるのは、おじいちゃんやおばあちゃんたちばっかりなのですが、みんな優しいんですよ。しょっちゅう薬局を訪ねてくれて、山のような野菜や魚を持ってきて、食べてなっせ、食べてなっせと…」

田舎暮らしに憧れて、地方への移住を考える方も多いようだが、なかには閉鎖的なところもあって、人間関係を築くまでに時間がかかったり、なかなか溶け込めないということもあるようだ。楠原さんが上天草に溶け込めたのは、上天草の人々の温かさはもちろんだが、薬剤師という頼りにされる職業であったことに加えて、20代で上天草に入り、何事にも好奇心旺盛で精力的に取り組み、周囲の人たちとの交流を楽しむことができたからだろう。
楠原:「独身だったので、夜になると釣りに出かけたり、バーベキューなどで知り合った仲間と呑みに行ったり。自然と友だちも増えていきました」
薬剤師という、一本の軸がある人生
上天草での暮らしは、とても楽しく、仕事の面では患者のみなさまに恵まれ、プライベートでも多くの友人たちに恵まれて、何の不満も感じなかったという楠原さんだったが、生まれ故郷である大阪への想いを断ち切ることはできず、悩んだ末に大阪に戻ることを決めたそうだ。

楠原:「もとより、やがては大阪に戻ることを念頭に過ごしてきた4年間でした。両親の面倒をみなければならないし、多くの友人たちもいる。すごく悩んだのですが、当初の計画通り大阪に帰って、薬剤師として頑張ろうと決めたんです。それで大阪近辺で探したのですが、思うような転職先が見つからない。就業条件が良くなくて、自分一人の生活で手いっぱい。仕送りもできないような給料だったので、もう少し範囲を広げて探してみると、名古屋に好条件で雇ってくれる会社がありました。
ところが1カ月もしないうちに、その選択を後悔することになります。このまま働き続けたら身体がもたないと感じて、『天草が恋しい、天草に帰りたい』とホームシックにかかったような状態でした」
そんなタイミングで、上天草で薬剤師として働いていた友人から電話が。楠原さんが現状を伝えると「それなら熊本に戻ってこいよ」と一言。その友人は、熊本県の人吉市で働くことになったようで「一緒に行こう」と誘われたのだった。
楠原:「人吉は、上天草からは少し離れた山あいの町になりますし、そこで暮らす人々との関わりについても、物語を最初の1ページから編み直すようなもので、それなりの苦労もあるだろう、そう覚悟して臨んだ新天地での仕事でした。
それでも、この新しいチャレンジに踏み切れたのは、そこに変わらない薬剤師という仕事があるから。上天草での多くの出会いを通じて、築き上げてきた薬剤師という一本の軸を、さらに自分らしく磨き上げるために、新しい土地での経験が必要だったのかもしれません」
与えられた故郷と、つくった故郷
人吉を新たな活動拠点として再スタートを切った楠原さんには、彼の人生における大きな節目となるライフイベントが用意されていた。奥様との出会い、そして結婚だった。
楠原:「僕が一人薬剤師(※1)として着任した調剤薬局の近くの病院で受付をしていた妻と出会うことになります。不思議なものですね。あれだけ海が好きだ、釣りに行きたいと言っていた僕が、山あいの町での暮らしに喜びを感じ、寒暖差の激しい盆地の気候にも慣れて、やがて結婚し、二人の子を育て、家を建てることにもなるのですから」
※1 調剤業務や店舗運営業務を一人で担当する薬剤師
楠原さん夫婦は、結婚後、一男一女を授かり、もう一つのライフイベントである「子育て」に取りかかることになった。この頃、夫婦の間では、このイベントの舞台を、楠原さんの故郷である大阪にするのか、このまま舞台を移さずに人吉とするのかについて、話し合ったという。
楠原:「いつかは大阪に帰りたい。僕自身は、そういう想いを常に持ち続けていました。二人の子供が生まれたタイミングで、家族4人で大阪で暮らすという選択もあり得たのかもしれません。実際、妻とはそういう話もしました。
妻は生まれも育ちも人吉で、あまり外に出ることもなく過ごしてきました。そんな彼女が大阪の地で新たなコミュニティとの関係を築いていくのだとすれば、かなり大きな負荷を強いることになるでしょう。僕としては、それは避けたかったし、人吉の豊かな自然のなかで子育てをしたいという想いもありました」
こうして子育ての舞台を人吉に定めた楠原さんは、さらに念願の家づくりにも取り組み、理想の住まいを手に入れた。
楠原:「家を建てたことで、もう後戻りはできない。人吉を拠点に生きて、ここに骨を埋めるんだという覚悟ができたように思います。令和2年の7月に発生した球磨川流域豪雨災害では、そんな我が家も大きな損傷を負ってしまうのですが、川を恨むことも、この地域で暮らすことを諦めてしまうこともありませんでした」
楠原さんのなかには「薬剤師」という軸に加えて、人吉という土地を選んだという、もう一本の軸が生まれたのかもしれない。楠原さんには、大阪という両親に与えられた故郷があったが、人吉は楠原さんが自ら選んで築き上げた故郷になる。その重い選択を、家族と共有しながら、薬剤師と人吉という二つの軸が交差する人生を、つむいでいくことになった。
理想とする医療を提供するために

人吉に家を建てる少し前のことだが、楠原さんは、人吉市内のグループ薬局への転職を決断した。それまでは仕事はきついが、収入面では有利な一人薬剤師として、担当する調剤薬局の運営を任されてきた。奥様が、二人目のお子さんを宿した頃に体調を崩したが、一人薬剤師のままでは、休みをとって子供の面倒を見るわけにもいかない。このため複数の薬剤師がいる薬局に移るために転職したのだ。実は、この転職には、楠原さんにとってもう一つの意味があった。
楠原:「地域に溶け込んで調剤薬局を利用してくれる多くの患者さんと接するなかで、僕のなかに『自分だったら、こうしたい!こんなサービスを提供したい!』という、医療サービスの提供者としての理想像を思い描くようになりました。二つありまして…」
その一つは病院ではじっくりと診てもらって、薬局では素早く的確に情報を伝えること。つまり薬局ではあまり待たせない。それが楠原さんの理想だった。
楠原:「本当はゆっくりおしゃべりをしたいんですけど、必要最低限の内容を伝えたうえで、忙しい人たちやわかっている人たちにはすぐに帰ってもらって、困っている人だけに、ゆっくり時間をかけて説明する。そのために必要だと考えたのが、作業をオートメーション化することでした。
当時は、処方箋をもらったら事務員さんがレセプトコンピュータに手入力して、複数の種類の薬をパッケージ化するのも手作業でした。そこで処方箋にQRコードをつければ、データが一瞬でレセプトコンピュータに読み込まれ、同時にそのデータが自動分包機にも移行して、自動的に薬が分包されるようなシステムがあればと。
ただ、そのためには初期投資が必要で、そこに投資をしてくれる薬局の開設者を説得するにはハードルが高い。そこにフラストレーションがたまっていきました。物理的な作業は機械化して、薬剤師にしかできない薬の説明や患者さんの容体確認などに時間をかけたいというのが、僕の理想だったんです」
そして、もう一つの楠原さんの理想とする医療サービスが、フォローアップ医療だ。
楠原:「経過観察ですよね。慢性的な疾患のある患者さんとは、付き合いも長くなりますから、顔を見れば、ちょっとした体調の変化にも気づいて、薬の相談にものれる。名前や趣味、家族構成もある程度把握していますから、世間話だってできます。
こうして経時的に患者さんをフォローしていくという医療です。最近では厚生労働省でも『かかりつけ薬剤師を持ちましょう』と強く言い始めましたが、僕は当時からそういう薬剤師になりたかったんです。薬学部入学前に、なんとなく薬剤師をイメージした『近所の薬屋さん』が原点かもしれません」

そんな理想と現実のギャップを解消するために、自らが開設者となって薬局運営にあたるというのが、楠原さんが出した結論だった。薬局の開設地となったのが、人吉市から車で40分ほどの芦北町という海沿いの町だ。天草と不知火海を挟んだ対面にある地に、自らが経営する調剤薬局を開設し、理想とする医療サービスを提供するための地域密着型の薬局経営をスタートさせた。2009年の12月、楠原さんが36歳のときだった。
楠原:「思い返すと、上天草の薬局を辞して大阪に帰ると言ったときに、多くの患者さんが『辞めんといて』と言ってくださって、なかには餞別をくれたおじいちゃん、おばあちゃんもいました。せっかく心を開いて相談ができる人が見つかったのに、帰ると言ってあっさりといなくなってしまう薬剤師。
そんな患者さんの気持ちを思うと、心が痛くて。こんなことを、ずっと繰り返すわけにはいかない。やがては一つのところに居座って、その地域の方々と10年でも20年でも、お付き合いを続けていこうと思いました。そんな心の痛みが起爆剤となって、薬局開設に向かわせてくれたのだと思います。
薬局開設から14年、嬉しいことがありました。軽度認知症の患者さんがふらっと薬局に来られました。僕が『◯◯さん、どうしたのですか?』と訪ねたら、『家への帰り道がわからなくなった。でも、薬局に来たらどうにかしてくれると思って。』と。すぐにご家族に連絡をして、無事に帰宅されました。自分の仕事が誰かの支えになれる喜びを感じ、浪人時代に本屋で描いた夢が今、つむがれた気がしました。
そして現在は、こんな僕を温かく受け入れて頂いている地域の皆さん、借金をして薬学部に行かせてくれた両親に感謝しつつ、薬学的知識の研鑽と習得に努め、薬剤師として地域医療のお手伝いを末永く続けて行けたらと考えています」
楠原さんが、上天草で、人吉で、多くの患者さんや地域の人々と出会い、磨き上げてきた一本の軸。それが、薬剤師という仕事だった。そして、人吉という土地に骨を埋めるという覚悟を持って、家族とともに生きる「新しい故郷」をつくった。これが二本目の軸になる。この二つの軸が相互に交差しながら、楠原さんらしい人生というキャリア(物語)をつむいでいくことになる。