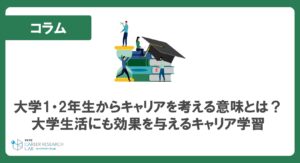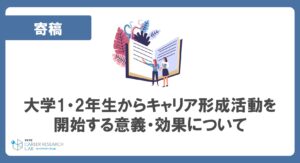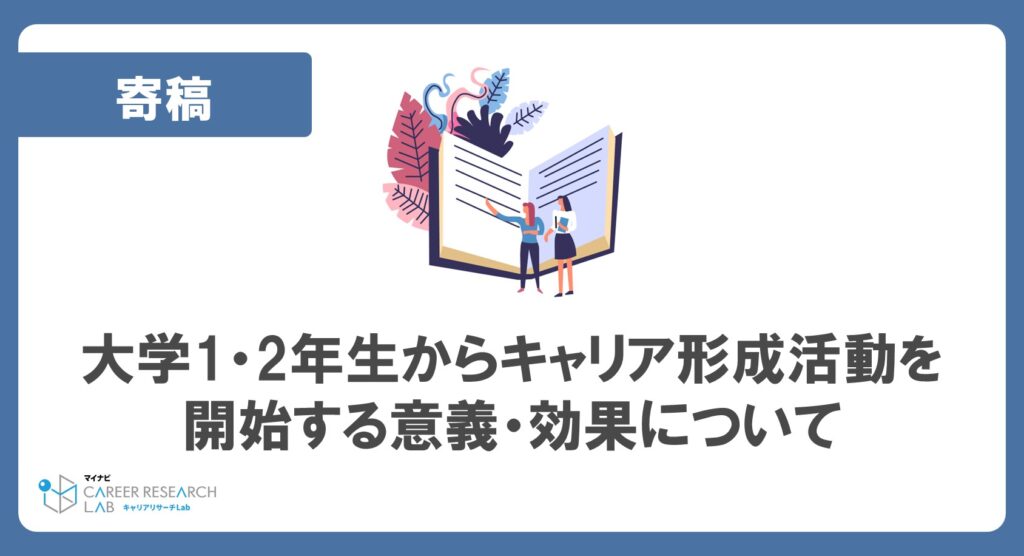大学生のキャリア学習を考える―大学での学びと就職後の活躍への影響について
昨今、大学1・2年生のころからのキャリア学習が重視され、インターンシップは定義が変更されるなど、キャリア形成活動を含む「大学生のキャリア学習」はますます重要度を増している。しかし、その一方で、この動きについて、「就活準備の早期化を促進し、学業への取り組みを阻害しているのでは」との懸念も存在している。
そこで本連載企画は、大学生のキャリア学習について、低学年からのキャリア形成活動に関するデータや企業が実施するインターンシップの事例を紹介しながら、大学生のキャリアについての学びや、職場体験などで経験を得ることの重要性や効果について見てきた。
この記事では、これまで4回にわたってお届けしてきた内容をまとめ、これからの大学生のキャリア学習と大学や企業のキャリア形成支援活動の在り方について、重要な要素を抜粋して紹介していく。
目次 [もっと見る]
第1回:大学1・2年生のキャリア学習の現状
第1回では、大学生のキャリア形成活動の中でも昨今注目を集めている、大学生低学年(大学1・2年生)のキャリア学習について、マイナビ調査をもとに現状をまとめた。以下、記事の要点をいくつかピックアップして紹介する。
大学・企業の低学年への取り組み
大学ではキャリア教育が必修となっている場合が多く、キャリア教育の開始時期もほとんどが大学2年次までのタイミングで実施開始されているなど、学生が低学年のうちからキャリアについて学ぶ機会が提供されているケースが多い。
また、企業について見ると、2024年2月調査ではすでに低学年へのキャリア教育の取り組みを行っている企業は13.4%と少ないが、必要性を感じている企業はそれよりも多く、これから検討する企業が増えることも予想される。
学生のキャリア学習状況
大学1・2年生でキャリアに関する授業やガイダンスに参加したことがある学生は例年3割ほどとなっており、企業のキャリア形成活動についても4人に1人程度の学生が低学年次に参加している。それぞれの内容としては大学ではキャリアデザインや社会人基礎力について学び、企業のキャリア形成活動では実際の職場や仕事について学んでいた。
キャリア形成活動による変化
前述のようなキャリア学習を通して得た知識や経験が活かせた場面としてもっとも多かったのは「将来の進路を考えるとき」だが、「履修する授業を選ぶとき」や「研究室・ゼミを選ぶとき」など学業における選択時にも影響していた。
キャリア観醸成によって、より将来を意識した履修選択や学習ができているのはもちろん、キャリア学習で傾聴力やコミュニケーション能力などの基礎力について学ぶことで、アルバイトや交友関係など現在の学生生活にも役立っているようである。
第2回:企業が取り組むキャリア教育(前編)
第2・3回では、「企業が取り組む大学生のキャリア教育」という視点で、株式会社DAY TO LIFEが行うインターンシップについてインタビューを行った。同社は、キャリアデザインスキルの習得をコンセプトとした、椙山女学園大学との産学連携のインターンシップで「第6回キャリアデザインプログラムアワード」の大賞を受賞している。
前編では同社の上田 勝幸さんに「キャリア教育」に着目した経緯や学生へのキャリア教育にも力を入れた理由などについてお話を伺った。以下、インタビューから要点をピックアップして紹介する。
女性の退職という課題から「キャリア教育」に注目
女性社員の離職率の高さによる人員不足という課題を解決するため、人事制度改革に取り組む中で、退職者からの「自分でキャリアを描けない」という声がポイントだと気づいたという上田さん。この背景を受け、椙山女学園大学との産学連携で、キャリア教育をベースとした自社の人事制度改革に取り組んできた。
インターンシップも採用ではなく「キャリア教育」重視で
自社の人事制度に「キャリア教育」の観点を取り入れる中、インターンシップで学生にもキャリア教育の重要性を広めていくことに。自社のインターンシップを「自社の社員採用の手段」よりも「学生のキャリアデザインスキル習得支援の場」と捉え、インターンシップに取り組んでいく。
学生が将来のキャリアを大きく描くために必要なこと
従来のインターンシップへの考え方のように、キャリアの方向性を絞り込もうとして、小さくまとまろうとしてほしくないと語った上田さん。「自ら主体的にアクションを起こす」「自分のキャリアを広げていく目線を持つ」など、インターンシップでなりたい自分を見つけられるようにするための4つの行動と4つのルールを伝えている。
第3回:企業が取り組むキャリア教育(後編)
第3回は、株式会社DAY TO LIFEへのインタビューの後編となっている。後編では、学生時代に同社のインターンシップに参加し、その後実際に入社した社員の松岡海唯さん・福嶋日奈子さんに、インターンシップへの参加による自身の変化を聞くとともに、引き続き上田勝幸さんにもお話を伺った。以下、インタビューから要点をいくつかピックアップして紹介する。
インターンシップへの参加による変化
インターンシップに参加した松岡さんはDAY TO LIFEのインターンシッププログラムを通じて、企業にこだわるのではなく、そこで自分が何をしたいのかに意識が向くようになったと話す。福嶋さんはキャリア観や、やりたいことの幅が広がり、それまでは酒造・飲料メーカーだけを志望していたが、酒造・飲料メーカーだけにこだわらなくても良いのではと気づけたという。
また、大学のゼミの選び方やアルバイトでお客さんのニーズを想像するようになるなど、二人ともインターンシップの経験を通じて学業やアルバイトなどの学生生活にも変化が見られた。
面談による自己理解の深まりと目標の明確化
DAY TO LIFEのキャリア形成支援活動においては、インターンシップのプログラムそのもの以外にも、「キャリアデザインスキル習得」をサポートするような手厚い面談も実施されており、松岡さんと福嶋さんからは、その面談による自己理解の深まりの話もあった。
面談によって自身の人生を振り返ったり、興味がある部門の社員と話す機会をもらったりしたことで、自身でも気づいていなかった興味関心や大事にしている価値観に気づくことができ、目指すべきキャリアや目標が明確化したという。
また、松岡さんは1年目の時点で簿記3級を取得し、現在も目標実現に向けた資格取得に励むなど、入社前から理想の将来像が整理されていることで、入社後も目標を意識しながら目の前の仕事やスキル取得に取り組むことができているようだった。
キャリア教育を軸としたインターンの理解浸透
再び上田さんへの質問に戻り、一般的に新卒採用の接点づくりとして実施されるインターンシップについて、採用ではなくキャリア教育を優先することをどのように社内に理解浸透させていったのか聞いた。ポイントとしては以下の3点であった。
- インターンシップの意義を経営幹部全員で議論し、認識を共有
- インターンシップを「自社の成長のヒントを得る場」「社員が成長する場」としても活用
- インターンシップに参加する社員には、「インターンシップを通して目指す社会像」を共有
インターンシップで起こる変化
DAY TO LIFEのインターンシップに参加し、自身の内面の変化と向き合って言語化し、次のアクションへつなげるという経験をした学生は学生生活に戻ってからも、大学での研究の意義やアルバイトやサークルを通じて得たものを考えるようになり、それが将来にもつながるという上田さん。そんな経験を積んだ学生は社会に出てからのギャップも乗り越えられるようになるという。
また、インターンシップに参加した社員も学生へのフィードバックを通してマネジメント力が磨かれるなど、コンピテンシーが高まり、学生からの参加後アンケートの結果も、率直なフィードバックとして参考になっているようだ。
第4回:大学1・2年生からキャリア形成活動を開始する意義と効果
第4回では、再び大学生1・2年生のキャリア形成活動に注目し、実践女子大学の初見康行氏に低学年のキャリア形成活動にはどのような価値があるのかについて解説していただいた。
「低学年からのキャリア形成活動」の意義を見出す必要性
第1回でも見てきたように、低学年向けのキャリア教育やキャリア形成支援プログラムは今後も増加していくことが予想される。大学も企業も、参加する学生も労力をかけている中で、このキャリア形成支援やキャリア教育が、従来通り3年生以降でも得られる効果をただ前倒ししているというだけではない、低学年から行う「大儀」と呼べるようなものを明確化しておくべきだろうと初見氏は指摘する。
低学年向けキャリア形成活動の効果は「学習意欲の向上」
初見氏と株式会社マイナビの共同研究から、低学年特有の効果として明らかになったのが「学習意欲の向上」だ。これまで、一部のキャリア形成活動やその早期化が大学での学習を阻害するのではないか、ということが懸念されてきた。
しかし、今回の分析結果から、キャリア形成活動には大学の学習意欲を向上させるという従来の懸念とは「逆の効果」があることが確認された。
低学年からのキャリア形成活動と入社後の活躍
また、本結果のみで断言することはできないが、低学年からキャリア形成活動を開始することが、卒業後の活躍にも影響を与える可能性が示唆される結果が見られたという。その背景には、低学年で向上した学習意欲がその後の学習活動に良い影響を与え、そこで得られた学びがさらに卒業後の活躍につながる、というポジティブな連鎖が起きていることも考えられる。
大学の学びとキャリア形成活動のサイクルを考える
初見氏は、低学年でのキャリア形成活動について、活動での経験が大学の学習に還元され、大学の学習で得られた学びが再度キャリアデザインに還元されていく、というサイクルを循環させるための枠組みを、大学・企業・行政が協力して創り上げていく必要があるのではないだろうかと指摘した。
全4回の連載を通して
今回、マイナビ調査から低学年のキャリア形成活動の状況について整理し、第2~4回は企業と専門家の視点から、大学生のキャリア教育・キャリア形成支援活動についてさまざまな示唆をいただいた。
キャリア形成活動と大学での学び
初見氏は第4回の記事にて、低学年でのキャリア形成活動と大学の学習のサイクルの循環について指摘しているが、初見氏の研究以外に、マイナビのアンケート調査でも大学生低学年でのキャリア学習が大学での学習意欲向上につながっていることが見て取れた。
また、DAY TO LIFEの若手社員の声からはインターンシップ後のゼミ活動などに変化があったという声があがるなど、大学3年次の取り組みにおいても大学生活に良い影響があったことが分かる。
このデータや例からも、大学1・2年次からのキャリア学習が大学の学習意欲や課外活動での積極性を高め、その学びを踏まえて検討・参加した企業のインターンシップ等での経験がさらに大学生活での行動にポジティブな影響を及ぼしてさらにキャリアにつながっていくという、良いサイクルが起こり得ることがイメージできるのではないだろうか。
キャリア形成活動と入社後の活躍
また、初見氏は大学1・2年生からのキャリア形成活動が就職後のワーク・エンゲージメントや在職意思にも影響を与える可能性があると指摘した。
今回インタビューした、DAY TO LIFEの二人の社員がインターンシップに参加したのは低学年次ではないが、インタビューではインターンシップの参加により、入社前から自身のキャリアについての目標が明確化し、新卒1年目でその目標に向けた資格を取得するなど、目標に向けて努力する様子がうかがえた。
配属後や研修後ではなく、入社前から目指すべきキャリアが明確化していることで、配属先の業務にも主体性が増し、スキルアップに向けた取り組みにも早くから着手できるのではないだろうか。そしてそのような、将来像をイメージするタイミングが大学1・2年次などに早まれば、それに向けた勉強をしたり、目標を意識した生活を送ったりする時間は長くなり、充分に準備した状態で就職することができそうだ。
まとめ
企業の人手不足や学生の将来への不安感の高まりなどから、企業が学生との接点を早くから持とうとしたり、学生が早くからキャリア形成活動に取り組んだりする傾向は今後も続くと考えられる。その際、大学や企業はこの動きがいたずらに学生の就職への危機感を煽り、単に就職活動を早期化させていくものにならないよう注意していく必要がある。
ただ、その点に注意して取り組んでいけば、キャリア形成活動が学生自身のキャリア観醸成だけでなく、大学での学びや活動の効果をさらに高めたり、就職後の企業へのエンゲージメントを向上させたりするなど、三方よしの状況が実現できるのではないだろうか。