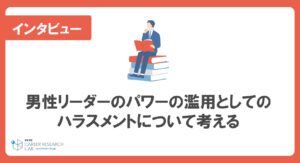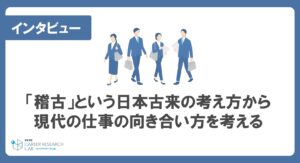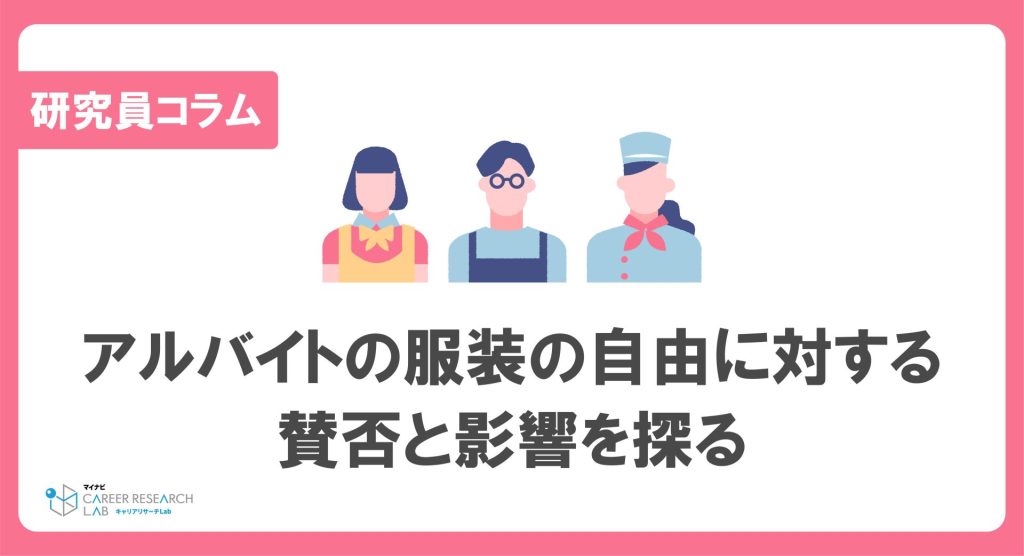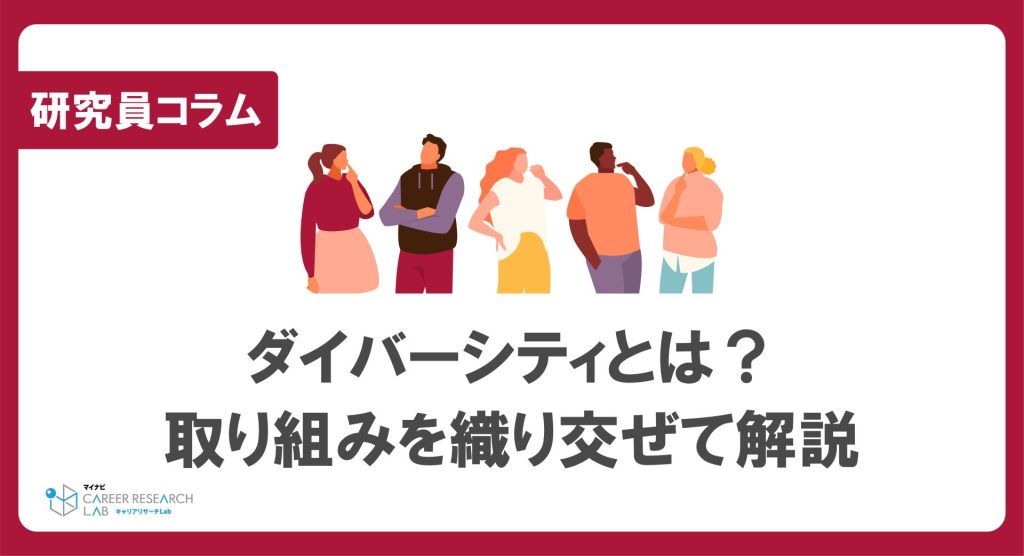
多様化・グローバル化が進む日本企業に求められる理解と実践~有識者のインタビューから考える日本社会のダイバーシティ~
労働力不足や経済のグローバル化、生産性の向上など現代の日本の職場環境において、ダイバーシティの推進はますます重要なテーマとなっている。多様な背景を持つ人々がともに働くことで、創造性や問題解決能力、組織全体のパフォーマンスの向上が期待されているが、ダイバーシティを実現するためには、単に多様な人材を集めるだけでなく、安心して働ける環境を整えることが不可欠だ。
本企画は、グローバル化が進む今、改めて日本の伝統や宗教観にフォーカスを当てて、日本の現代の働き方の良い点や改善点を明らかにしようという想いで始めたが、今回インタビューをお願いした先生方とのやりとりの中で、まずは知っておくべき基本知識を知ること、視野を広げることが重要だと感じ企画の方向性を変更した。結果として、自分たちが知っておくべき基本的な知識を各記事で伝えることができたのではないかと感じている。
この記事では、これまで4回にわたり、各分野の専門家である先生方のお話から得た内容をまとめ、これからの日本の職場におけるダイバーシティ推進について、必要となる要素を抜粋して紹介しようと思う。
目次 [もっと見る]
専門家の紹介
まずは、インタビューを伺った先生方を紹介する。以下でまとめている内容は、記載している各インタビュー記事より抜粋している。詳細はそれぞれの記事を参照してほしい。
立命館大学特任教授・一般社団法人UNLEARN代表理事 中村正氏
・テーマ:男性学/職場におけるハラスメント・ジェンダー理解
京都大学名誉教授・上智大学グリーフケア研究所 副所長 西平直氏
・テーマ:日本古来の「稽古」という考え方/世代間の考え方のギャップ
早稲田大学 法学部教授 水町勇一郎氏
・テーマ:日本と世界の労働観の違い/個人の多様化に合わせた制度設計
國學院大學 神道文化学部名誉教授 井上順孝氏
・テーマ:宗教の基本知識/職場における宗教観の違い
次の段落以降、各インタビューより抜粋した内容をまとめている。
男性学の視点から見る職場のハラスメント
立命館大学の中村先生には、男性学の視点から職場におけるハラスメントの問題やジェンダー理解について伺った。インタビューの中で特に印象に残ったことは、職場におけるハラスメントや暴力の背景には、リーダーやマジョリティの無自覚や無知が影響しており、適切な理解と行動が求められるという点だ。
以下では、インタビューから要点をいくつかピックアップして紹介する。
パワーを持つ者の責任
パワーを持つ者は無知であることに責任が伴い、適切な理解と行動が求められる。特にリーダーには、パワーやコントロールについての適切な理解と行動力が必要であり、ハラスメントの抑止にはこれが不可欠である。
アンラーンの重要性
従来の経験則を断ち切り、新たに学び直し(アンラーン)の機会が求められており、リーダーは上の世代を模倣するのではなく、合理的に物事を選択できる能力を持つことが重要だ。さらに教養としてハラスメントに関わる「知」も必要で、それにより他者の自由を尊重することで、自分の自由も尊重されるという関係を築くことができる。
ジェンダーの違いをきっかけする
リーダーのパワーの濫用は、日本においてはジェンダーの問題としても捉えられる。男性リーダーが無自覚に行うハラスメント行為は、ジェンダーバイアスに基づくものが多く、これを理解し、改善することが求められる。
伝統的な「稽古」の視点から見る世代間ギャップ
京都大学の西平先生には、日本の伝統的な稽古という視点から現代の仕事の向き合い方についてお話を伺った。インタビューの中で印象に残っているのは、「稽古」という考え方は、現代の仕事の向き合い方やスキルの高め方、また世代間の考え方の違いにも通ずる部分があるという点だ。
稽古は練習とは違い、技術の修得だけでなく、内面を磨き、アートへと昇華する。それが自分にしかできない技術を追求することになるのだ。
以下では、インタビューから要点をいくつかピックアップして紹介する。
稽古の意味と練習・修行との違い
日本の伝統的な武道や芸術において、「稽古」は技術の修得や向上のために行われてきた。稽古はスキルの修得だけで終わらず、内面を磨く行為も含まれる。「練習」は特定の技術を習得するための行為であり、「修行」は内面性の成熟に重きを置くが、「稽古」はその両方を含んでいる。若い世代はスキルの習得に重点を置く傾向があり、「練習」の部分を重視する傾向がある。
成功と成就の違い
成就は内面的な納得感を伴うものであり、成功とは異なる。成就には「やるべきことはやった」という納得感が含まれ、外部からの評価よりも自己の内面に重きを置く。たとえば、「稽古」には終わりがなく、名人になっても同じ稽古を続ける。
外からの評価だけでなく、自分自身の内面的な納得感が重要な意味を持つのだ。若い世代は外部からの評価を重視する傾向があるが、成就の意義を理解することで、より深い満足感を得ることができる。
過剰に「タイパ」を求める弊害
現代社会では、短時間で結果を出すことを求められることが多く、過剰に「タイパ」(タイムパフォーマンス)を求める傾向がある。しかし、これが技術の本質的な修得を妨げることにつながることがある。長期的な視点で技術を磨くことや短期的な成果ばかりに目を向けず、長期的な視点をもって見守り、声かけをすることも重要だ。
日本と欧米の労働観の違いと多様化に合わせた制度作り
早稲田大学の水町先生には、日本と欧米の労働観の違いについてお話を伺った。日本企業の職場環境の多様化が進む中で、異なる考え方や生き方を尊重する意識とダイバーシティを大切にする組織作りが求められている。
日本の場合、江戸時代の家業観に基づく労働観が雇用システムの基盤となり、高度経済成長期には企業が大きな家族のような共同体となって、終身雇用や家族手当などの制度が確立された。一方で、欧米は、長らく労働は非人間的な行為とされており、宗教革命において真面目に働くことが良いことだという現在の労働観が形成された。
以下では、インタビューから要点をいくつかピックアップして紹介する。
日本の労働観の歴史的背景
日本の労働観には、歴史的背景と文化的要素が深く影響している。江戸時代には、働くことは家業として捉えられ、「生業」と「職分」の二つの側面があった。
生業は生活のための仕事を意味し、職分は社会的役割や責任を果たすことを指す。この時代の労働観は、家族や地域社会との結びつきが強く、江戸時代の家業観に基づく労働観が、日本の雇用システムの基盤となっている。
欧米の労働観との違い
欧米では、宗教改革によって約2000年続いた労働観が変わり、労働は罰から「自由な行い」へと変化した。個人の自由や権利が重視され、労働は自己実現の手段と見なされるようになった。このため、欧米では個人の成果や能力が評価される傾向が強く、集団よりも個人を重視する文化が根付いている。
現代の労働観とダイバーシティ
現代においては、グローバル化が進む中で、日本企業の職場環境も多様化している。労働観を含めて異なる考え方や生き方を尊重する環境整備が求められている。
これからの日本企業には、柔軟な働き方や多様なキャリアパスの提供、異文化理解の促進など、ダイバーシティを尊重し、個人の多様化に見合った制度改革が求められている。
宗教の基本知識と宗教観の違い
國學院大學の井上先生には、知っておくべき宗教の基本知識と宗教観についてお話を伺った。インタビューの中で印象に残った点は、日本の職場環境の多様化に伴い、宗教に対する基本的な理解や同僚・チームメンバーの信仰・価値観への理解、寛容な態度の必要性が求められているという点だ。
宗教に対する基礎知識を持ち、宗教文化の違いを理解することで、トラブルを未然に防ぎ、円滑なコミュニケーションを図ることができる。さらに、正しい情報を見極める力や宗教情報リテラシーの向上も求められている。
以下では、インタビューから要点をいくつかピックアップして紹介する。
信仰にはグラデーションがある
日本人の多くは無宗教とされるが、実際には宗教的な習俗を自然に行っている。信仰の深さにはグラデーションがあり、無宗教とされる人も宗教的な行動を取ることがある。
同様に宗教や信仰に対する態度は国によって異なるが、どの国でも信仰の深さにはグラデーションがある。例えば、アメリカではキリスト教徒でも聖書を読んだことがない人がいる。
戒律や食のタブーを知らないとリスクを抱える危険性も
グローバル化が進む中で、宗教ごとの戒律や特に日常生活に関わりの深い「食のタブー」を知らないとトラブルになる可能性がある。イスラム教やユダヤ教の戒律は特に厳しく、日本人も基礎知識を持つことが重要だ。
また、企業や教育機関などで宗教に対する理解が不足していると、事業や教育に大きな障害をもたらすリスクがある。宗教文化の違いを理解し、適切に対応することが求められる。
正しい情報を見極める力や宗教情報リテラシーが求められる
インターネット上には不確かな情報が多いため、信頼できる情報源から正しい知識を得ることや情報を見極める力が重要だ。また、普段の生活において、宗教情報リテラシーを高めることで、トラブルを未然に防ぐことにもつながる。
まとめ
今回、それぞれの専門家の視点から、これからの日本の職場において必要な要素についてさまざまな示唆をいただいた。グローバル化が進む中、これまで以上にさまざまな背景をもった人が同じ職場で働くことが増えてくることが予想されている。
そのためには、まず視野を広げ、知識や教養を身につけることが重要だ。もちろん、日本独自の考え方や風習を否定するわけではない。日本が培ってきた良い面をベースとして、試行錯誤しながら取り入れていくことが求められているのだ。インタビューを通して共通して感じたことは、これからの日本の職場においてダイバーシティを推進するには、柔軟な姿勢と継続的な学びが不可欠であるということだ。
これらの示唆が、皆さんの職場でのダイバーシティ推進のヒントになれば幸いだ。