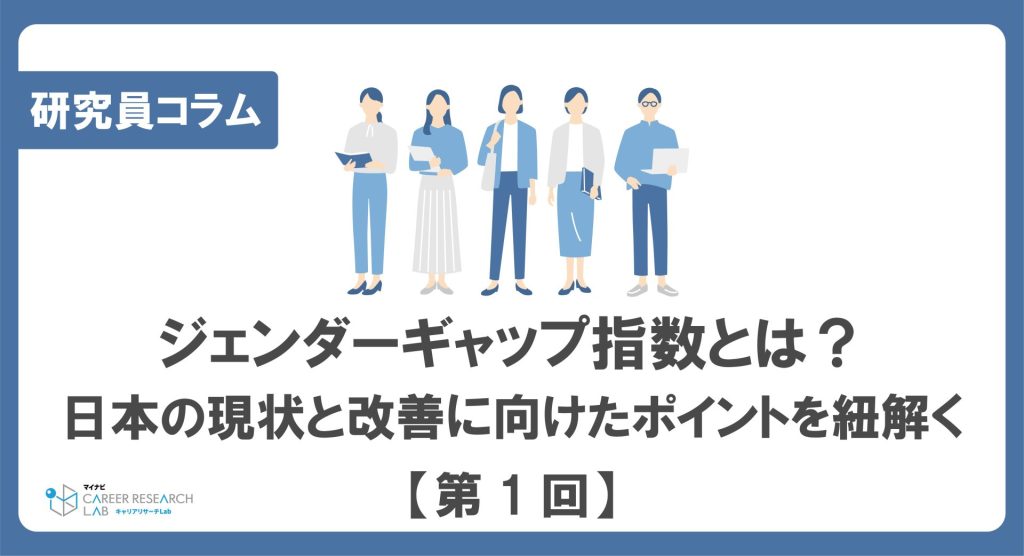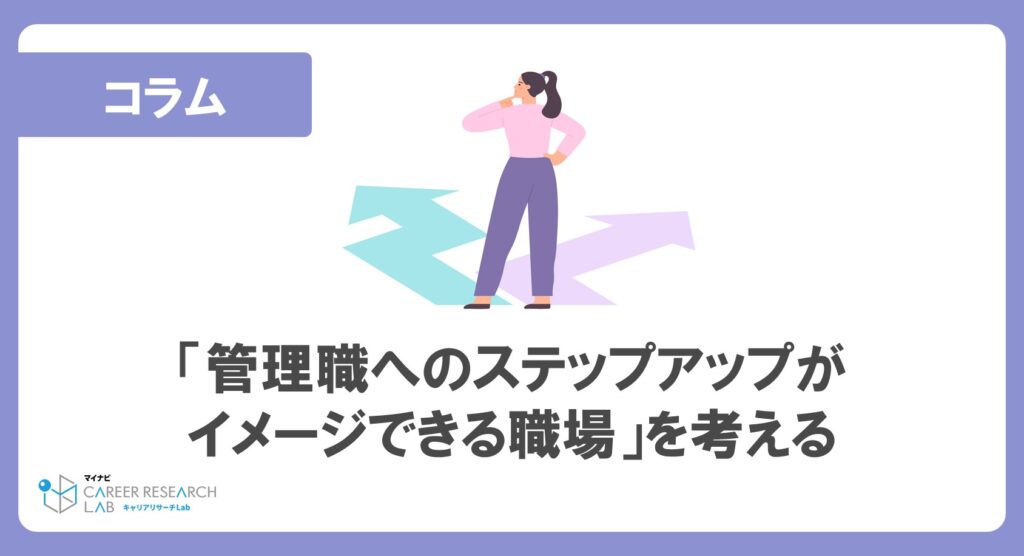3月8日は国際女性デー、女性の生き方を考える日に「女性管理職比率の向上」に注目する─法政大学 キャリアデザイン学部 坂爪洋美教授
毎年3月8日は、国連が定めた記念日「国際女性デー(International Women’s Day)」だ。国際女性デーとは、国連により1975年に定められた記念日で、女性たちが、平和と安全や開発における役割の拡大、組織やコミュニティにおける地位向上などによって、どこまでその可能性を広げてきたかを確認すると同時に、今後のさらなる前進に向けて話し合う機会として設けられた。
本コラムでは、国際女性デーに関連して、日本において特にジェンダー格差が指摘されている「女性管理職比率」について、法政大学キャリアデザイン学部の坂爪洋美教授に主任研究員である東郷がお話を伺った。

坂爪洋美(法政大学 キャリアデザイン学部 教授)
慶應大学文学部卒業後、㈱リクルート人材センター(現:リクルート・キャリア)での勤務を経て、慶應義塾大学大学院経営管理研究科にて2003年博士(経営学)を取得。和光大学を経て、2015年4月より現職。専門は組織行動論。主たる研究テーマは、多様化した働き方の下での管理職のマネジメントのあり方。近著に「管理職の役割」(中央経済社、共著)。
目次 [もっと見る]
女性管理職比率向上の必要性とは?
Q:管理職になることがキャリアアップのゴールとは限りませんが、女性が管理職になる比率が男性に比べて明らかに低い日本の現状は、働く女性のモチベーションに大きく関わってしまうのではないかと考えております。リーダーシップ研究をされている坂爪先生は、女性管理職比率向上の必要性についてどのようにお考えでしょうか?
坂爪:どう働くかというのは個人の選択ではありますが、入社時の男女の比率が半々だったのに、管理職の比率が男女で極端に差ができてしまうとしたら、入社後のキャリアの中で、女性の就業継続が難しいことや女性のキャリア開発のどこかの段階に課題があると考えられます。
女性自身が「私には無理」「私は期待されてない」「女性だから~~しなければ……」「女性のくせにと思われていうのではないか」と感じてしまって、その結果、本来持っている力を発揮できていないのなら、それは解消されるべきだと考えています。

女性管理職比率の向上が働き方の多様性を促進
Q:女性管理職比率を上げること自体を目的化することが必ずしも正しいとは思いませんが、さまざまな取り組みの結果として、女性管理職比率が向上したというのは、企業内でポジティブな影響があるのではないでしょうか。
坂爪:企業における管理職の重要性が高まっています。企業の成長には優れた人材が必要不可欠で、管理職は部下の育成、評価やフィードバックにおいて非常に重要な役割を担うようになっており、管理職に対する期待も高まっているわけです。
女性が管理職になるチャンスが拡大すれば、会社の中で管理職候補が増え、より良い管理職を選ぶことが可能になります。また、女性自身も前向きな気持ちで仕事に取り組むことができることを通じて社内の活性化も期待できるでしょう。本来であれば家事や育児、介護は男女ともに取り組むべきことではありますが、現状では、女性の方が多く家事や育児、介護と仕事を両立しながら働いている実態があります。家事や育児、介護を担いながら活躍する女性管理職が増えてくることで、会社全体の働き方にも多様性が生まれてくるでしょう。
また、女性管理職比率が向上するということは、その企業が女性のキャリア形成の困難さを解消すべく取り組んでいることを示す指標として、社内外への有効なメッセージになるのではないでしょうか。
昇進に際して、さまざまなサポートが必要に
Q:女性管理職を増やすことが推進されていますが、なかなか女性管理職比率が向上しないようです。女性が管理職に就く際に直面する主な課題は何でしょうか?
坂爪:女性管理職比率の数値公表の義務化が進んでいることで、数値的な目標を掲げて取り組みを進める企業が少なくありません。しかし、数値目標を掲げると、どうしてもその目標を達成することが目的化されてしまい、十分に管理職としての役割を学ぶ機会が提供されないまま無理してでも昇進させるケースがあるように思います。仮にそういった昇進があるとしたら、昇進させて終わり、ということではなく、昇進後にも当面の間、適切なサポートが必要となるでしょう。
一方で、正当な評価で女性が管理職に昇進したケースであっても、周りから「女性だから昇進したんだ」と揶揄されることがないように、人事担当者なり、より上の立場の人間が昇進の背景について明確に説明する必要があるでしょう。
また、女性管理職の誕生がその企業の従来の男性中心だった管理職像とギャップが存在する可能性も考えられますし、男性管理職を中心としたコミュニティ(いわゆるオールドボーイズネットワーク)に新たに飛び込んでいく際にハードルを感じるケースもあるかと思います。それに対しても会社は目配りすることが求められます。
多様な人材が活躍できる組織を作ることが重要
Q:女性が管理職として活躍できる組織にするために、組織側はどういった対策や心構えが必要になるでしょうか?
坂爪:労働人口の減少と人材の流動化が進む中で、企業にとって優秀な人材の確保が非常に重要な課題になっています。これまで以上に多種多様な人材が力を発揮できる組織作りが求められています。その意味で、女性活躍を切り口に人材活用のあり方を変えていく視点が必要なのではないでしょうか。
必要に応じていくらでも残業ができて、どこでも転勤ができる人だけが活躍していた時代と、今は大きく状況が変わっています。働く人々全体の多様性が高まっていて、多様な人材が活躍できる組織、言い方を変えれば特定の属性が働きにくさを感じない組織を作ることが大切です。自分と違う価値観の人がいるということを尊重し、そのことに思いをはせることができる職場環境が求められています。
これからの管理職に求められる役割とは?
Q:これからの管理職にはどのような役割が求められるでしょうか?
坂爪:近年、管理職の仕事の負荷がますます高まっています。家事・育児負担が女性に偏っている日本の現状を踏まえると、年齢的には育児や介護もしなければならない世代でもある女性が管理職になりたくないと思うことがないよう、管理職の業務はどうあるべきかについて、あらためて経営者にも考えてもらう必要があるように思います。
管理職の仕事は取捨選択が必要です。「自分がやった方が早いから」とか「部下に残業させるわけにいかないから」と部下の仕事を巻き取らず、男女関わらず、「任せる」ことがキーワードになってきているように感じます。特に女性管理職は、「女性だからダメだと思われないように結果を出さなければ」と気負いすぎる傾向がみられます。「できない部分」を部下と共有して仕事を進めることが重要ではないでしょうか。いかに自分の仕事を手離れさせていくか、管理職がそんなスキルを高められるような人材育成も必要だと思います。
組織内の衝突を解決し、教育を通じて情報を提供
Q:女性管理職比率の向上など、ダイバーシティ推進のための教育やトレーニングの重要性について、どのようにお考えですか?
坂爪:人は変化することに対して抵抗する生き物です。その抵抗を少しでも和らげるために働きかけるのが、教育やトレーニングです。ダイバーシティ推進について、「もう聞き飽きた」と感じている人がいるかもしれませんが、なぜ推進する必要があるのかについて、教育し続ける必要があります。
ダイバーシティ推進の難しさは、「現状で何に問題があるの?」という根深い疑問があることと、進んでいくと「不公平感(女性優遇・子育てや介護を担う人優遇)」が出てくることです。
こういった組織内での対立や衝突を解決するコンフリクトマネジメントが重要で、教育とトレーニングを通じて、気づきや情報を提供し、アンコンシャス・バイアスを解消していくことが大切だと考えます。

国際女性デーをきっかけに女性活躍、ダイバーシティ推進を考える
Q:国際女性デーを女性の生き方やキャリアを考えるきっかけにしたいと思います。何かメッセージがあればお聞かせいただけますか。
坂爪:女性活躍は古くて新しいテーマです。企業で長く働いている方の中には「もういい加減いいのではないか」「もう十分ではないか」といった印象を持つ人も少なくないように思います。しかし、世界経済フォーラムが算出しているジェンダー・ギャップ指数をみれば明らかなように、まだまだ不十分というのが現実です。国際女性デーが、そのことを考えるきっかけになればいいなと思います。
また、ダイバーシティ推進に関しては、企業間で考え方や取り組みの差が拡大してきている印象があります。従業員の力を引き出してうまく回り始めた会社が増えてきた一方で、何となく今まで通りのままになっている会社も少なくないように感じます。しかし、5年後、10年後の日本の労働人口を考えてみると、今のままで良いわけがありません。そういった状況を踏まえて、自分の会社に何ができるのか、特に経営層の方に考えてほしいですね。