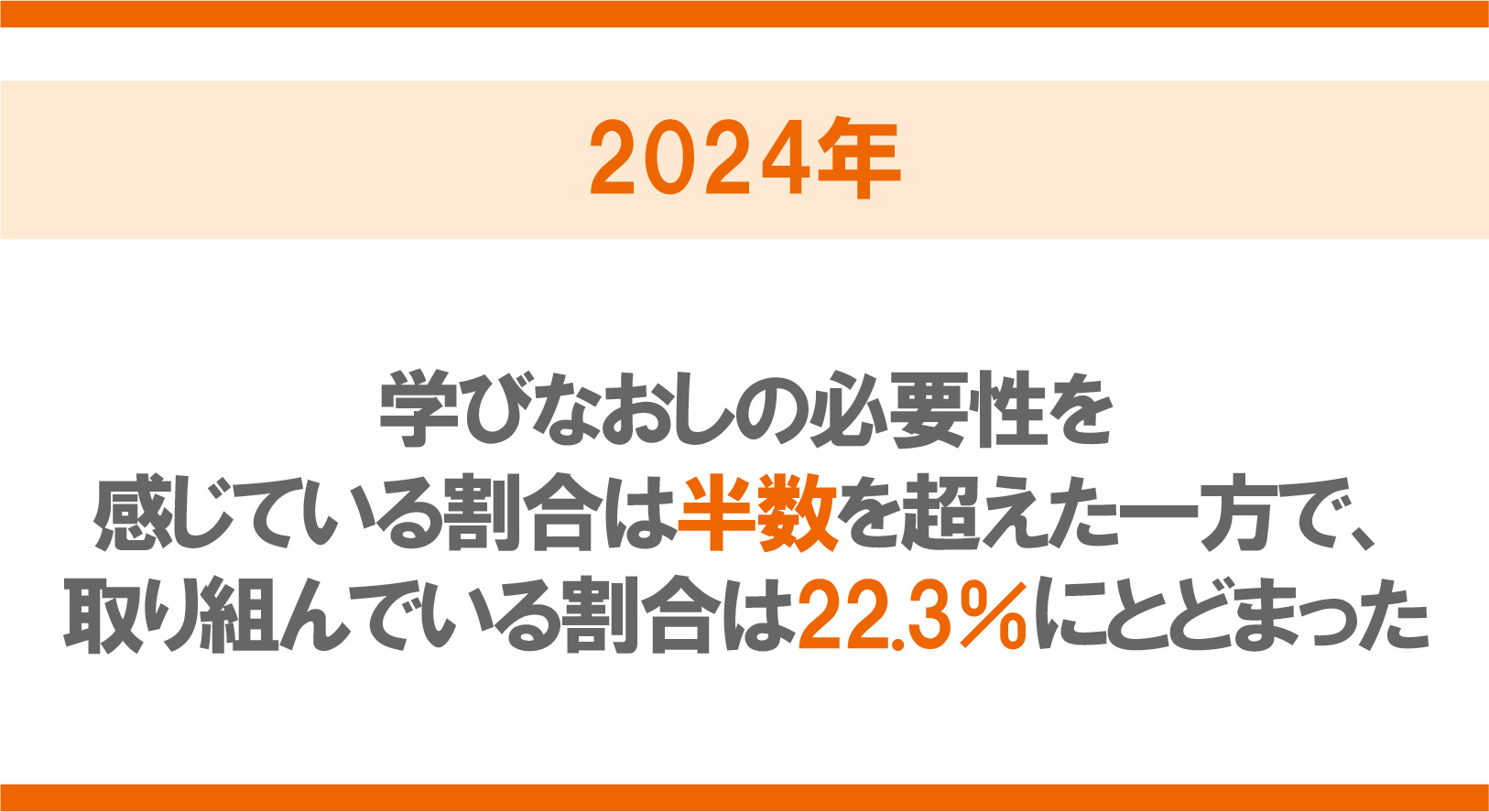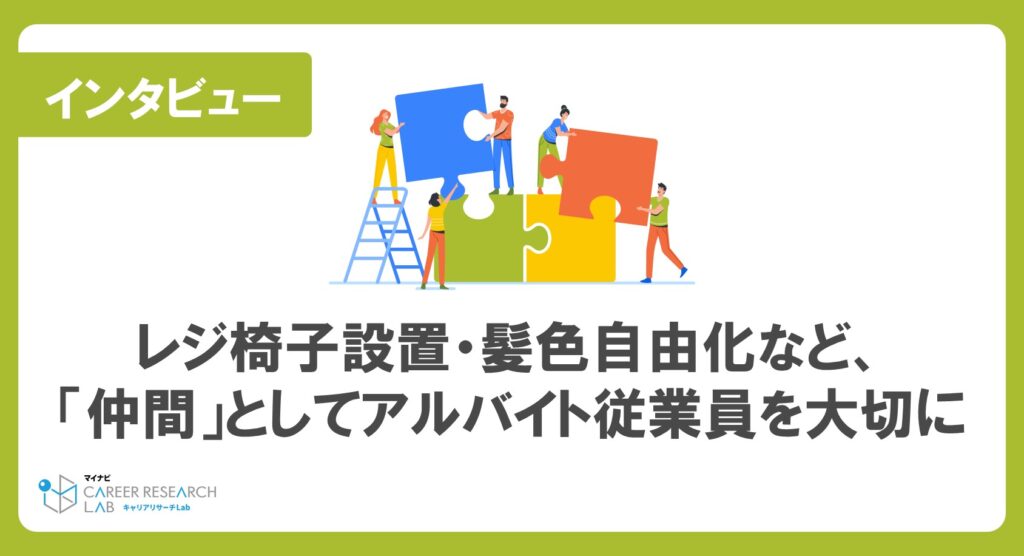
子連れ出勤がもたらす職員の確保・定着と利用者さんの笑顔(社会福祉法人 新生寿会)
「アルバイト従業員の新しい在り方」について考える本シリーズ。今回は、少子高齢化が進む現代において、特に人手不足が深刻な課題となっている介護業界に着目しました。
社会福祉法人 新生寿会は、この課題に対し、正職員の雇用継続を目指して2010年ごろから「子連れ出勤」に取り組み始めました。育児中の職員が子どもを連れて働きやすい環境を整備することで、離職を防ぎ、長く安心して働ける職場作りを進めており、パート職員にもその取り組みが拡大されています。
本インタビューでは、新生寿会きのこ地域連携室室長の鈴木裕太さんと東五反田倶楽部・小山倶楽部施設長の下村一真さん、そしてパート職員の河野真弥さんに、子連れ出勤を始めた背景と具体的な取り組み内容、そして現場のリアルな声を語っていただきました。
社会福祉法人 新生寿会
設立:1980年
事業内容:介護サービス全般

社会福祉法人 新生寿会
きのこ地域連携室 室長
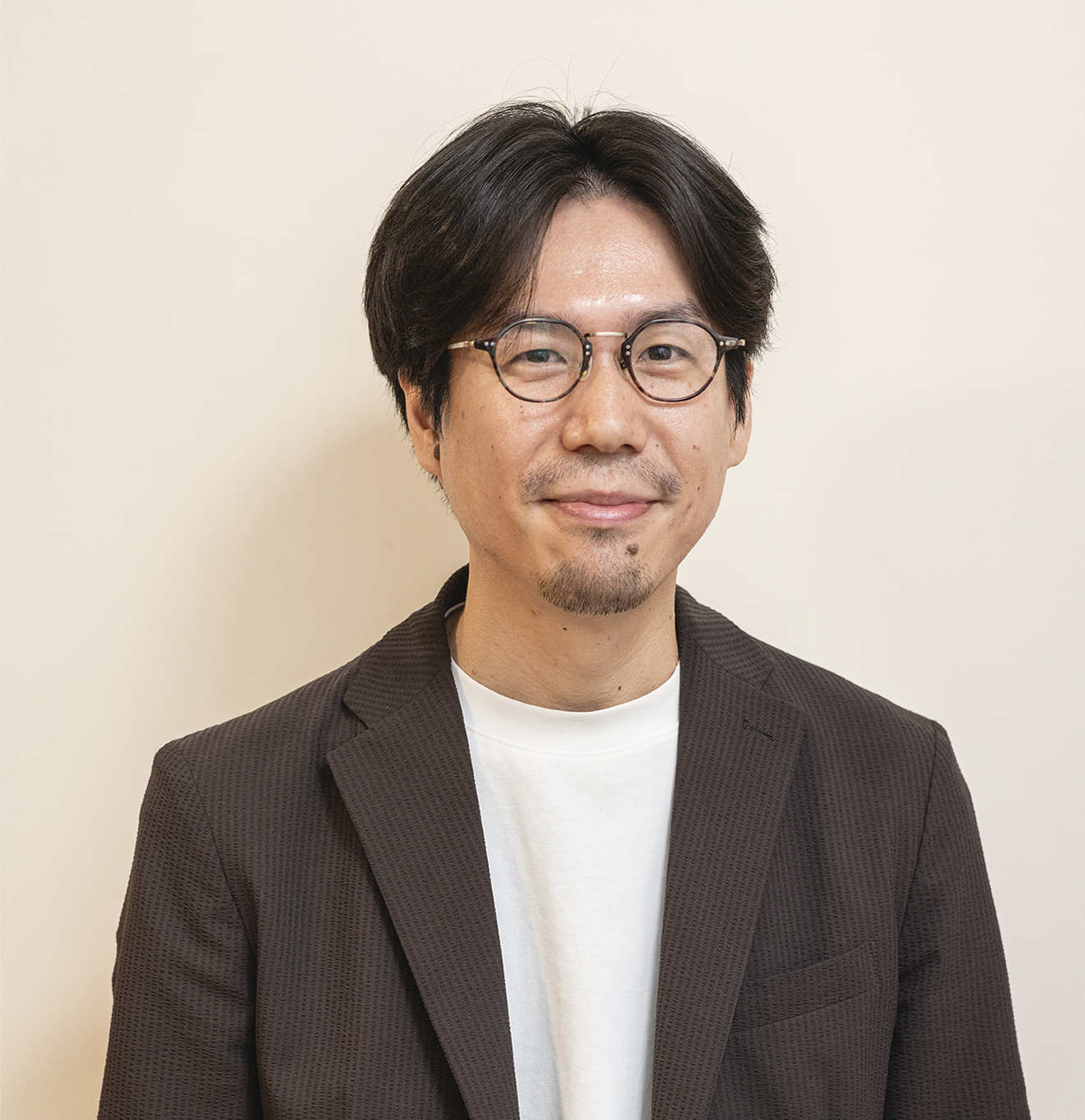
社会福祉法人 新生寿会
東五反田倶楽部・小山倶楽部施設長
目次 [もっと見る]
正職員の離職防止を目指して「子連れ出勤」をスタート
Q.貴法人では、正職員の離職という課題をきっかけに、2010年ごろから職員の「子連れ出勤」の受け入れを始められたとのことですが、当時感じられていた問題意識などについてお聞かせください。
介護職員は不規則な労働時間や変則的な勤務体系になりがちですから、妊娠や出産を機に退職せざるを得ないという方が多いというのが課題でした。せっかく育ってきた人材が、ライフイベントによって現場を離れてしまうのは、法人としても大きな損失です。なんとかして、そうした状況を打開できないか、職員に長く安心して働き続けてもらえる方法はないかと悩んでいました。
そこで着目したのが、出産後の女性職員の働き方です。子どもを保育園に入れられなくて、働きたくても働けない、というお母さんたちの声を耳にしていました。一方で、法人としては、経験のある職員にはぜひ現場に復帰してほしいというニーズがあり、この二つのニーズをなんとかつなげられないかと考えたのが、「子連れ出勤」の原点です。
「働く人の生活」を思い、ニーズに合わせて対応
当初は制度というほど大げさなものではなく、正職員の方が長く働けることを目的として「困っているなら、お子さんを連れてきてもいいよ」という、現場のニーズに合わせた柔軟な対応から始まりました。
でも、もし職場にお子さんを連れてきて働けるのであれば、保育園が見つからない間も仕事を続けられますし、何よりも、これまで培ってきた経験やスキルを活かし続けることができると考えていました。当時はお子さんが保育園に入園したあとも、勤務途中で中抜けしてお子さんを迎えに行くということもよくありました。働く方の生活も大事ですし、長く働いてもらいたい思いもあるので、そういったことにも対応していくことで、職員の方が子育てしやすい環境を整えようとしていました。
柔軟な働き方で職員が定着、若手のロールモデルにも
Q.子連れ出勤を始めたことによる職員の方の変化について教えてください。
大きかったのは、やはり退職を防ぐ効果があったということです。出産や育児を理由に離職せざるを得なかった職員が、子連れで働き続けるという選択肢を持てるようになったことで、結果的に長く勤務してくれる方が増えました。
また、職員は20代で正職員としてスタートする方がほとんどなので、「将来、自分も子どもを産んでもここで働き続けられるんだ」という安心感にもつながったようで、若い世代の職員が将来のライフプランを描きながら働けるようになったという声も聞かれました。そのようなライフプランを選ぶにしろ選ばないにしろ、選択肢が増えたというのが良かったのではと思います。
パート職員も含む、新規職員募集にも子連れ出勤を拡大
Q.既存職員の方の子連れ出勤の効果を踏まえて、その後、新規職員募集においても子連れ出勤について打ち出したとのことですが、その際の反響についてお聞かせください。
初めは元から働いている正職員に対して可能にしていた「子連れ出勤」でしたが、東五反田倶楽部を運営する中で施設の人手不足と、働きたい地域のお母さん方のニーズから、当施設での新規職員の募集においても、積極的に「子連れ出勤可能」であることをアピールすることにしました。求人媒体に、「子どもを連れて働いてみませんか?短時間OK!」といった、他の介護業界の求人広告とは一線を画すような打ち出し方をしました。
また、そのタイミングで正職員だけでなくパート職員も子連れ出勤OKとして、1日2時間から勤務可能という形で募集しました。その結果、通常の募集と比較して、問い合わせの数は明らかに増え、ひっきりなしに電話が鳴っていたほどでした。
特に、子どもを預ける場所に困っていたパート勤務希望のお母さんたちからの応募が非常に多かったと記憶しています。当初は2名程度の採用を予定していたのですが、最終的には7名もの方にご入職いただくことができました。
近隣にお住まいの方だけでなく、これまでなかなか応募がなかったような、やや遠方の方からの問い合わせや応募もありました。1時間半程度の通勤圏内の方からも連絡があり、「子どもを保育園に入れられなくて働けない、でも働かないと保育園入園のための点数が足りない」というお母さんたちにとって、子連れで働ける環境がどれほど切実なニーズであったかを改めて感じさせられました。
子連れ出勤が潜在層へのアプローチにつながる
この募集を通じて強く感じたのは、従来の「介護の仕事を探している人」だけでなく、「働きたいけれど子どもを預けられない」という悩みを抱えている潜在的な労働力にアプローチできたということです。子連れ出勤を打ち出すことで、これまで介護の仕事に関心がなかった層にも興味を持ってもらい、結果的に人手不足の解消にもつながる可能性を感じました。
応募いただいた方は無資格・未経験の方がほとんどでしたので、施設内の生活スペースでの洗い物や掃除などから始めてもらいました。家事の延長線上でできることから始めて、介護業務は正職員から少しずつ教えてもらってできるようになればという形でしたが、当施設では食事準備等も特に大事な業務ですので、そこだけでも正職員の手が離れるのは大きなことでした。

一方で、子連れで勤務しているお母さんたちは、最初はやはり「他の職員に迷惑をかけているのではないか」という気持ちを抱えていた方が多かったようです。子どもが泣いたり、ぐずったりすれば、どうしても対応に追われてしまい、介護業務に集中できない時間帯もあったでしょう。
そのため、同じように子連れで働くお母さんたちを複数採用し、お互いに相談し、助け合えるような環境を作るように心がけました。精神的な負担は、私たちには完全には理解できない部分もあると考え、当事者同士で支え合ってもらうことが重要だと考えたからです。
当時の職員が定着し、子どもが保育園や小学校に入るように
現在、この施設では、常にお子さんを連れて出勤している職員はいない状況になりました。子連れ出勤OKを打ち出して採用に至った当時の職員は、その後、働けるようになったことでお子さんが保育園に入れるようになり、現在では小学生以上になるなど預け先の悩みがなくなり、常に子連れで出勤する必要がなくなったからです。
お子さんの学校などがお休みの日や、行事の日など何か用事があるときにだけ連れてくることも可能なので、小学生~大学生くらいまで、時々職員のお子さんが施設内にいることはありますが、子連れ出勤はそのくらいの機会のみになりました。
また、当時募集した職員たちがそのまま働き続けてくれているため、新しい職員を募集する必要もなくなっています。シフトについては、当初は短時間勤務からスタートする方が多かったと思いますが、徐々にお子さんが成長するにつれて勤務時間を延ばしたり、より多くのシフトに入れたりするようになった方もいらっしゃいます。
利用者様の笑顔が増え、コミュニケーションも活性化
Q.お子さんが施設にいることによる、利用者様の変化があれば教えてください。
子連れ出勤をされる方は3歳くらいまでのお子さんを連れていらっしゃることが多く、ピーク時は8~9人ほどのお子さんがいることもありましたが、まず、会話のきっかけが格段に増えました。小さなお子さんの姿を見ると自然と笑みがこぼれ、話しかける方が多くいらっしゃいます。

「可愛いね」「何歳になったの?」といった日常的な会話から、ご自身の子どもや孫の話へとつながることもあり、これまであまり会話のなかった利用者様同士や、利用者様と職員間のコミュニケーションが活発になる場面が多く見られました。
利用者様の中には、お子さんを自分の孫のように可愛がってくれる方もたくさんいらっしゃいます。ミルクをあげたり、離乳食を食べさせたりするのを手伝ってくれる方もいて、子育て中の職員にとっては心強い存在です。また、子どもたちが利用者様と一緒に遊んだり、お絵描きをしたり、お菓子を作ったりする光景は、日常的な介護業務の中ではなかなか見られない、心温まるものです。
小規模多機能ホームでは訪問介護もあるのですが、その際、ご家族に許可をいただいた利用者様のお宅には、お子さんを一緒に連れて行くこともありました。玄関先で「子どもが来てるよ」と声をかけると、普段はなかなか出てこないおじいちゃんやおばあちゃんが、笑顔で出てきてくれることもありました。子どもと手をつないで一緒に歩いたり、たわいもない話をしたりする中で、利用者様と職員の間に、より一層深い信頼関係が築かれていったと感じています。
もちろん、中には子どもの声や動きが苦手な方もいらっしゃいます。そうした方への配慮も忘れず、可能な範囲で場所を分けたり、声をかけたりするなど、こまやかな対応を心がけています。
子連れ出勤の可能性を行政も理解
Q.お子さんが施設にいる状況で施設を運営していく上で注意していること、配慮していることなどを教えてください。
もっとも注意しているのは安全面です。小さなお子さんは予測不能な行動を取ることがありますので、利用者様の安全はもちろんのこと、お子さん自身の安全確保にも細心の注意を払っています。危険なものがない場所にいてもらう、目を離さない、必要に応じてベビーベッドやベビーチェアを用意するなど、具体的な対策を講じています。
運営面で苦労したことの一つに、行政の理解を得るという点がありました。しかし、私たちは、子連れ勤務の重要性を粘り強く説明し、担当省庁にも相談した結果、「良い事例なのでぜひ進めてほしい」という後押しをいただくことができました。最終的には、行政にも私たちの取り組みの意義を理解していただき、現在では子連れ出勤に対する理解も広まっていると感じています。
悩みを抱えすぎないよう手厚いコミュニケーションを意識
現場の職員に対しては、子連れで働くお母さんたちが孤立しないように、コミュニケーションを密に取るように心がけています。定期的な面談を実施し、困っていることや不安なこと、働き方に関する要望などを丁寧にヒアリングするようにしています。また、子連れで働くお母さん同士が交流できる機会を作ることも重要だと考えています。
労務管理の面では、短時間勤務の職員が増えることで、シフト作成や勤怠管理が複雑になるという課題もあります。しかし、それ以上に、子連れで働けるという柔軟な働き方を提供することのメリットが大きいと考えています。シフトを組む担当者は大変な面もあると思いますが、職員一人ひとりの状況に合わせた働き方を尊重し、できる限り希望に沿えるように調整しています。
開かれた施設運営で地域との交流を深める
Q.従業員の働き方や利用者様の過ごしやすい環境作りについて、大事にしていることや今後目指していることがあれば教えてください。
私たちがもっとも大切にしているのは、「地域とのつながり」です。その一環として、地域の町内会と協力して夏祭りを復活させたり、施設内で駄菓子屋を開いたり、書道教室などの地域住民も参加できるイベントを開催したりしています。

利用者様が子どもたちや地域の人たちと触れ合う機会を積極的に作ることや、働いている職員だけでなく地域と連携することも重要だと考えています。子連れ出勤は、職員が子育てしながら働ける環境づくりとともに、利用者様と地域との自然なつながりを生み出す上でも、大きな役割を果たしていると感じています。
利用者様が地域で長く安心して暮らしていくためには、地域の理解と協力が不可欠です。認知症の方が地域で困ったときに、地域住民の方々が温かく見守り、必要に応じて施設に連絡してくれるような関係性を築いていくことが、今後の重要な課題だと考えています。そのためにも、施設を地域に開かれた存在とし、さまざまな形で地域との交流を深めていきたいと考えています。
子連れ出勤を経験したパート職員の声
ここからは、実際に子連れ出勤をしていたパート職員の方へのインタビューをご紹介します。お話をお伺いしたのは品川区立地域密着型多機能ホーム「東五反田倶楽部」の河野真弥さんです。

子連れ勤務で育児と仕事の両立を実現。さまざまな出会いが子どもの成長にもプラスに
Q.入職当初と現在の勤務のご状況についてお聞かせください。
入職してこの春で丸6年になります。現在は、品川区立地域密着型多機能ホーム「東五反田倶楽部」の介護職員として、利用者様の食事・入浴・排泄の介助、利用者様の自宅への食事のお届けなどを行っています。
勤務し始めた6年前はまだ子どもが生まれたばかりで、週に2、3日、午前10時から午後3時まで勤務していました。自宅が近いので、子どもを連れて自転車で通えるということもあり、本当に働きやすい環境でした。
子どもが1歳になる頃に保育園が見つかったので、それ以降は保育園に通わせていました。現在も以前と変わらず週に3回、同じ時間帯で働いています。子どもが今年、小学校に入学するので、これからは、もう少し勤務時間を増やせたらいいなと思っています。
Q. 東五反田倶楽部にて、子連れ出勤で働かれるようになった経緯などについてお聞かせください。
東五反田倶楽部で勤務を始める前は、約4年間デイサービスで働いていました。子どもができたことをきっかけに前の職場を辞めたのですが、子どもを連れて働くのが難しい環境でした。
子どもが生まれてから、やっぱり仕事がしたいなと思って求職活動をしていたときに、デイサービスで一緒に働いていた頃の仲間がこちらで勤務していて、その方に紹介してもらいました。子どもがまだ小さいうちは、できれば一緒にいたいという気持ちが強かったので、「子連れ出勤OK」と聞いて、本当にありがたかったです。

Q. お子さんを連れての働き方の利点について、実感されていることをお聞かせください。
一番大きかったのは、やっぱり一緒に過ごせたということです。一緒に職場に来て自分が仕事をしている間は、ベビーベッドで寝かせたり、部屋の中で遊ばせたりしていました。利用者様の家を訪問する際に一緒に連れていくこともありましたし、自分が手を離せないときには他の職員の方が見てくれたりしたので、心配はありませんでした。
それに、利用者様との関わりがあったのもすごく良かったなと思っています。子どもは、少し人見知りのところがあったのですが、利用者様の世代の方に対する人見知りが解消された気がします。ここに来ることによって、利用者様や職員を含めていろいろな世代の方たちと関われたのは、子どもの成長にとっても良かったんじゃないかなと思っています。
もちろん大変だったこともあります。子どもの世話をしながらでは、どうしてもできる仕事の範囲が狭まってしまいます。他の職員の方に迷惑をかけてしまっているのではないかと気になることもありました。それでも、同じように子連れ勤務をしている人もいましたので、お互いに支え合いながら仕事をすることができました。
勤務し始めた頃は0歳だった子どもも、今年、小学生になりました。今では、何かのイベントでもない限り、子どもを連れてくる機会はありませんが、子どもが小さい頃、子連れで勤務させてもらえて本当に助かりました。こういう勤務形態がもっといろいろな職場で実現するといいなと思っています。
編集後記
今回お話を伺った社会福祉法人 新生寿会ではライフイベントをきっかけにした職員の離職防止を狙いとして子連れ出勤を開始し、その後、働きたいお母さんのニーズと職員を増やしたい法人のニーズから、子連れ出勤を新規職員に拡大し、パート職員の採用も開始しました。
その結果、子連れ出勤している職員がお子さんを保育園に預けて働けるようになっただけでなく、他の職員のロールモデルになったり、利用者さんの笑顔を増やしたり、お子さんが普段関わらない年代の大人と交流する機会にもなっています。
また、子連れ出勤をきっかけに入職したパート職員の方々は、未経験・短時間からのスタートでしたが、お子さんが小学校に入った際などには、今まで周りにサポートしてもらった分、さらにシフトに入ろうと意欲向上にもつながっているそうです。
職員の働きやすさへの取り組みは課題やハードルもありますが、働きかけ方次第で職員だけでなく、関わるさまざまな人にポジティブな影響をもたらしたり、職員の意欲向上などの長期的な効果を生んだりする可能性をも秘めているのではないでしょうか。