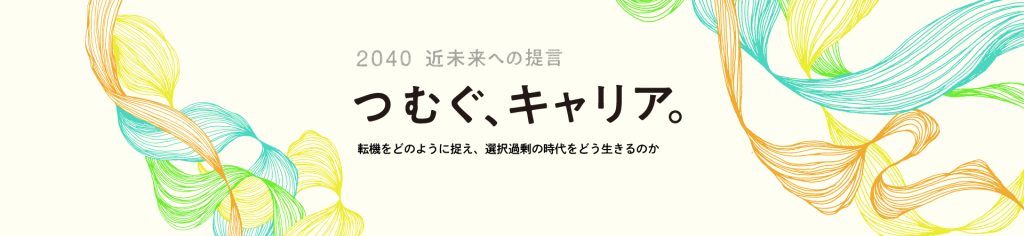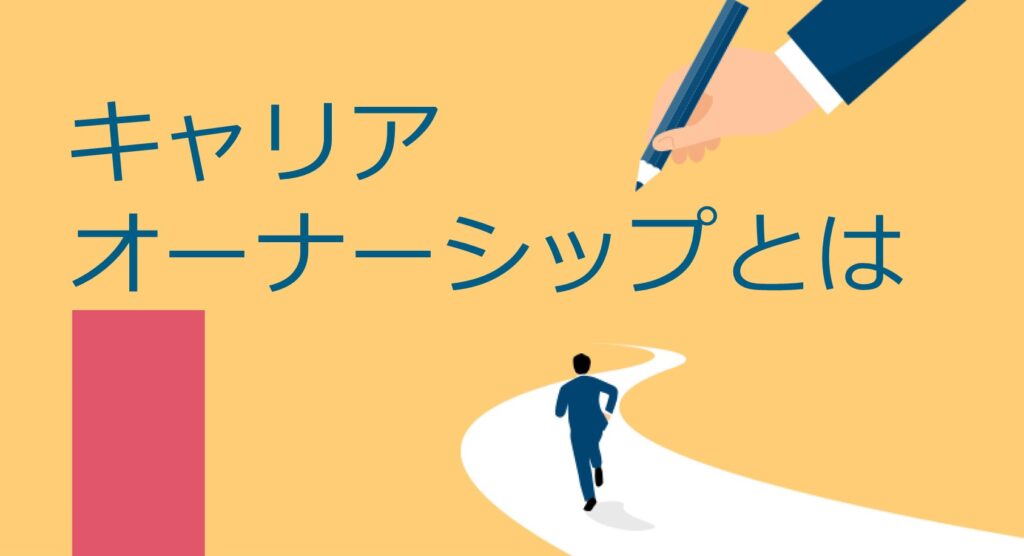国際幸福デー(3月20日)をきっかけに幸せなキャリア・持続可能な働き方を考える-国連広報センター所長 根本かおる氏
みなさま、3月20日が何の日かご存じでしょうか。3月20日は、国際連合(以下、国連)が制定した国際幸福デーという日です。今回、3月を目前に、国際幸福デーとはどのような日なのか、どのような想いがあって制定したのか、国際幸福デーを起点に私たちができることはあるのか、などについて、国連広報センター所長の根本かおるさんに話を伺いました。

根本かおる(国連広報センター所長)
東京大学法学部卒。テレビ朝日を経て、米国コロンビア大学大学院より国際関係論修士号を取得。1996年から2011年末まで国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)にて、アジア、アフリカなどで難民支援活動に従事。ジュネーブ本部では政策立案、民間部門からの活動資金調達のコーディネートを担当。WFP国連世界食糧計画広報官、国連UNHCR協会事務局長も歴任。フリー・ジャーナリストを経て2013年8月より現職。2016年より日本政府が開催する「持続可能な開発目標(SDGs)推進円卓会議」の構成員を2024年6月まで務めた。2015年以来、SDGsの重要性を訴え続けたことが評価され、2021年度日本PR大賞「パーソン・オブ・ザ・イヤー」を受賞。
目次 [もっと見る]
国連の国際幸福デー・国際デーに対する想いとは?

国際幸福デーとは?
質問:まず、国連が国際幸福デーを制定した経緯や意義について教えてください。
根本:国際幸福デーは、ヒマラヤ山脈の東端にある仏教王国ブータンによって提唱され、2012年7月の国連総会で決議された記念日です。1970年代にブータンの前国王が、GNP(国民総生産)やGDP(国内総生産)などの物質的な豊かさの指標に代わる、精神的な満足度を国の一つの指標にしようと考え、国民総幸福量(GNH)という概念を打ち出しました。GNPやGDPなどの指標では抜け落ちてしまう自然の豊かさや家庭の満足度などを加味した豊かさを測っていこうと提案されたわけです。
国連総会でこの決議が採択される直前、2012年の6月にはブラジルのリオデジャネイロで国連持続可能な開発会議「リオ+20」が開催されました。そこで議論された結果を踏まえて2015年に持続可能な開発目標(SDGs)が国連で採択されるわけですが、そういった持続可能な開発を目指した社会目標を作ろうということが議論されたのが「リオ+20」だったわけです。
ですからちょうどその頃というのは、バランスの取れた経済や社会、環境と持続可能性(サステナビリティ)に重きを置いた豊かさというものが必要だよねという考えが国際的な潮流になっていたと言っても過言ではありません。こういった時代背景を反映する形で、国際幸福デーが制定されたわけです。
質問:世界幸福度報告というものもあるかと思いますが、国連や国際幸福デーと関係はあるのでしょうか。
根本:世界幸福度報告(World Happiness Report)は、国連から独立したグローバルな研究者のネットワーク「Sustainable Development Solutions Network(SDSN=持続可能な開発ソリューション・ネットワーク)」がまとめているもので、国際幸福デーにあわせて発表されています。
SDSNというのは、研究機関や大学、企業、市民団体などが連携して、持続可能な社会の実現に向けた解決策を導き出すことを目的として設立されたネットワークで、世界幸福度調査の報告の一環として調査対象の国々の幸福度のランキングを出しており、このランキングがニュースなどを通じて話題になることがありますね。
国際デーに対する想い
質問:国連は国際幸福デーに限らず、多くの国際デーを制定していると思うのですが、どのような想いが込められているのでしょうか。
根本:国連で定められた国際デーはたくさんあり、365日、何かの国際デーに当てはまらない日はないほどかと思います。日によっては4つ・5つも重なることもあるくらいです。それぞれの国際デーには、国連からのメッセージを発信しており、事務総長自らのメッセージが発信されることも少なくありません。すべてではありませんが、日本語化してWEBサイトに掲載もしています。
私たちはこのメッセージを非常に大切にしています。国連には領土もありませんし、予算も潤沢にあるわけではありません。国連に信頼を寄せてくださっている人々に向けたメッセージや言葉こそが、国連にとって大きな力になります。国際デーがその事柄について改めて考えるきっかけになればいいなと思っています。
世界幸福度ランキングから見る日本の幸福度とは?

質問:物質的に恵まれている日本ですが、2024年版の世界幸福度ランキング(※)では、日本は51位と、先進国では低い位置にあります。日本の現状をどのようにお考えでしょうか。
根本:幸福度ランキングは6項目で評価されるのですが、日本は特に「人生の主観的満足度」が低い傾向にあります。子どもたちの教育の場面でもそうだと思うのですが、日本は減点主義だと私は感じています。褒めて伸ばすのではなく、できていないことを指摘する、そういう国民性が強いのではないかなと思います。
また、ある意識調査によると、日本人は与えられたチャンスを好機と捉えず負担と感じる人もいるようです。日本が豊かな国であることに間違いはないですが、自分たちに与えられているもの、自分たちの手の中にあるものに目を向けるのではなく、ないものを意識してしまうという、そういう国民性が、先進国としては幸福度が低いところにも表れているのではないかなと思います。
※世界幸福度ランキングは、対象国で実施された世論調査(①GDP、②社会的支援、③健康寿命、④社会的自由、⑤寛容さ、⑥人生の主観的満足度)をもとに、幸福度を0から10の10段階で自己評価した主観の平均値をランキング化しています。
質問:では、これから日本が幸福度をより感じるようになるために、根本さんの経験談などありましたら教えてください。
根本:私は、貧困に苦しむアフリカの国などでも仕事をした経験がありますが、そこで暮らしている人々は貧しい暮らしをしていても、とても良い笑顔を見せます。自分のコミュニティや家族の間での助け合いも発達しています。
アフリカで仕事をしていた頃、日本に帰ってくるたびに、物質的には恵まれない国の人たちがあんなに素晴らしい笑顔を見せるのに、この豊かな日本では、電車で疲れ切っている人々を見るにつけ、どうしてこんなに元気がないのだろうと不思議に思うことがよくありました。
また、私はアメリカに留学した経験があるのですが、アメリカでは「You can do it. あなたならできる!」と励まされ、うまくできれば、「Bravo, Excellent!」と褒めてくれて、「こういうふうにできたらもっといいね!」といったスタイルの指導法が中心なのです。
「駄目だ、駄目だ」と言われると反発する気持ちになりますが、プラスの側面に目を向けて、「こうすればもっと良くなる」と言われれば、より大きな力が出るのではないでしょうか。よく言われることですが、コップの半分に水が入っているときに、「もう半分しかない」と考えるのではなく、「まだ半分ある」と考える、そういう発想の転換が必要なのかなと思います。
持続可能性・ウェルビーイングという視点から日本の働く場でできること

質問:持続可能性やウェルビーイングの視点から日本の職場環境を見たとき、日本の企業が考えるべきことについて教えてください。
根本:これからの時代、サステナブルな考え方を大切にする企業経営が求められます。日本では、働きすぎによる自死や過労死が社会的にも問題になりました。そういう意味でもこれからはサステナビリティという考えを無くして経営はできませんし、社員のサステナビリティを考えないといけません。
私自身、バブルのピークの時期に社会人になったこともあり、かつては寝る間を惜しんで働いていた時代もありました。しかし、年齢を重ねる中で親の介護など家庭の事情が変わるにつれてこのままではうまくいかないと気付いたわけです。
これから社会人になろうとする人たちや若手社会人は、地球の資源には限りがあって、いろいろな制約の中で経済を回し、暮らしていくことが当たり前だと考えています。経済的豊かさのために、何かを犠牲にすればいいという考えではないですよね。
若い人たちはバランスの取れた働き方に関心が高く、不公正や不平等なことに敏感です。優秀な人材を採用し、長く定着して働いてもらうためには、企業はサステナブルな経営の仕方に舵を切る必要があると思います。職場での具体的な取り組みとしては、社内のミーティングなどの機会に、リーダーが中心となって、自分たちが仕事だけでなく生活面も含めて心身ともにハッピー(幸福)な状態にあるかどうか、まずは言葉にしてみることが大切なのではないかと思います。
国際幸福デーをきっかけにするとしたら、何かイベントやキャンペーンをやってみるのもいいでしょうし、社内で幸福度調査をするのもいいかもしれません。社員がどの程度ハッピーな状況にあるのか、アンケート調査をしてみることで明らかになると思います。自分をハッピーにするものをテーマにみんなが情報発信するなどして、社内のインターナルコミュニケーションを促進するのも効果的ではないでしょうか。
これらの取り組みは、トップダウンで進めることも重要かと思います。私もSDGsを推進していく立場として、まずは自分たちの組織から働き方などを変えていかなければいけないと思いました。「言行一致」ですよね。社長をはじめとした経営層、管理職が率先して、自分がハッピーであることを大切にしていると意思表示をすれば、社内にも浸透が図れるのではないでしょうか。また、そういった企業姿勢を社外に発信するのもいいかもしれません。
日本の優れたことに目を向け、幸せを感じる
質問:個人が取り組める具体的なアクションがありましたら教えてください。
根本:仕事柄、世界のたくさんの国を見てきましたが、日本の優れているところってたくさんあると思うのです。夜でも安心して外を歩くことができますし、家に帰ってスイッチを押せば電気がつきます。蛇口をひねれば水が出るのも当たり前で、時間を指定してモノを届けてもらうことができます。
他の国と比べて、こんなに素晴らしい環境で生活ができているのに、それでも幸せを感じることができないとすれば、幸福であることに対する感度を育てたり、自分が幸せだと思える状態になるためのトレーニングをしたりする必要があるかもしれません。たとえば、ヨガをするときに、明るい風景とか緑の風景を思い浮かべるように、良いイメージを持つのは効果的だと思います。
また、最近では推し文化に代表されるように、その存在があるおかげで自分ががんばれるもの、つらい気持ちになったときに、それを見たり触ったりすることでテンションが上がるもの、苦しい環境からちょっと一歩引いたところで自分を高めてくれるものがあるといいですね。
その対象は、人それぞれだと思うのですが、私の場合はアートです。普段、私はアート作品が載っている日めくりカレンダーを使っていますし、美術館に行って1時間、好きな作品を眺めていると、その日1日、とても幸せな気分になれます。書店などで美術書や海外の雑誌などを見ているだけでも気持ちがすっきりします。あまりネガティブなスパイラルに入ってしまわないように気をつける際のツールにもなっています。
普段の仕事の中で、私たちができること

質問:国際幸福デーにちなんで、幸せなキャリアの作り方について何かアドバイスがあればお話しいただけますか。
根本:SDGsの8つ目の目標「働きがいも経済成長も」の中に、「ディーセントワーク」(decent work=働きがいのある人間らしい仕事)が掲げられています。働きがいのある仕事をして、個人の人権も守られ、適正な対価を得る。がむしゃらにがんばるのではなく、ワークライフバランスを保ちながら、自分らしさが追求できる仕事をする。そんな働き方を大切にしてほしいですね。
そのためにも、仕事の中でどんなふうにキャリアアップしていきたいのか、どうスキルアップして、そのためにどんなトレーニングが必要なのか、自分なりの信念も持って仕事に向き合うことが大切でしょう。
そして、自分でイメージしたことを、言葉にしてみることも、私自身の経験から有効だと思います。口に出してみる、紙に書き出してみることは、ありたい自分に近づく最初の一歩だと思います。自分は何ができて、次に何をやりたいのか、自分の比較優位、強みは何なのかを整理し、具体的なアクションに落とし込んでいくと効果的かと思います。
編集後記
今回は、国際幸福デーについて国連広報センターの根本さんにお話しを伺いました。実はこのインタビューの前に、「働くの明日を考える」というコンセプトのサイトを運営する私たち編集部内で、国際幸福デーに向けて何ができるかを話し合い、その結果、国際幸福デーの存在を多くの人にしってもらうために、インタビュー記事を掲載することに決まりました。
根本さんのお話しにもあったように、国際デーにはそれぞれの想いが込められており、国際デーをきっかけに何かを考えたり行動したりすることが大切です。この記事を読んでいるみなさまも、国際幸福デーをきっかけに普段の生活を振り返り、自分にとっての幸せとは何か、どのような行動ができるかを考えるきっかけになれば幸いです。