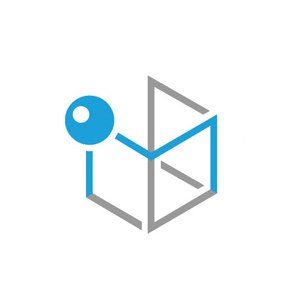副業・複業がもたらすキャリアの新たな可能性と新規事業創出のチャンス(サイボウズ株式会社)
目次
副業・複業に高まる社会的な注目
副業によって、社員のキャリア形成を後押しする企業が増えている。2022年には厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改正した。人材不足の影響も追い風となり、これからますます受け入れる企業の割合は高まるだろう。
さらには複数のキャリアを並行して進める「複業」にチャレンジする人材も現れている。今回は、社員の副業・複業導入をいち早く取り入れ、新たな働き方のモデルを社会に提示してきたサイボウズ株式会社の取り組みを紹介する。
サイボウズでは「100人100通りの働き方がある」とし、社員一人ひとりの自律したキャリア形成を支援している。今回は入社以来、幅広い業界・業種での複業を実現している中村龍太さんと複業経験から新規事業を立ち上げた前田小百合さんに、複業と本業による相乗効果について、詳しく伺った。
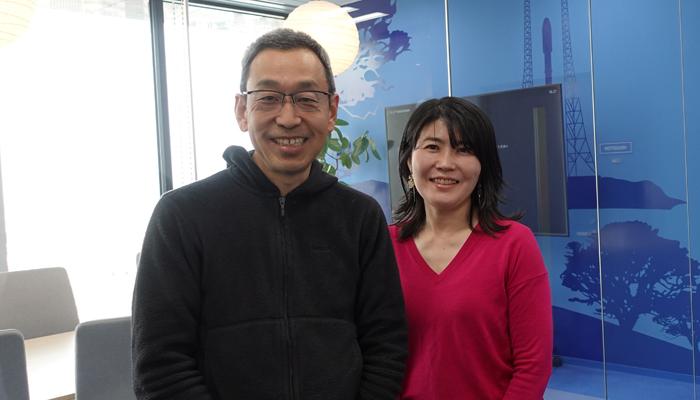
サイボウズ株式会社
設立:1997年
事業内容:グループウェアの開発、販売、運用
【画像左】執行役員 兼 ソーシャルデザインラボ所長 中村 龍太 さん
日本電気、日本マイクロソフトを経て、2013年にサイボウズ入社。同時に中小IT企業に業務委託として参加。副業のキャリアをスタートさせる。2015年にはNKアグリの提携社員として農業に従事。現在はいくつもの仕事を掛け持つ、複業エバンジェリストとして活躍中。
【画像右】ソーシャルデザインラボ サイボウズの楽校 校長 前田 小百合 さん
外資系大手IT企業でエンジニアとして活躍後、サイボウズに入社。未経験からスタートし、ソリューション営業を経験。サイボウズ製品「kintone」の活用提案に携わった後、ソーシャルデザインラボ(旧社長室)へ異動。現在は新規事業として立ち上げたオルタナティブスクール「サイボウズの楽校」に尽力している。
副業から複業へ。サイボウズが引き出した「人材の価値」

中村さんは他の社員に先駆けて、入社当初から副業をされていたそうですね。副業にチャレンジしようとしたきっかけは何だったのでしょうか?
中村:「最初は家族のためで、収入アップが目的でした。日本マイクロソフトからサイボウズに転職したのは2013年。最終面接を受けた際に『年収ダウンするし、どうしよう』と思ったんです。
すると『副業で稼ぐという手段もあるよ』と教えてもらい、もちろんそうした手段があることは知っていましたが、本気でやろうとは考えもしませんでした。そこで『今までのキャリアで培ってきた経験の延長でできる、職種でやってみよう』と決め、中小IT企業のシステムコンサルタントを副業として務めることになったわけです。
当時は週に1日だけ副業を入れて、がむしゃらにやっていましたが、たった1日だけでも期待以上の成果を求められるので、プレッシャーもありました。副業先でチームの立ち上げをゼロから行ったため、それなりに時間もかかりましたね。」
そこからどのように業務の幅を広げ、パラレルワーカーとなっていったのでしょうか?
中村:「きっかけはITを活用した植物工場を展開する『NKアグリ株式会社』への参加でした。当時、私は業務委託としてIoTを活用したスマート農業を進める役割を担うことになったんです。
義実家が農業をやっていて、米づくりは以前から手伝っていましたから農業には馴染みがありました。当時、農作業を楽しむクラブを作って楽しくやっていたところ、NKアグリの方と知り合って、『サイボウズの主力製品であるクラウドサービス“kintone(キントーン)”を使ったら農業のIoT活用がさらに促進されるのでは?』と話したんですね。
1か月後、本社のある和歌山で詳しく教えてもらいたいと声がかかり、そのクラウドサービスを導入してデータ管理をすることになりました。
他にも副業先だった中小IT企業のオフィスのそばに美味しいパエリア屋さんがあり、そこのシェフに『パエリア用の国産米を作れませんか?』と相談されて、チャレンジすることに。そうして自然と副業から“複業”へと、変わっていきました。」
副業先での実績を本業、さらには別の副業先へと広げて「複業」に発展させていったのですね。それぞれの仕事が影響しあい、新たな価値が生まれているのでしょうか?
中村:「自分のやりたいこと・やってみたいことを、それぞれの場に提供しているだけです。
サイボウズの企業理念は『チームワークあふれる社会を創る』。チームのメンバーが共通の理想に向かって役割分担をしながら協働し、働く人の幸福度とチームの生産性が高い状態にあるチームワークを目指しています。
それを別の環境下でもやってみようとしているんです。『こういうリスクがあるなら、こう動けば良さそう。そうすれば一石三鳥…いや一石四鳥かも』とあれこれ考えて行動し、結果として新たな価値が生まれているのだと思います。」
周囲の方への影響はいかがでしょうか?上司の様子を見て、部下である前田さんはどのように感じていますか?
前田:「中村さんは上司であり、人生の先輩でもありますから『いくつになってもワクワクする仕事ができる』という可能性に希望を感じています。
私の前職は大手IT企業なのですが、階層型組織の中でキャリア形成に対して後ろ向きな社員も多く『あと10年で逃げ切ろう』と語る先輩もたくさんいました。ですから中村さんのようにワクワクする楽しい仕事を自ら探し、実現していることに人として勇気づけられます。
部下としても、いろいろな気づきがありますね。自分では考えもつかなかった視点に、思考を広げてもらっています。それは複業を通じて培った経験をお持ちの中村さんだから、できるのだと思います。」
前田さんは、サイボウズ以外に副業・複業の経験をお持ちなのでしょうか?
前田:「2023年11月より、杉並区の教育委員を務めていて、我が子が中学生の時にPTA会長を務めたのがご縁で、杉並区教育委員会主催の会議に月2回ほど出向き、アドバイスやディスカッションをしています。
この委員を務めるには、杉並区長の任命が必要で、私がサイボウズ社員であること、IT活用に関する忌憚のない活発な意見交換を期待していただき、指名いただいたようです。」
多様な働き方が新たな企業価値向上にどうつながるのか

新規事業として2023年12月にオルタナティブスクール「サイボウズの楽校」を立ち上げることになったそうですね。新規事業の創出に、複業経験の影響はありますか?
中村:「もちろん、影響はあると思います。私たちの所属する部署『ソーシャルデザインラボ』には、社会課題をITによって解決するというミッションがあります。これまでにも災害支援、虐待防止支援などの取り組みを実現してきました。その延長で、私自身が学校教育に非常に興味を持っていたんです。
複業をしていると、さまざまな業界や地域社会の課題が耳に入ります。学校教育が気になり出したのは、小学校でプログラミング教育が必修化されると知った頃でした。いざプログラミングの授業が始まったものの、先生方が忙しすぎてなかなか対応しきれていないという学校もありました。
そうした現実を知ってどうしたものかと思っていた時に、経済産業省が主導している教員の働き方改革プロジェクト『学校のBPR(Business Process Re-engineering)』の実証事業に参加することになったんです。
このプロジェクトには、前田さんも同じチームメンバーで入ってもらいました。まずは教育現場における業務の実態を把握し、効率化できるところや改善点を模索していきましたね。
そのプロジェクトで、多くの学校の先生や教育委員会に話を聞き、学校内の見学もしました。そのような中、不登校生が通う教室に入る機会がありました。生徒の様子を見ているととても楽しそうに学んでいるようには見えない。配られたプリントを前に、ただ話をしているだけの授業で良いのだろうかと考え込んでしまいました。
また、年々増えていく不登校児童生徒数の数も気になっていました。『(当時)20万人もの子供が学校に行かず、何をしているんだろう?』と地元のフリースクールを訪ねました。ちょうど、法人化を目指しており、フリースクール運営に関わることになりました。このフリースクール運営も、もちろん複業です。
結果として、これは地域社会全体の課題だと確信し、それならばサイボウズらしい学校をゆっくり作ろうと思い、前田さんを巻き込みました。」
前田:「最初は『サイボウズで学校を作る』と聞いてもイメージが湧きませんでした。破天荒すぎて『どういうことなんだ?』と。私の中からは出てこない発想でしたので、驚きました。
ただ、私の子供もコロナ禍で学校に行けなくなった時期があって、不登校の問題は人ごととは思えなかったんです。私たちは楽しく、自分らしく仕事をしているのに、学校はどうだろうか。先生も生徒も、楽しく、自分らしく学びを深めているのだろうか。そんなことを改めて考える機会がありました。
もう少し、子供たちが自分らしさを大切にできる新しい学校を作って、我が子も入れると良いな──そんなことを思いながら、事業化に向けて動き始めたんです。」
サイボウズにおける「複業と本業の関係性」とは
個人が楽しく働き、キャリアアップをすることで、地域社会や他の企業にも好影響を与えているのですね。サイボウズの他の社員も、同じような取り組みをされているのですか?
前田:「どんどん増えていますね。社員は複業を始める際に、まず専用のアプリを確認します。そして、複業の種類にチェックをしてもらい、サイボウズが指定する10種類のいずれかに当てはまる場合は、登録してもらいます(当てはまらない場合は登録不要)。
このアプリに登録された複業は原則全社員に公開されています。複業の種類ごとにガイドラインが表示される仕組みになっており、注意点やリスクを本人が理解した上で自己承認します。
中村:上司や人事の許可ではなく、社内イントラ上で、複業をするうえでの注意点などを確認し、自分でその対処方法を決めて承認する点がポイントですね。複業が登録されると、上長やチームの関係者には、通知が届く仕組みになっています。上長や会社側からは必要に応じて助言をすることはありますが、基本的には本人にリスクを判断してもらいます。
もちろん、サイボウズにとって不利益になる仕事であれば本人に説明責任が発生しますが、この仕組みは、他社にはない独自のものだと思います。
複業はあくまでも個人的なもので、たとえば飲み会に行くのと一緒、という感覚です。お酒を飲みすぎたら、翌日は仕事にならない。それでは困りますよね?サイボウズの業務に支障をきたさないという前提のもと、相談しやすい仕組みは整えつつも、基本は、個人の裁量に委ねます。その結果、複業が社内に浸透するようになりました。」
複業が社内に浸透した結果、サイボウズにはどのようなメリットがあったと感じていますか?
中村:「私自身の例で考えると、今まで経験してきた複業先で、自社のクラウドサービスを使って多くの課題を解決できたことでしょうか。特にコードが書けなくても、文系でパソコンに触れた機会が少なくても、業務アプリ開発の支援実績があります。
『ITを導入すると業績が3割上がります』と数字で言われるよりも、具体的なストーリーを語れる方が心に刺さるものです。『サイボウズのクラウドサービスを導入したら、登校した児童の安否確認が簡単にできますよ。そうすれば先生も安心ですよね』と語れれば、サイボウズにも新たな事例が蓄積されます。
自社の売上拡大と、事例の蓄積が得られたこと。これは大きなメリットでした。」
複業を通じた実践から見えてきた「次に目指したいキャリア」
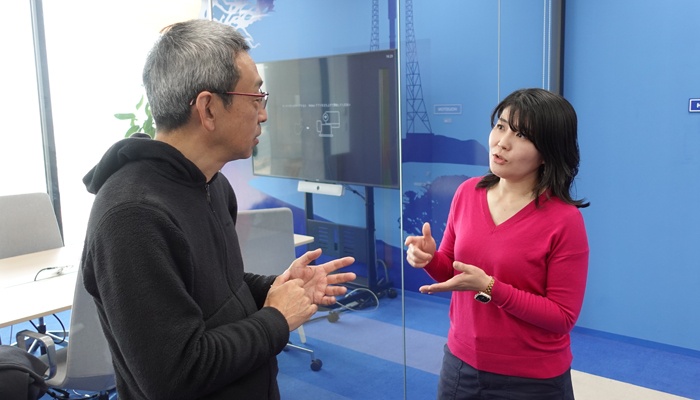
将来を見据えた今後の展開やチャレンジしたいことについて教えてください。
前田:「現在は新規事業としてスタートした『サイボウズの楽校』を2023年12月に開校し、試行錯誤中です。元小学校教員のスタッフがカリキュラム作成と授業を担当しています。私の肩書きは『校長』ですが、一緒に教室で授業をサポートしたり、事務をしたりと忙しく兼務しています。保護者との連携や経理、生徒募集のためのSNS運用までマルチに活動中です。
今後の目標は、保護者と子供たちと一緒にコミュニケーションを取りながら学校を作っていくこと。スクール内で何をして過ごし、どんな学びを深めているのかを関わる人で共有しながら学びの場を大切にしていきたいです。
同時に、学校の外にいる方たちに、“サイボウズの楽校に関わってくれるチームメンバー”として参加してもらえる環境づくりも進めていきたいです。何かしら関わりたいなと思ってくれている方が結構多いと感じています。さまざまな立場の方に参加していただければ、子どもたちの学びが広がる、私たちスタッフも視野が広がる、いいことづくしです。」
中村:「私はいま夢中になっていることをやるだけで、5年先の未来目標も怪しいですが…それでも事業成功に向けて自社の売上を伸ばし、サイボウズの楽校も軌道に乗せたいですね。安心して選択できる学び場の創出には、力を入れたいです。
と言うのも、私が今までに経験してきたキャリアをすべて包含すると『学びの場の創出』につながると思っているからです。ITや農業、パエリア、子供たち。こうしたテーマで学びの場を提供できるんですよね。
複業を通じて外の世界に出たからこそ、見えた景色や課題もたくさんありました。ビジネスにおける成功者が意思決定プロセスとして実践している『エフェクチュエーション』の本を出版したのも、その一つ。子供だけではなく、保護者や保護者を取り巻く産業界の人々すべてに学びを提供し、できるようになってほしい。そして一度学んだら“先生”になって、次の誰かに教えてあげてほしいと思います。」
編集後記
収入アップのために始めた副業が、いつしか自分の可能性を拡張する「複業」へと変わっていく。そんな「理想的なキャリアの歩み」が凝縮されているように感じた取材でした。
注目すべきは、この複業が「1人の社員の個人的な体験」に閉じていない点です。サイボウズでは「100人いれば100通りの人事制度があってよい」との方針を掲げており、公平性よりも各自の個性を重んじる多様な働き方を実現してきました。
副業・複業も多様な働き方を推進するための取り組みとして、他社に先駆けて解禁しています。個人を尊重する企業文化のもとで、気軽に副業・複業を始められるようにしたほか、さまざまな人事制度を導入した結果、多くの社員の「働くモチベーション」が上昇し、離職率は28%から4%へと低下(※)したそうです。
※参照データ:中小企業庁
個人と組織、双方にとってメリットの多い「複業」を実践していくためには、まず「やってみようか」と立ち上がる風土づくりがポイントになるのかもしれません。
執筆:林 美夢