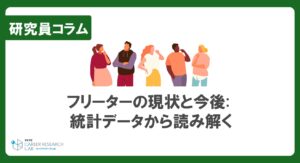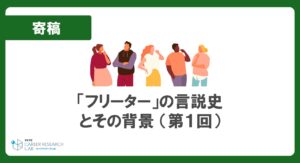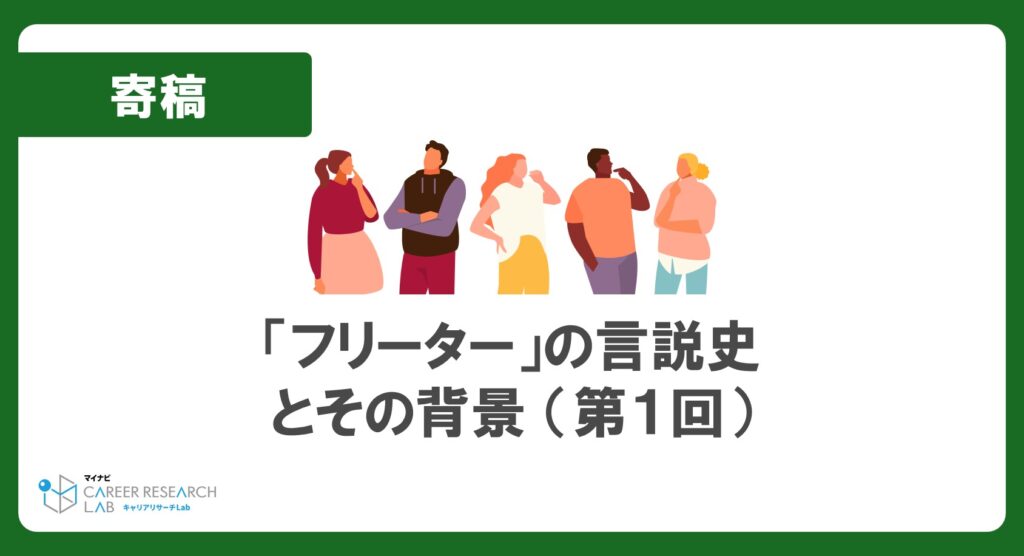フリーターの現代的課題と「オルタナティブな生き方」の可能性-奈良県立大学 地域創造学部 教授 梅田直美氏
本稿は「『フリーター』という生き方を考える」という連載企画の第4回目だ。前回に引き続き、奈良県立大学 地域創造学部 教授 梅田先生に解説していただいた。

梅田 直美(奈良県立大学 地域創造学部 教授)
1973年生まれ。専門は社会学・社会福祉学。「孤独・孤立」についての言説史研究と、「生きづらさ」を経験した人が自分の経験や問題意識をもとに起業したソーシャルビジネスに関する実践研究を行っている。近年は、学ぶこと・働くこと・楽しむこと・つながること・支えあうこと…などの営みが乖離しないオルタナティブな生き方を探る学びのコミュニティづくり(「山岳新校」など)を実践するとともに、そのベースとなる理論・思想を探究するため「撤退学」研究に取り組んでいる。著書に『「孤独・孤立」の歴史社会学』(単著、晃洋書房、2025)、『撤退学の可能性を問う』(共著、晃洋書房、2024)、『山岳新校、ひらきました―山中でこれからを生きる「知」を養う』(共著、H.A.B、2023)、『子育てと共同性-社会的事業の事例から考える(OMUPブックレットNo.62)』(編著、大阪公立大学共同出版会、2018)などがある。
<新著>梅田直美著『「孤独・孤立」の歴史社会学』(晃洋書房、2025年2月28日発売)
目次 [もっと見る]
はじめに~前回の振り返り~
前回は、フリーターの言説分析を通じて、社会システムに適合的な「標準」の生き方から外れることをめぐる人々の認識枠組みの変容の過程をみていきました。今回は、その認識枠組みを超えて生き方の選択肢をもっと広げていくためにはどうすればいいかを、「オルタナティブな生き方」の可能性と課題に焦点を当てて検討します。
戦後の日本社会では、「学校に行き、学校を卒業したらすぐ定職に就き、定年まで働く」という「標準」の生き方があり、大多数の人がこうしたライフコースを歩むことで社会システムが維持されてきました。
しかし、社会情勢や個人の意識の変容などを背景に、これまでの「標準」のライフコースを歩まない人、歩むことが困難な人が増えています。その一方で、日本社会ではいまだ「標準」のライフコース規範が根強く、そこから外れることに対する不安や偏見が残存しています。また、正規就労と非正規就労の格差などの現実的な問題もいまだ解消されていません。
こうした状況のなか、近年、これまでの「標準」からは外れていながらも豊かで創造的な生き方(ここでは「オルタナティブな生き方」と呼びます)を実践する人々への注目が高まっています。まだ少数派ではありますが、それらの人々が自らの実践とその背後にある価値観などを発信し、それに共感を抱く人が確実に増えています。
また、そうした生き方が、地方創生や自然再興、生きづらさの解消など社会課題への対応につながり得ることもわかってきました。個人にとっても社会にとっても、「オルタナティブな生き方」によって可能になる未来、解決されうる問題が多々あるのです。
では、これからの日本社会で、「オルタナティブな生き方」の価値を共有し生き方の選択肢を広げていくためにはどうすればよいのでしょうか。この記事では、フリーターという生き方についての考察を手がかりに、そのヒントを探ります。
フリーターという概念は1980年代に登場し、「自由で新しい生き方」として注目されました。しかし、バブル崩壊後からフリーターの社会問題化が進み、2000年代には若者の甘えや自立心のなさといった若者批判に用いられる概念となりました。
その後は、若者批判への対抗言説の形成を経て、フリーターは就業構造の問題に起因する雇用不安定化や格差の象徴となりました。こうして2010年代までに形成されたフリーター言説は、現在においても、深まり続ける格差と貧困の「危機」を現す言説として引き継がれています。
一方で、2010年頃からは新たな言説がみられるようになりました。フリーターやニートという言葉が指す状態を含めた、戦後日本社会で「標準」とされてきた生き方や価値観とは距離をおいた「オルタナティブな生き方」の実践が注目され、その可能性を探ろうとする言説が現れてきたのです。
「オルタナティブな生き方」を実践する人々
実は、2010年代に入る以前にも、新聞の読者投稿欄などでは当事者の声を中心にフリーターという生き方をポジティブに捉える言説は存在し続けていました。ただし、専門家による言説や政策的言説ではフリーターを問題視するものが圧倒的多数で、フリーターをポジティブに捉える声はほとんど拾い上げられませんでした。
ところが、2010年代になると、若い世代の「当事者」自身が、書籍やブログなどを通じて自らの経験を基にオルタナティブな言説を形成し始めました。
仕事は人生を豊かにするための一つの手段に過ぎない
その代表的なものの一つが、「日本一有名なニート」と称されたpha氏による一連の言説活動です。pha氏は、著書『ニートの歩き方―お金がなくても楽しく暮らすためのインターネット活用法』(技術評論社、2013)において「人間は働くために生きているのか」と問いかけ、「この本は、かつての僕と同じように『人間はちゃんと会社に勤めて真面目に働いて結婚して幸せな家庭を作るのが当たり前の生き方だ』という社会のルールにうまく適応できなくてしんどい思いをしている人に向けて、『別に働くことだけが人生じゃないし、ニートも一つの選択肢としてありなんじゃないか?』ということを伝えようと思って書いたものだ」と言います。
さらに、日本でなぜ若者がこれほど生きづらさや閉塞感を感じているのかと問い、「それは多分、日本の経済がまだ成長しているころに作られたルールや価値観が生き残っていて、それがみんなを縛っているせいなんじゃないかと思う」と述べています。
「一億総中流」という幻想は壊れ、正社員になることさえ困難であり、一流とされている会社が突然倒産するなど会社に身を預けていれば安心だという時代は終わり、知人のなかには新卒ですぐに大企業に勤めたが過労で半年後に自殺してしまった人もいる。
そうした状況に対しpha氏は、「仕事なんて命に比べたらどうでもいい。人間は仕事のために生きてるわけじゃないし、仕事なんて人生を豊かにするための一つの手段に過ぎないんだから」「でも、会社という組織に属しているとその組織の雰囲気に縛られて、そういう人生の基本的なところを忘れてしまうことがある。ちゃんと働かなきゃいけない、真っ当に生きなきゃいけない、他人に迷惑をかけてはいけない、といった強迫観念がみんなを縛り付けているせいで、日本の自殺者は年間3万人もいるんじゃないだろうか」と問題提起し、「ニート」と称される生き方でも幸せに暮らせることを自らの実践を通じて発信しています。
このpha氏の問題提起は注目を集め、新聞等のメディアでも活発に議論されました。pha氏はその後も『持たない幸福論』(幻冬舎、2017)、『ひきこもらない』(幻冬舎、 2017)、『パーティーが終わって、中年が始まる』(幻冬舎、2024)など執筆活動を続けています。
「ナリワイ」という生き方の実践
また、フリーターやニートという概念・言葉にとらわれることなく、これまでの「定職に就く」賃労働とは異なる働き方・生き方を実践・発信する人々も増え始めています。そのひとりが、「ナリワイ」を提唱し実践する伊藤洋志氏です。
伊藤氏は、『ナリワイをつくる―人生を盗まれない働き方』(東京書籍、2012/筑摩書房、2017)、『イドコロをつくる―乱世で正気を失わないための暮らし方』(東京書籍、2021)などで知られ、「資本主義社会でのゲリラ作戦」として、「自分の時間と健康をマネーと交換するのではなく、やればやるほど頭と体が鍛えられ技が身につく仕事、やればやるほど仲間が育つ仕事」を「ナリワイ」と呼び、その生き方を自ら実践しながら社会に発信し続けています。
伊藤氏は、普段は東京で暮らしながら、農作物の収穫時期にあわせて全国各地の農山村をまわり収穫を手伝うと同時に直販などもする「遊撃農家」、古くなった家などで床張りをする技術を合宿などで楽しみながら学ぶ「全国床張協会」など、さまざまな「ナリワイ」を考案し自ら実践しています。
また、pha氏と共に、熊野でシェアハウスをつくった実体験を元に『フルサトをつくる-帰れば食うに困らない場所を持つ暮らし方』(東京書籍、2014)という本を世に出し、「都会か田舎か、定住か移住かという二者択一を超えて、もう一つの本拠地をつくろう」と提唱しています。
こうした営みは、自ずと都市と中山間地域の接続、空き家の活用、生活者自らが生きる力を養う姿勢と技の学び合いの場の創出、仕事と生活と遊びと交流の融合、「フルサト」「イドコロ」を持つことによる孤独・孤立への対応など、現代社会の諸課題に応えるものとなっています。
そのほか、『年収90万円で東京ハッピーライフ』(太田出版、2016)の著者である大原扁理氏は、自らの生活スタイルを「隠居生活」と呼び、「世間の価値観」やお金に振り回されない自由な生き方・働き方を自分で地道に見つけていくことの重要性を数々の著書・ブログ等を通じて示しています。
2020年には、石井あらた氏らによる「山奥ニート」と称する限界集落での生活実践が『「山奥ニート」やってます。』(光文社、2020)という書籍やメディアで報道され注目を集めました。
「オルタナティブな生き方」と新たな価値創造の可能性
社会の諸課題を解決する可能性
以上の実践はいずれも先鋭的ではありますが、それゆえに社会的インパクトが強く、「定職に就く」ことによって一定の収入を安定的に確保する生き方をしていなくても幸せな暮らしは可能であるという言説を普及させました。また、注目すべきは、これらの実践のいずれもが、社会の諸課題を解決する可能性を示している点です。
たとえば、「山奥ニート」は限界集落に活力を生み出し、「ナリワイ」や「イドコロ」の創出は都市と中山間地域を接続すると共に仕事・生活・遊び・交流の融合を実現させ、「隠居生活」は誰もが実践可能なミニマルなライフスタイルの可能性を示しています。こうして若い世代の「当事者」らによる言説が広がった背景の一つには、SNS等の普及により一般の人が自らの考えなどをダイレクトに社会に発信しやすくなったことが挙げられます。
しかしそれだけではなく、社会情勢や個人の意識の変容、将来の不確実性の高まりに伴い、もはや「標準」のライフコースを歩むことが困難であるにもかかわらず、辛さを我慢し心身に不調をきたしてでもそのライフコースから外れないように闘い続けることに疑問を持つ人が増えたことが背景にあると考えられます。
賃労働ではない「仕事」「活動」は山ほどある
戦後日本社会では、一定数の人々が持っていた自由に楽しく働きたい、生きたいという志向は抑え込まれ、誰もが「定職に就いて生涯安定して働く」ためのレールに乗る競争から外れないよう忍耐を強いられてきたとも言えます。
しかし、近年生まれている実践は、その抑え込み否定されてきた志向、生き方こそが、今世界が直面する諸課題の解決につながりうる創造的な生活実践を生み出す可能性を持っていることを示唆しています。
また、これらのオルタナティブな生き方の実践は、賃労働ではない「仕事」「活動」は社会に山ほどあり、それらの「仕事」「活動」を大事にすることによって、社会の人々のあいだから失われていると嘆かれてきた、豊かな知恵と教養を培ったり分けあったりする時間、そこから生まれる自律的で自給的な「生きる力」、ケアなどの支え合いのための時間的・精神的ゆとり、社会の多様な人々とのつながり、自然との共生、生きていくことの楽しさや幸福感といった価値を再び創造・共有する可能性を持っています。
「オルタナティブな生き方」を選択する上での現代的課題
生き方をシフトすることのハードルの高さ
では、なぜこのように自由で創造的な生き方が実践され、社会に発信されているにもかかわらず、多数の人々にとって、生き方の選択肢は限定的なままなのでしょうか。
ここで検討すべき問題の一つは、日本ではオルタナティブな生き方を「社会に適応できない人の生き方」や「特別な思想にもとづく生き方」など、「普通」ではない生き方と捉え、自分とは切り離してしまう傾向があることです。そのため、オルタナティブな生き方をしている人々に憧れる人や、その理念に共感する人ですら「自分には無理」「自分には関係ない」と思い込んでしまうことが多いのです。
筆者は、2022年から「山岳新校みちのり」というお互いの生き方や価値観などをシェアして学びあう場をひらいています。その学び合いに参加した方々からお話を聞いていると、オルタナティブな生き方の価値を理解し、そのような生き方をしたいと思っても、「自分には出来ない」「一歩を踏み出せない」などと感じていると言います。その背後にあるのは、理想と現実は違う、現実の社会はまだまだ変わらないからどう折り合いをつければよいかわからない、といった意識だと言います。
このように、生き方をシフトすることにハードルの高さを感じるのは、今の日本社会の多数の人々に共通することと思われます。たとえば、いきなりナリワイの伊藤氏のような生き方をしてみよう、と言っても無理な話です。しかし、そうした実践者らも初めから「特別な人」だったわけではありません。一人ひとりの、まさに長いみちのりのなかで、困惑・葛藤・挫折・怒りもあれば楽しく嬉しい運命的な出会いもあり、紆余曲折のなかでの今の生き方です。
「ありのままの生」にはモデルとなる「正解」がない
また、「オルタナティブな生き方」という言葉は、一人ひとりが「標準」の生き方にとらわれず生きたいように生きられる、ありのままの生そのものが尊重される社会にしていくことを企図して用いているのであって、当然のことながら「正解」があるわけではありません。
pha氏や伊藤氏といった言説活動をリードしている人々の生き方や価値観を「オルタナティブな生き方」の条件や典型とみているわけではありません。しかし、「生き方のモデル」がまるで「正解」のように示され、それにあわせて生きることが良しとされてきた社会では、自らの歩みや選択に自信が持てず、生きていく上でのさまざまな岐路において何を基準にどういった選択をしていけばよいのか悩みや不安を抱える人も少なくありません。
この問題への対応としては、「オルタナティブな生き方」すなわち「標準」とは異なるが多様で豊かな生き方をしている数多の人々と出会い、対話を通じてその生き方や背後にある価値観とふれながら自らの生き方をゆっくりと考えることが出来る場や機会を社会の各所に生み出していくことが重要であると考えます。
「休むこと」「じっくり考えること」への不寛容
ここで浮かび上がってくるもう一つの重要な問題は、日本社会では「休むこと」や「じっくり考えること」など、アクティブに利益を生み出す行為をせずに過ごすことに対しての寛容さ、ゆとりがないことです。特に、働けるはずの年代の人々に対しては、「何もしないでゆっくりする」ことはもちろん、「じっくり生き方を考える、見直す」といった行為に対しても、不寛容です。
ボランティアや留学、育児・介護などのケアといった活動や労働をしていると一定の層には理解されますが、それでも、利益を生み出す活動、つまり、いわゆる賃労働でない限りは、「生産性」に欠けるとして認められにくい風潮があります。このように日本は寛容さがない社会、ゆっくり休んだり考えたりする余裕がない社会です。この問題が、日本社会で生き方の選択肢がなかなか広がらない原因の一つではないかと筆者は考えています。
近年、「学び直し」「リカレント教育」といった言葉があふれていますが、その内容もキャリアアップのためのリスキリングが目的とされています。そうではなく、何歳でも、どのライフステージにおいても、ゆっくり、生きること、たとえば自分や他の人の幸福について、生と死について、自由と共同性について、人類と地球について、などのテーマについて学び対話し、生きていく上で大事にすべき価値やこれからの生き方を考える機会が得られるべきではないでしょうか。
またもちろん、「標準」とは異なる生き方を選択した際につきまとう貧困や孤立のリスクも重要な問題です。こうした現実と向き合わないまま、「多様な働き方」「オルタナティブな生き方」として、フリーターという生き方をポジティブに捉えることは、楽観的に過ぎると言わざるを得ません。これまですでに指摘されてきたように、正規就労と非正規就労の格差解消、家族や職場以外の多様なつながりと活動の場の創出などに、引き続き取り組むことも不可欠です。
まとめ
以上のように、オルタナティブな生き方には新たな価値創造の可能性が見出される一方で、現代の日本社会ではその選択を困難にしている問題が多々残されています。
しかし、今ようやく、オルタナティブな生き方を「自由で楽しく豊かな生のスタイル」の一つと捉え、そうした生き方を選択しやすい社会に変えていく機運が高まっています。近年、生き方の選択肢を広げていこうとする動きは、個人レベルでの実践だけでなく、社会全体に見出されます。
たとえば、大ベストセラーとなったリンダ・グラットンとアンドリュー・スコットの著書『LIFE SHIFT(ライフ・シフト)-100年時代の人生戦略』(東洋経済新報社、2016)では、「人生100年時代」の生き方として、「教育→仕事→引退」という「3ステージ人生」から、学びや仕事や社会活動などステージの移行を数多く経験する「マルチステージ人生」への移行が示されています。
この「人生100年時代」のライフコースのあり方については、well-beingの実現という目標とあわせて社会の各所で議論されるようになりました。また、「複業」「多拠点居住」「セカンドキャリア」といった概念も普及しつつあります。このような動きがみられるなかで、いかに生き方の選択肢を広げ、いかに生きやすい社会に出来るかは、私たち自身の日々の意識や行動にもかかっています。
戦後何十年にも渡り構築されてきた社会システムや社会規範は、すぐには変わらないかもしれません。社会システムが変わらない限り、個人レベルでの認識枠組みや生き方の転換によって社会の変革を企図するには限界があります。
しかし、社会システムがなかなか変わらなくても、すでに生き方を変え始めた人々がいます。オルタナティブな生き方の実践者らが共通して示唆しているのは、社会システムそのものがすでに時代や人々の生き方の変化に対応できないものとなっているにもかかわらず、なかなか変われないのであれば、そのシステムに自分の生き方を合わせる必要はない、自分が大切にしたい価値にもとづき、自律的に生き方を選択し歩んでいけばよい、ということではないかと考えます。
また、オルタナティブな生き方を、社会に適応できない人、特別な思想を持った人の生き方としてみるのではなく、近代以降の「標準」の生き方や価値観を問い直し、環境・エネルギー問題や人口の減少と集中、格差拡大と分断、孤立などの現在世界が抱える諸問題の解決につながり得る創造的な生き方として捉え、その可能性を探っていくことも重要であると考えます。
フリーターという生き方についても、それを単に「定職に就けない人の生き方」と捉えて終わるのではなく、そこに潜む社会の構造的問題や当事者の事情と向き合いつつも、一方でそこに個人にとっての今・ここの幸福や未来に向けての創造的な価値や希望を見出し、議論・アクションしていく、こうした営みが今求められるのではないでしょうか。
日本も賃金は上昇しているが、直近5年間の上昇率を他国と比較すると、上昇幅が小さいことがわかる。なお、アメリカの最低賃金は、連邦政府と各州政府によって定められており、連邦最低賃金は全国一律で、各州はそれを下回ることはできないが、上回ることは可能というルールのもと、各州の最低賃金は地域の経済状況や労働市場の状況により異なる。
【表1】を見ると2020年から2024年まで金額が一定になっているが、独立行政法人労働政策研究・研修機構の報告 によると、2024年1月には全米50州のうち、22州で最低賃金が引き上げられており、その金額もまた、最低賃金の7.25ドルを上回る金額で設定されている。