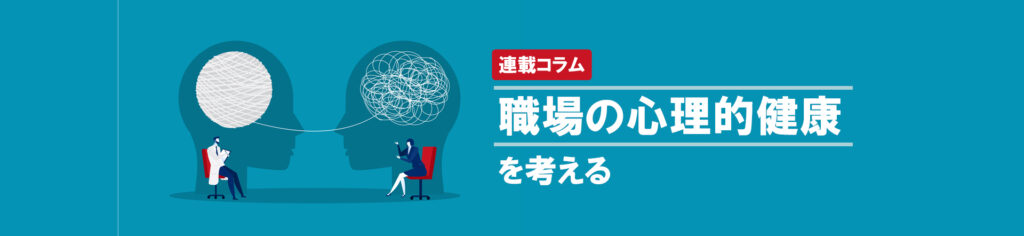上司がスマホの画面ばかり見ている~ファビングがもたらす組織への影響~
目次 [もっと見る]
はじめに
職場や日常生活のあらゆる場面で、目の前にいる人との会話よりもスマートフォンを優先してしまうことがあります。こうした行為は「ファビング」と名付けられ、近年、多くの研究者がその影響を調べるようになりました。
スマートフォンが登場する以前は想像しにくかったこの行為は、いまや仕事上の打ち合わせや雑談の中でも当たり前に起こり得るため、人間関係や精神面への懸念が高まっています。
企業としては、職場環境を円滑に維持し、生産性やチームワークを高めることが重要です。それにもかかわらず、ファビングによって従業員同士が「無視された」と感じたり、会話の質が落ちたりすれば、組織全体の活力にも影響しかねません。
本コラムでは、ファビングの定義から研究動向、さらに「ボス・ファビング」と呼ばれる上司によるファビングの悪影響まで、学術的な知見を整理しながら概観します。ファビングが増えてきた背景や繰り返されると強まる疎外感、相手がどのように不快感を覚えるかなどを中心に、職場コミュニケーションの文脈で注目すべき要素を紹介します。あわせて、この問題への対処策にも触れ、どのようなルール設定や取り組みが有効かを考えていきます。
「ファビングはとにかく悪い」という一面的な見方だけでなく、デジタル世代の価値観とのズレや、オンラインの情報をすぐに調べられるメリットなど、別の視点も踏まえて議論を進めます。
「仕事の連絡がスマートフォン中心で進むいまの時代に、すべてを一律に禁止すればいいわけではない」というジレンマも存在するはずです。本コラムが、ファビングをめぐる職場での課題を理解し、より良い人材マネジメントに生かす一助となれば幸いです。
ファビングとは何か
「ファビング(Phubbing)」とは、対面で会話している最中にもかかわらず、スマートフォンに意識を奪われて相手をないがしろにする行為を指します。語源は「電話(phone)」と「冷遇(snubbing)」を組み合わせた英語圏の造語で、スマートフォンが普及してから注目されるようになりました。
本人はただ画面をチェックしているだけかもしれませんが、相手からは「無視された」と受け止められる可能性があります。以前はマナー違反程度の認識しかなかったかもしれませんが、いまでは人間関係を壊す要素として本格的に研究されるようになっています。
ファビングが注目されている背景
2010年代の半ば頃からファビングを扱う論文が増加し、2019年前後にはさらに急激な伸びを示しています[1]。心理学やコミュニケーション論、教育・情報技術など、実に多様な領域で研究が進んでいます。
背景には、デジタル依存の拡大と、対面コミュニケーションの重要性を再確認する動きがあると言えるでしょう。対面の最中でもスマートフォンを見続ける新しい行動パターンが、コミュニケーションのあり方を変えていると認識され始めたのです。
ファビングによるリスク
多くの調査や実験では、ファビングをされた側が疎外感や排除感を抱くリスクが示唆されています[2]。話し相手に意識を向けてもらえない経験が続くと、自分の存在意義が小さく思え、憂うつや不安など心理的ストレスが高まることがあります。
さらに、その寂しさを埋めるためにSNSに過度に依存するなど、いっそうスマートフォンにのめり込むケースも指摘されています。こうした悪循環が人間関係を深く傷つける要因になり得ます。
実験的なアプローチによれば、ファビングが一度きりならまだ我慢できるとしても、繰り返し行われると「もう完全に無視されている」と強く受け止められます[3]。何度も画面に意識を移されれば、「相手は自分と話す気がないのだ」と捉えられ、気分が大きく落ち込んだり、対人関係への不信感が強まったりします。一度で済む場合とは心理的ダメージに差があると報告されています。
観察調査においては、ファビングを行っている本人がほとんど自覚を持っていない場合もあることが見つかっています[4]。本人にとっては手元をちらっと見るだけのつもりでも、相手からすれば「話を聞いていない」と感じられてしまうのです。
実際、ファビングを見た側が「打ち解けた会話ではなかった」と評価する事例が少なくありません。こうして、当事者の意識と周囲の受け止め方にギャップが生まれ、コミュニケーションの質が落ちてしまうわけです。興味深いことに、雑誌を読んでいる相手と比べて、スマートフォンを触っている相手のほうが強い不快感を誘発するという比較調査もあります[5]。
雑誌ならば学習や情報収集かもしれないと推測される一方、スマートフォンは何をしているか外からはわかりにくく、「ゲームやSNSでただ遊んでいるだけでは」と思われてしまいます。その結果、「今ここにいる相手よりもスマホの内容を重視しているのか」と感じ、強い疎外感を抱きます。
さらに、相手がファビングを行う頻度が上がるほど、会話そのものを「充実していない」とみなすことも明らかになっています[6]。何度もスマートフォンを見られると、「自分の話などたいして興味を持たれていないのでは」と感じるため、深い議論やアイデア交換が行われにくくなります。これは、ただの雑談でも重要な打ち合わせでも同様に観察されており、内容を問わず対話の質を下げる要因となり得ます。
ボス・ファビングの悪影響
上司が部下とのやりとりの最中にスマートフォンばかり見てしまうファビングは、「ボス・ファビング」と呼ばれています。
上司と部下の関係では、部下が上司からの承認やフィードバックを求める場合が多いため、通常のファビングよりも深刻な影響を与えやすいと指摘されています。職場の指揮系統においては、上司の態度がチームの意欲や協力体制を左右するからです。
部下の疎外感が高まる
ボス・ファビングが頻繁に起きる組織では、部下の疎外感が強まり、仕事への興味が失われる傾向が見られます[7]。上司が画面ばかり見ていると、部下は「自分の意見など聞いてもらえない」と感じ、相談や提案を諦めます。これが続くと職務におけるモチベーションが下がり、組織内コミュニケーションの活発さまで損なわれます。
研究では、上司のファビングによって職場で孤立感を覚える部下が増え、それがサイバーローフィング(業務時間中の私的なインターネット利用)を促す流れが示唆されています[8]。部下が「この環境で頑張っても報われない」と感じたとき、業務時間内の私的なSNS閲覧などへ逃避してしまうのです。上司から大切にされない印象が募るほど、チームとしての協働が成り立たなくなり、生産性だけでなく人間関係の質も悪化します。
部下のエンゲージメントが低下する
ボス・ファビングは部下のエンゲージメントの低下にもつながります[9]。ここにおけるエンゲージメントとは「仕事に熱意を持って取り組む度合い」ですが、上司からまともに向き合ってもらえないと感じるたびに、部下は「この職場で頑張る意味があるのだろうか」と疑問を抱きます。これが高じると、業績ばかりでなく組織への愛着や自発性までも損なわれます。
前向きなエネルギーが枯渇していく
さらに、心理的資本と呼ばれる「自信」「楽観」「希望」などの前向きなエネルギーが枯渇していくリスクも実証されています[10]。上司がスマートフォンに夢中で部下としっかり向き合わないと、部下は自身の価値を認められないと感じ、段階的にやる気を失っていくということです。特に長期的に続く場合、メンタルヘルス面にも影響を及ぼし、仕事のパフォーマンス全般を下げてしまいます。
承認欲求が強い部下ほど、ボス・ファビングによる悪影響が大きいとも言われます[11]。上司からの評価を得たい気持ちが強い従業員ほど、スマートフォンに気を取られている姿を目にすると「自分には関心を払ってもらえない」といっそう落ち込みます。結果、能力を発揮する機会を自ら遠ざけたり、組織への貢献意欲を失ったりするため、上司には注意が求められます。
ファビングへの対処法
ファビングへの対処にあたっては、スマートフォンを徹底的に排除するのではなく、対話の質を下げないルールづくりや意識づけが大切です。必要以上に制限すると業務効率を損ねる可能性もあり、まずはファビングが起こる心理や危険性を共有するところから始めると良いでしょう。
使用基準を明確にする
会議中や1on1ミーティングなどでは、スマートフォンを机上に置かない、通知をオフにするなど、使用基準を明確にします。人によっては「少しなら平気」と考えがちですが、誰かが操作を始めると周囲にも伝染しやすく、会話が途切れる要因になります。
すべての場でスマートフォンを禁止すると逆に不便を感じることもあります。そこで、「スマホチェックOK」の会議や時間帯を別途用意し、それ以外の場面では極力操作しないよう協力を促す方法もあります。メリハリをつけることで、従業員のフラストレーションを抑えつつファビングを減らせます。
上司が話を聞く姿勢を見せる
上司が自ら率先してスマートフォンを脇に置き、部下の話をしっかり聞く姿勢を見せましょう。ボス・ファビングが減れば、部下のファビングも自然と減り、対面コミュニケーションへの意識が高まります。上司自身が「スマホを見ない」見本を示すことが、効果的なアプローチだと言えます。
デジタル・デトックス・タイムを導入するのも一案です。「水曜の13時から30分はスマホなしで交流する」といった形で全員が同じルールを守れば、連絡への不安を覚える人も少なく、対話に集中しやすくなります。短時間でも、こうした取り組みを継続して行うと、スマホへの依存度が下がり、ファビングの抑止効果が期待できます。
ファビングは絶対悪か
とはいえ、ファビングをすべて悪とみなし、一切のスマートフォン使用を禁じるのも現実的ではありません。仕事の連絡に即応する必要があるときや、急ぎで情報を調べたい場面など、スマートフォンが有用なケースも多いからです。
デジタルネイティブ世代の若年層は、オンラインとオフラインを同時進行する「デュアル・アテンション」が自然に身についていることも指摘されています。そのため、世代間の感覚のズレを踏まえる必要があり、「ファビングは絶対に失礼」という価値観が通用しない場面もあるでしょう。
会話の途中で調べものを素早く行い、その情報を共有できれば業務効率が上がるというメリットもあり得ます。「いつ、どのように使うか」を事前に共有できているかどうかがポイントになります。
たとえば、双方がスマートフォンで情報を探し合い、それをもとに話を深めるのであれば、ただのファビングとは言えないでしょう。やっている内容を説明し合い、相手を置き去りにしていないことが伝わるならば、建設的な対話が実現する可能性もあります。
最終的には、「無視されている」と感じさせない工夫が鍵になります。スマートフォンを見つつも「聞いていますよ」「なるほど」などの反応をきちんと返せば、相手は自分を尊重されていると受け止められます。大切なのは、操作の最中も対面相手をないがしろにしていない、というシグナルを出し続けることです。
おわりに
ファビングは「画面ばかり見ていて失礼だ」という簡単な話にとどまらず、人間関係や職務上の信頼を損なう原因になり得ます。特に、上司が部下の前でスマートフォンに夢中になるボス・ファビングは、組織内のコミュニケーションを阻害し、エンゲージメントやパフォーマンスの低下につながると示唆されてきました。
にもかかわらず、デジタルツール自体は業務を円滑に進めるうえで欠かせない存在でもあります。したがって、すべての端末利用を厳しく制限するだけでは不便が多く、実効性も疑わしいところです。
そこで重要なのが、「必要に応じてスマートフォンを活用しつつ、対面でのコミュニケーションをおろそかにしない」仕組みづくりです。会議中のスマホ使用を最小限に抑えるルール、上司が率先して端末を手放す姿勢、デジタル・デトックスの時間帯など、導入できる施策はいくつも考えられます。
また、世代による感覚の違いを踏まえ、ファビングへの考え方を共有し、互いに配慮し合う文化を育むことも求められます。企業としては、職場の心理的安全性や人間関係の円滑さを保ちつつ、新しい働き方に合わせた柔軟なルールを模索する必要があります。
ファビングが蔓延すれば、本人たちの自覚のないままコミュニケーションとモチベーションが少しずつ蝕まれていくかもしれません。そうしたリスクを抑え、より良い組織づくりを進めるためにも、ファビングの問題をあらためて見直すことが大切ではないでしょうか。
<参考文献>
[1] Garrido, E. C., Issa, T., Gutierrez Esteban, P., and Cubo Delgado, S. (2021). A descriptive literature review of phubbing behaviors. Heliyon, 7(5), e07037.
[2] David, M. E., and Roberts, J. A. (2020). Developing and testing a scale designed to measure perceived phubbing. International journal of environmental research and public health, 17(21), 8152.
[3]Knausenberger, J., Giesen-Leuchter, A., and Echterhoff, G. (2022). Feeling ostracized by others’ smartphone use: The effect of phubbing on fundamental needs, mood, and trust. Frontiers in Psychology, 13, 883901.
[4] Abeele, M. M. V., Hendrickson, A. T., Pollmann, M. M., and Ling, R. (2019). Phubbing behavior in conversations and its relation to perceived conversation intimacy and distraction: An exploratory observation study. Computers in Human Behavior, 100, 35-47.
[5] Mantere, E., Savela, N., and Oksanen, A. (2021). Phubbing and social intelligence: Role-playing experiment on bystander inaccessibility. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(19), 10035.
[6] Chotpitayasunondh, V., and Douglas, K. M. (2018). The effects of “phubbing” on social interaction. Journal of applied social psychology, 48(6), 304-316.
[7] Yao, S., and Nie, T. (2023). Boss, can’t you hear me? The impact mechanism of supervisor phone snubbing (phubbing) on employee psychological withdrawal behavior. Healthcare, 11(24), 3167.
[8] Saxena, A., & Srivastava, S. (2023). Is cyberloafing an outcome of supervisor phubbing: Examining the roles of workplace ostracism and psychological detachment. International Journal of Business Communication. Advance online publication.
[9] Roberts, J. A., and David, M. E. (2017). Put down your phone and listen to me: How boss phubbing undermines the psychological conditions necessary for employee engagement. Computers in Human Behavior, 75, 206-217.
[10] Zhen, Y., and Wen, C. Y. (2022, November). The Impact of Boss Phubbing on Employees’ Job Performance: A Mediation Model with Moderation. In 2022 7th International Conference on Robotics and Automation Engineering (ICRAE) (pp. 384-387). IEEE.
[11] Xu, T., Wang, T., and Duan, J. (2022). Leader phubbing and employee job performance: The effect of need for social approval. Psychology Research and Behavior Management, 15, 2303-2314.

著者紹介
伊達洋駆(だて ようく)
株式会社ビジネスリサーチラボ代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(すばる舎)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。